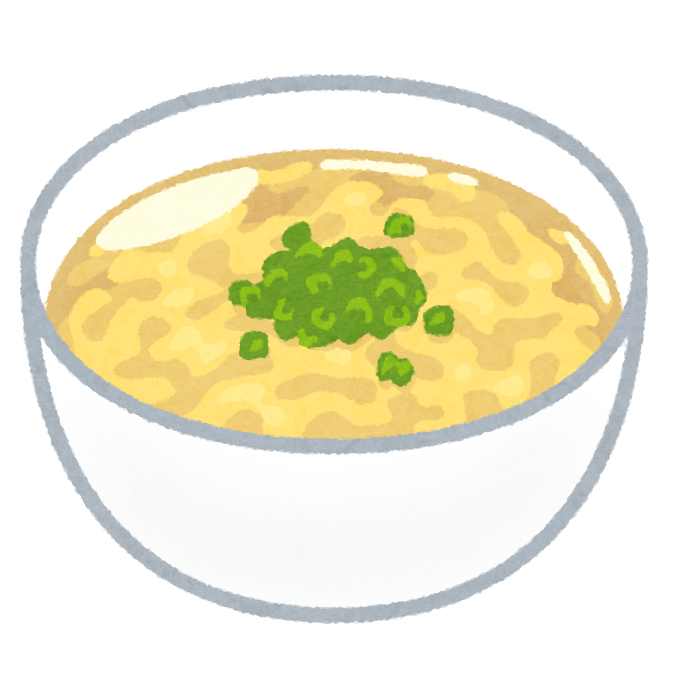
あなたの愛犬が最近、ごはんを残すようになったり、水をあまり飲まなくなっていませんか?
それは腎臓病のサインかもしれません。
「療法食だけでは食べない…でも何をあげればいい?」と悩む飼い主さんも多いのではないでしょうか。
でも安心してください。
実は、家庭で作れる手作りスープひとつで、愛犬の食欲を取り戻し、体調管理までサポートできる方法があります。
本記事では、腎臓にやさしく、しかも犬が喜んで飲むスープの作り方から、ステージ別の工夫、毎日のチェックポイントについて徹底解説します。
腎臓病の愛犬の食事に悩んでいる飼い主さんに、是非読んでいただきたい内容です。
目次
腎臓病犬に手作りスープが
注目される理由

「この子のために、何かできることはないかな」
愛犬の腎臓病と向き合う飼い主さんの多くが、そんな思いでいるのではないでしょうか。
療法食を嫌がったり、食欲が落ちたり、飲水量が減ったり…。
焦る気持ちの裏にあるのは、ただひとつ“少しでも楽に過ごしてほしい”という深い願いですよね。
そんな中で注目されているのが、手作りスープです。
スープは「食べさせなきゃ」というプレッシャーを少し軽くしながら、愛犬が自分のペースで水分と栄養をとりやすい形です。
以下の理由から、多くの飼い主さんに選ばれています。
- 飲み込みやすく、自然と水分補給ができる
- 温かい香りで、落ちた食欲をそっと刺激してくれる
- 食材を調整しやすく、愛犬の体調に合わせやすい
- 「自分にもできることがある」という心の支えになる
本章では、腎臓病の犬に手作りスープが注目される理由と、状態に応じた取り入れ方について解説します。
愛犬の今の状態に合わせたケアを考える際のヒントとして、参考にしていただければ幸いです。
犬の腎臓病の
実情と食事の重要性
腎臓病は、ある日突然わかることが多く、「もっと早く気づいてあげられたら…」と自分を責めてしまう飼い主さんも珍しくありません。
でも、どうか覚えていてください。腎臓病は誰のせいでもなく、気づいた“その日から”できることを重ねていく病気です。
腎臓病の犬が抱えやすいのは、次のようなつらさです。
- 食欲が落ちて、好きだったごはんをなかなか口にしない
- お水をあまり飲まなくなり、脱水が心配になる
- リン・塩分・タンパク質の調整が必要で、食事選びが難しい
だからこそ、まずは「食べる・飲む」ことを無理なく続けられる工夫が大切です。
スープはその一歩としてとても有効。体に優しく、香りで気持ちを引き上げるサポートもできます。
かかりつけの獣医師さんに相談しながら進めると、より安心して取り入れられます。
スープ形式の手作り食が
選ばれる理由
「スープなら飲んでくれた」
「これなら食べてくれるかも」
そんな小さな希望が、飼い主さんの心を支えてくれます。

スープが腎臓病の子に向いている理由を解説します👇
自然に水分を確保できる
腎臓病では“脱水を防ぐこと”がとても大切です。
でも、無理に飲ませることはできませんよね。
スープは、愛犬が「おいしい」と感じながら自然と水分をとれる優れた方法です。
消化への負担が少ない
体力が落ちている時期は、消化に負担がかからないことが大切です。
具材を細かく煮ることで、弱った体にも優しい形で栄養を届けられます。
香りで食欲を刺激できる
温かいスープの香りは、食欲が落ちた犬にとって心地よい刺激になります。
どうしても食べてほしいときの、小さな“きっかけ作り”に役立ちます。
成分コントロールができる
市販フードでは難しい「塩分ゼロ」「タンパク質少なめ」などの調整ができるのも手作りの大きな利点です。
愛犬のその日の体調に合わせて、やさしく調整してあげられます。
腎臓病ステージ毎の
スープ活用術
腎臓病のステージによって、スープの役割は少しずつ変わります。
「今のうちの子には何がベスト?」と悩む飼い主さんが安心して判断できるように整理しました。
【ステージ1〜2(初期〜中期)】
水分補給と嗜好性アップが目的
この段階では、腎臓の働きはまだ残っており、「水分を多く摂らせる」ことが最優先です。
鶏むね肉・かぼちゃ・にんじん・キャベツなどを薄味で煮て、香り高いスープを与えましょう。
ポイントは「塩・しょうゆ・だしの素」を一切使わないことです。素材の旨みだけで十分です。
【ステージ3(進行期)】
負担を減らしながら“栄養を入れる”
腎臓機能が落ち始めると、食欲が落ちる犬が増えます。
この時期は、スープに低リン・低ナトリウムの具材を選びましょう。
例えば、白身魚・じゃがいも・ブロッコリー・キャベツなど。
だしは「煮干し」ではなく「鶏むね」または「かつお削り節の薄味」もおすすめです。
【ステージ4(末期)】
“少しでも口にしてくれる”ことが最優先
腎臓病末期の愛犬は、食欲がほとんどなくなります。
この時期の目的は「完璧な栄養バランス」ではなく、“食べられること”。
愛犬が好きな香り・舌触り・温度を徹底的に合わせ、“スプーン1杯でも食べてくれたらOK”という気持ちで接してあげてください。

かかりつけの獣医師さんと相談しながら、愛犬にあったスープを作ってあげてね。
腎臓病の犬に
手作りスープを作る前に
押さえておきたいポイント

「腎臓病の愛犬のために、少しでも食べやすく、飲み込みやすく、負担の少ない “手作りスープ” を作ってあげたい」
愛犬の腎臓病と向き合う飼い主さんの多くが、そんな思いでいるのではないでしょうか。
しかし、腎臓病の犬の食事づくりには、通常の手作りご飯とは異なる特別な配慮が必要です。
愛犬の腎臓病と向き合う飼い主さんが抱く悩みとしては、
- 「どの食材が腎臓に悪いの?」
- 「逆に積極的に使っていい食材は?」
- 「スープにしても大丈夫?」
- 「リンやたんぱく質の制限ってどう考えればいい?」
と言った内容ではないでしょうか。
これらの疑問が解消するよう、実際に腎臓病の犬の食事で押さえるべき栄養学的なポイントをまとめました。
腎臓に負担をかける栄養素と
避けるべき食材
腎臓病の犬にとって、“避ける”べき栄養素と食材を知ることが第一歩です。
リン(P)
リンは骨や歯の健康に必要なミネラルですが、腎臓病になると余分なリンを体外に排出できなくなります。
血中リン濃度が高いと、腎臓へのダメージが進みやすくなります。
ナトリウム(塩分)
塩分を摂りすぎると、体が水分をため込み血圧が上昇。腎臓にさらなる負担をかけてしまいます。
たんぱく質(過剰摂取)
腎臓病では、「たんぱく質の過剰摂取」も大敵。
たんぱく質が分解される過程で老廃物(尿素窒素)が発生し、それを排出するのが腎臓の仕事です。
つまり、摂りすぎると腎臓に過剰な負担を与えてしまいます。
添加物・香辛料・油分
市販のスープの素やコンソメ、味付き肉などは厳禁。
塩分だけでなくリン酸塩などの保存料や添加物が多く、腎臓に負担を与えます。
腎臓ケアに取り入れたい
栄養素と推奨食材
腎臓病だからといって「減らす」ばかりでは栄養不足に陥り、筋肉量が落ちて生活の質を下げる原因にもなります。
腎臓を労わりながら、体力維持にもつながる栄養をご紹介します。
低リン・低ナトリウムの食材
白身魚(タラ・カレイ・タイ)や鶏むね肉、卵白は、リンが少なく腎臓にやさしいたんぱく源です。
抗酸化栄養素(ビタミンE・βカロテン・ポリフェノール)
腎臓の老化を抑えるために、抗酸化作用のある食材を取り入れましょう。
オメガ3脂肪酸
オメガ3脂肪酸は、炎症を抑え、腎臓病の進行を緩やかにする効果が期待されています。
■食物繊維
便通を整え、体内の老廃物を排出しやすくします。

ポイントは、“薄味で香りを活かす”ことだよ。
素材そのものの香りと旨みで嗜好性を高めることが、手作りスープ成功のカギ🔑
手作りスープの注意点
腎臓病の犬のスープは、健康な犬の手作り食とはまったく考え方が異なります。
特に次の点は必ず押さえておきましょう。
具材を煮込む時間と煮込み方
腎臓病犬は消化吸収力が落ちていることが多いため、具材は柔らかく煮るのが基本です。
ただし、煮込むほどリンやたんぱく質がスープに溶け出すため、ステージに応じて煮汁の使用量を調整する必要があります。
スープだけに頼りすぎない
水分摂取が大切とはいえ、スープは「栄養のメイン」にはできません。 あくまで、
- 水分補給のサポート
- 食欲が落ちた日の補助
- フードへのトッピング
といった目的で取り入れるのが安全です。
ステージによって調整が必須
腎臓病はステージ(G1〜G4)によって食事内容が大きく変わります。
特に進行ステージでは、スープの「煮汁を使うかどうか」も慎重に判断する必要があります。
ポイント!
- 初期 → 少量の煮汁もOK
- 中期 → 煮汁は薄めるか控えめに
- 後期 → 原則として煮汁なし(野菜のゆで汁なども控える)
好みが大きく分かれるため“試行錯誤”が必要
腎臓病の犬は食欲が落ちやすく、「昨日食べたスープを今日は食べない」ということも珍しくありません。
そのため、スープ作りは食材よりも“その子に合う形”を探す作業になります。
腎臓病犬は嗅覚が落ちることもあり、温度・香り・とろみが食欲を左右することは非常に多いです。
保存・衛生面
手作りスープは保存料を使わないため、雑菌が繁殖しやすいです。
冷蔵は3日、冷凍は2週間以内を保存の目安にしましょう。
調理後はすぐに冷ますし、小分け冷凍が理想です。
解凍時は電子レンジで温めすぎず、香りを逃がさないように注意しましょう。
スープの温度は人肌(35〜40℃)が理想です。
熱すぎると嗅覚が鈍り、冷たすぎると飲みにくくなります。
獣医師・栄養管理士に
相談すべきサイン
どんなに愛情を込めて作っても、犬の体調は日々変化します。
次のようなサインが見られたら、手作り食を一時中断し、すぐに獣医師に相談してください。
- 食欲が2日以上続けて落ちている
- 嘔吐・下痢・便秘が続く
- 体重が急に減った、または増えた
- 尿の量や色がいつもと違う
- スープを飲んだ後にぐったりする
また、「血液検査でクレアチニン値やBUNが上昇している」「療法食を完全に食べなくなった」という場合も、栄養管理士に“併用レシピ”を相談するのがおすすめです。
腎臓病犬のための
手作りスープレシピ

腎臓病の犬にとって、「食べやすく・水分を自然に摂れる」手作りスープは、日々の体調管理に大きな助けとなります。
本章では、栄養バランスを意識しつつ、自宅で簡単に作れる3つのスープレシピを紹介します。さらに、季節やステージに合わせたアレンジのコツ、失敗しやすいポイントも具体的に解説します。
低リン・低ナトリウム
野菜たっぷり和風だしスープ

腎臓病の初期〜中期におすすめの、体にやさしい定番スープです。
リンとナトリウムを抑えながら、野菜の自然な甘みで食欲を引き出します。
材料(小型犬1日分目安)
- 水 … 300ml
- キャベツ … 20g
- にんじん … 10g
- かぼちゃ … 10g
- しいたけ(軸を除く)… 1枚
- 鶏むね肉(皮なし)… 15g
- 昆布 … 3cm角1枚
作り方
- 鍋に水と昆布を入れて30分ほど浸す。
- 弱火でじっくり温め、沸騰前に昆布を取り出す。
- 具材をすべて加え、弱火で15〜20分煮る。
- 冷まして具材を細かく刻むか、ブレンダーでペースト状に。
ポイント
- 動物性だし(かつお節)はリンが高いため避ける。
- 具材の食感は、腎臓の状態や歯の健康に合わせて調整しましょう。
- 与える量は、愛犬の体重、体調に合わせて調整しましょう。
高嗜好・水分補給重視
魚エキス&コラーゲンスープ

「なかなか食べてくれない」「水分を摂らない」犬に最適なレシピです。
魚の香りで嗜好性を高め、コラーゲンで関節や皮膚の健康もサポートします。
材料(小型犬1日分目安)
- 水 … 350ml
- 白身魚(鱈・カレイなど)… 20g
- ゼラチン … 小さじ1/2(無添加)
- ブロッコリー(茎も可)… 10g
- 大根 … 10g
- オリーブオイル … 数滴
作り方
- 魚を熱湯でサッと湯通しして臭みを取る。
- 鍋に水と魚・野菜を入れて弱火で15分煮込む。
- 火を止めて少し冷まし、ゼラチンを溶かして軽くとろみをつける。
- オリーブオイルを最後に数滴加える。
ポイント
- とろみをつけることで「飲む」というより“舐めて食べる”感覚に。
- 白身魚の種類は週ごとに変えると飽き防止になります。
- 具材の大きさ、与える量は、愛犬の体重、体調に合わせて調整しましょう。
シニア期・療法食併用期向け
栄養補助&冷凍保存スープ

療法食をメインにしている犬でも使いやすい、「トッピング感覚」の栄養補助スープです。
少量でも水分とミネラルを補えます。
材料(製氷皿約6個分)
- 水 … 400ml
- 鶏ささみ … 20g
- かぼちゃ … 10g
- きのこ類(舞茸・えのき等)… 10g
- 無塩の野菜だしパウダー … 少量
作り方
- 具材をすべて弱火で15分煮込む。
- 火を止め、粗熱をとってからブレンダーで滑らかに。
- 製氷皿に流し入れて冷凍保存。
- 与える際は1個分(約50ml)を自然解凍または湯せんで温める。
ポイント
- 療法食に直接かけてもOK。香りで食欲を刺激しましょう。
- 冷凍のまま与えない(腸を冷やすため)ようにしましょう
- 具材の大きさ、与える量は、愛犬の体重、体調に合わせて調整しましょう。
応用アレンジ:
季節/体調/好みに応じたカスタマイズ
腎臓病犬の状態や季節によって、同じスープでも少しの工夫で使い分けができます。
以下の表を参考にカスタマイズしてみてください。
| 状況 | アレンジ例 | ポイント |
|---|---|---|
| 夏バテ気味 | スープを少し冷やし、きゅうりやトマト少量を追加 | 食欲増進&水分補給 |
| 冬の冷え対策 | 生姜のごく少量を加えて温め効果 | 体温維持・代謝UP |
| 食欲不振 | 鶏スープベースにごま油を1滴 | 香りで嗜好性UP |
| 下痢気味 | 具材を完全ペーストにして消化を助ける | 胃腸への負担軽減 |
注意点: アレンジはあくまで軽度症状や季節対応。数値が悪化している場合は必ず獣医師に確認をしましょう。
失敗しがちなポイントと
その回避法
手作りスープはやさしい反面、油断すると腎臓に負担をかけてしまうこともあります。
よくある失敗例と回避法を紹介します。
| 失敗例 | リスク | 回避法 |
|---|---|---|
| かつおだし・チキンスープを使用 | リン・ナトリウム過多 | 昆布・野菜だしに切り替え |
| 味見して塩分を足す | 犬にとって過剰塩分 | 塩・しょうゆ・味噌は一切不要 |
| 魚の骨を取り忘れる | 消化不良・喉詰まり | 骨は必ず全除去 |
| 作り置きを常温放置 | 細菌繁殖・下痢 | 冷蔵2日以内・冷凍1週間以内で管理 |
| 脂肪を多く使う | 腎臓・肝臓負担 | 油はごく少量(数滴)で十分 |

腎臓病犬のスープづくりで大切なのは、“見た目より機能”!
「薄味すぎるかな?」と感じるくらいでちょうど良いバランスだよ。
手作りスープの
現実的な悩みと解決策

腎臓病と診断された愛犬のために「少しでもおいしく食べてほしい」「食欲を取り戻してほしい」と思い、手作りスープを検討する飼い主さんは少なくありません。
しかし同時に、「療法食をやめていいの?」「毎日作るのは大変そう」「栄養バランスが心配」など、現実的な不安も多いでしょう。
本章では、実際に多くの飼い主さんが抱く“4つのリアルな悩み”を取り上げ、その具体的な解決策をまとめました。
悩み①
診断されたら療法食しか与えられない?
腎臓病と診断されると、多くの獣医師から「療法食(腎臓サポート食)」の給餌を勧められます。
確かに、療法食は科学的に栄養設計されており、リン・ナトリウム・たんぱく質の量が厳密にコントロールされています。
したがって、病期が進行している犬にとっては“安全で効果的な選択”です。
一方で、「療法食しかダメ」と思い込む必要はありません。
実際、多くの獣医栄養学のガイドライン(AAHAやNRCなど)でも、「嗜好性が落ちて食べない場合は、手作りで食欲を維持することも選択肢」とされています。
つまり、“食べない療法食”より“食べる手作りスープ”のほうが、結果的に腎臓へのダメージを防ぐケースもあるのです。
ただし注意点として、完全に療法食をやめるのではなく、「療法食+手作りスープの併用」や「一部トッピングとして利用」という段階的な導入がおすすめです。
獣医師と相談しながら、無理なく進めていきましょう。
悩み②
手作りごはんは
時間・コストがかかるのでは?
「毎日煮出して、食材を細かく刻んで…そんな時間ない!」という声はとても多いです。
しかし、腎臓病犬のスープ作りは“時短・低コスト”に工夫できるのが特徴です。
例えば、鶏むね肉・かぼちゃ・キャベツ・にんじんなど、腎臓に優しい定番食材をまとめて煮込み、冷凍キューブ化しておけば、1週間分を一度に準備できます。
出汁は煮干しではなく鶏ガラや野菜出汁を使うと、リンやナトリウムを抑えながら旨味を引き出せます。
最近では獣医師監修の冷凍手作りスープ(市販)も登場しており、忙しい日だけそれを活用するのも現実的な方法です。
「完璧にやらなきゃ」と思うよりも、“食欲を支える工夫”を続けることが最も大切です。

わが家では、愛犬のご飯の食材の残りを食べていました。
食材を共有できれば、コスパも良いですね❣️
悩み③
どうやって成分・量を
管理すればいい?
手作りスープを始めた飼い主さんの多くが感じるのが、「どのくらいのたんぱく質やリン量が適正なの?」という疑問です。
結論から言えば、家庭での完全計算は難しく、おおまかなバランス感覚と獣医師の定期チェックの併用が理想です。
基本の目安としては以下の通りです:
| 項目 | 腎臓病犬向けの目安 | ポイント |
|---|---|---|
| たんぱく質 | 体重1kgあたり1.8〜2.5g/日(軽度) | 動物性+植物性をバランスよく |
| リン | できるだけ低く(骨・内臓を控える) | 出汁やスープの素材で調整 |
| ナトリウム | 塩分無添加 | 人用スープの流用はNG |
| 水分 | 体重1kgあたり約50〜60ml/日 | スープで自然に摂取できる |
「腎臓数値が安定している時期」と「悪化傾向が見られる時期」で食事内容を微調整することが大切です。
迷ったときは、ペット栄養管理士にレシピを見てもらうのも安心です。
悩み④
うちの犬は好き嫌い・偏食で…
腎臓病の犬は、味覚や嗅覚の変化により“これまで食べていたものを急に嫌がる”ことがよくあります。
この場合、香り・温度・食感の3要素を見直してみましょう。
食欲改善の3要素
- 香り:
鶏ささみや白身魚を少量加えると嗜好性がアップすることがあります。 - 温度:
人肌(約38℃前後)に温めることで香りが立ち、食欲を刺激します。 - 食感:
ミキサーでとろみをつけると、飲み込みが楽になるケースもあります。
毎回同じ味だと飽きてしまうため、数種類のスープをローテーションするのもおすすめです。
「今日は鶏と野菜」「明日は白身魚と豆腐」など、バリエーションを持たせることで、食べる楽しみを取り戻せることがあります。
それでも食欲が落ちるときは、脱水や口内炎などの身体的原因が隠れていることもあるため、早めに動物病院で相談をしましょう。
スープは“治療”ではなく“サポート食”です。
だからこそ、無理なく続けられる形で、愛犬と一緒に向き合っていくことが大切です。
手作りスープ活用時の
チェックリスト

腎臓病の愛犬に「手作りスープを続けたい」と思う一方で、多くの飼い主さんは「うちの子に本当に合っているのか?」という不安を抱いているのではないでしょうか。
腎臓病はゆっくり進行する病気のため、毎日の小さな変化を見逃さないことが、とても重要です。
本章では、「スープ活用時にチェックすべき具体的な項目」を、家庭で実践しやすい形でまとめました。
毎日のチェック項目
スープを導入したら、まず意識したいのが毎日の変化の観察です。
腎臓病は進行性のため、日々のわずかなサインを見逃さないことが大切です。
| チェック項目 | 見るポイント | 注意すべき変化 |
|---|---|---|
| 食欲 | スープを飲む量、食べ方 | 急に飲まなくなる・嫌がる |
| 尿量 | 回数と量、色 | 極端に増減・濃い色尿・血尿 |
| 体重 | 週1回を目安に測定 | 急な減少(脱水・筋肉量低下) |
| 飲水量 | 1日あたりの摂取量 | 体重1kgあたり約50mlが目安。急な増減に注意 |
スープで水分を摂るようになると、飲水量が減っても脱水ではない場合があります。
そのため、スープの量も含めた総水分摂取量を把握するのがポイントです。
食欲が安定していても体重が減少している場合は、カロリーが足りていない可能性があります。

毎日のチェックは、ノートやアプリで記録するのがおすすめだよ🖊️
記録があると、獣医師さんに相談する時に役立つよ❣️
血液検査で見る
腎臓の指標と変化の目安
スープ導入の効果を客観的に判断するには、血液検査データのチェックが欠かせません。
主に見るべき指標は以下の通りです。
重要な腎臓関連指標
| 指標名 | 意味 | スープ導入時に注目する理由 |
|---|---|---|
| BUN(尿素窒素) | タンパク質代謝の結果生じる老廃物。腎機能低下や脱水で上昇する。 | 急激な変化は脱水や食事バランスの乱れを示すことがあるため。 |
| Cre(クレアチニン) | 腎臓病の進行度を示す代表的な指標。筋肉量の影響も受ける。 | スープの導入で改善はしにくいが、安定していれば良好なサイン。 |
| SDMA | 初期腎臓病でも上昇しやすい高感度マーカー。 | スープ導入後の負担が少ない場合、悪化が進みにくい。 |
| リン(P) | 腎機能低下で上昇しやすく、病態悪化を促進する。 | 野菜スープの素材によってリン量が増える可能性があるため。 |
| カリウム(K) | 体液バランスや心機能に関わる。腎臓病では高低どちらも危険。 | 食材の種類やスープ量によって上下しやすいため。 |
| TP / Alb(総蛋白 / アルブミン) | 栄養状態、脱水、蛋白喪失の指標。 | スープ導入後の栄養状態や水分バランスの変化を把握できる。 |
スープ導入後にBUNやクレアチニンが急上昇しなければ、腎臓への負担を増やしていない証拠といえます。
リンの数値が上がる場合、食材に鶏レバーや魚の骨などリンの多い部分が含まれていないかを見直しましょう。
スープ導入後に期待できる変化の目安
腎臓病期ではデータ値の改善を目指すのではなく、”悪化を止める”ことが目標です。
期待できる目安は以下のような内容です。
スープはあくまで腎臓病管理のサポート食です。
検査値の改善ではなく、数値の「安定」を目指しましょう。
スープ導入3〜6か月後に
確認したいこと
腎臓病管理は「短期改善」よりも長期的な安定が大切です。
スープを始めて3〜6か月経過したら、次の項目をチェックしましょう。
タイトルテキスト
- 体調面の変化
・元気、排尿、被毛のツヤなど
・「なんとなく調子が良さそう」が継続していれば◎ - 水分摂取量
・スープなしでも飲めているか、あるいはスープにより十分補えているか - 体重の推移
・減り続けていないか、維持できていれば◎ - 血液検査の推移
・数値の改善はもちろん、悪化していないことも大きな成果
・3か月ごとの検査を推奨 - 尿検査
・尿比重・尿タンパクの変化を確認(腎臓病は尿の変化が早い) - 食事内容の見直し
・野菜や具材が偏っていないか - 食いつきの安定
・初期は喜んで飲んでも、飽きる場合もある
・具材や香りの工夫で無理なく続けられるようにしましょう
毎回同じ味のスープより、野菜を少し変えるだけでも嗜好性が変わります。
ただし、塩分やリンの多い食材(ツナ缶、鶏皮、乳製品など)は避けることを忘れないようにしましょう。
最も重要なのは、“スープが生活の質(QOL)改善につながっているか”という視点です。
食事に喜びを感じ、食べてくれる時間が増えているなら十分成功と言えます。
他のサポート食との併用注意点
腎臓病の犬では、スープだけで栄養を完結させるのは難しいため、療法食やサプリメント、水分補給アイテムとの併用を行うケースが多いです。
しかし、これらを併用する際には重複成分と塩分量に注意が必要です。
療法食との併用について
- 療法食の栄養バランスを崩さないことが最優先です。
- スープは「香り付け」「水分補給」として少量をかける程度にしましょう。
- 丸ごとの食材(芋・カボチャ)を多く入れすぎると炭水化物過多になることもあるので注意しましょう。

スープがおいしすぎて療法食を食べなくなる場合もあるから、トッピング的に少量からスタートするのがオススメだよ。
サプリメントとの併用は要確認
- リン吸着剤を使用している場合、リンの多い野菜スープと組み合わせると負担になることがあります。
- オメガ3脂肪酸サプリを使用中なら、脂質の追加は控えめにしましょう。
- カリウム制限が必要な子には、ほうれん草やかぼちゃのスープは要注意です。
手作りトッピングとの併用
スープ、トッピング、療法食…と複数の手作り食品を組み合わせると、 知らないうちに「総量オーバー」を起こしてしまうことがあります。
併用する場合は、必ず以下を守りましょう。
併用のポイント
- 1日の総カロリーは犬の体重×(年齢・活動量別の係数)で管理しましょう
- トッピングとスープの具材は「合計で体重×0.5〜1%」以内が目安です
- 数値の確認は、獣医師と相談しながら調整しましょう
愛犬にとって最適な
スープライフのために
できること

手作りスープを取り入れることは、単なる“ごはんの工夫”ではなく、愛犬の生きる力を支える選択です。
本章では、「どう始めればいいの?」という飼い主さんに向けて、今日から実践できる3つのステップと、愛犬に合ったスープの考え方をご紹介します。
あなたの愛犬にとって最適なスープライフを、今日から一緒に始めましょう。
今日から実践できる3つのステップ
①食材リストを作る
- 腎臓にやさしい食材は、低リン・低ナトリウム・消化が良いものを選びましょう。
- 代表的なのはキャベツ・大根・にんじん・かぼちゃ・さつまいも・鶏むね肉(皮なし)・白身魚などです。
- “OK食材リスト”を作ることで、迷わずスープ作りを始められます。
- 苦手食材がある場合は、少量ずつ加えて嗜好を確認するのもポイントです。
②冷凍スープを仕込む
- 忙しい日も続けられるコツは、まとめて作って冷凍しましょう。
- 野菜を細かく刻み、鶏肉や魚を加えて煮出したら、スープだけを小分け冷凍するのがおすすめです。
- 氷のキューブトレーを使えば、1回分を解凍するだけで便利です。
- 解凍時にぬるま湯を少し加えると香りが立ち、食欲が落ちた愛犬でも反応しやすくなります。
③スープ日記をつける
- 手作りを始めたら、食べた量・尿量・体調・血液検査を簡単にメモしておきましょう。
- スープ導入前後で比較できると、効果の実感が得やすくなります。
- また、動物病院で相談する際にも「どんなスープを、どのくらい与えたか」が伝わるため、より的確ながもらえます。

腎臓病のケアは長期戦です。
飼い主さんも無理をしすぎず、できることから一つずつ始めてみてください。
愛犬の「スープパターン」を知る
犬にもそれぞれ「スープとの付き合い方」があります。
性格や年齢、嗜好によって、最適なスープパターンを見つけることが重要です。
| タイプ | 特徴 | おすすめスープの与え方 |
|---|---|---|
| 慎重派タイプ | 初めての味に警戒する | いつものフードに少量混ぜて慣らす |
| グルメタイプ | 飽きっぽく好みが変わる | 香りを変える(かぼちゃ・ささみ・白身魚でローテ) |
| シニアタイプ | 噛む力・嗅覚が低下している | 柔らかめ&香り重視(鶏スープベース+野菜) |
| 元気はあるけど食欲に波あり | 体調で嗜好が変わる | 体調良い日に新しい食材を試し、好みを記録 |
ここで大切なのは、「どんなスープが一番喜ぶか」を観察して探すプロセスです。
腎臓病の管理は、数値を追うだけでなく、「今日もおいしく食べた」という日々の積み重ねが何よりの励みになります。
あなたの愛犬は、どのタイプに近いでしょうか?
ぜひ、明日のスープ作りの参考にしてみてください。
まとめ

- 腎臓病犬に手作りスープは強力なサポート食です
- 食欲が落ちた犬でも、水分と栄養を同時に摂ることができます
- 脱水予防と体調維持の両面から役立ちます
- 療法食との併用が基本です
- 完全に置き換えるのではなく、トッピングや水分補給として活用します
- 少量から導入することでリスクを抑えられます
- 食材選びは低リン・低ナトリウム・消化性重視が基本です
- 鶏むね肉、白身魚、かぼちゃ、キャベツ、さつまいもなどが代表例です
- 高リン食材や塩分の多い食品は避けましょう
- 冷凍保存を活用すると無理なく継続できます
- まとめて作り、小分け冷凍することで日々の負担を軽減できます
- 解凍時にぬるま湯を加えると香りが立ち、食欲を刺激しやすくなります
- 毎日の観察と記録が重要です
- 食欲・体重・尿量・飲水量を日々チェックしましょう
- BUN・クレアチニン・リン・ナトリウムなどの血液検査と併せて評価すると分かりやすいです
- 愛犬に合わせたスープパターンを作りましょう
- 年齢・性格・食欲に応じて、香りや具材、温度を調整します
- ローテーションすることで飽きを防ぎやすくなります
- サプリや療法食とのバランスに注意が必要です
- 成分の重複や塩分量を必ず確認しましょう
- 不安がある場合は、獣医師や栄養の専門家に相談すると安心です
- 継続こそが最大のポイントです
- 腎臓病のケアは長期戦であることを理解することが大切です
- 手作りスープを「食べる楽しみ」と「水分・栄養補給」を両立する手段として、無理なく続けましょう
本記事が、皆さまの愛犬が少しでも穏やかで健やかな時間を過ごすための参考になれば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

📚<主な参考文献・情報>
- Akita, K., & Yamamoto, T. (2020). 犬の慢性腎臓病と食事管理. 日本小動物獣医師会誌, 71(4), 210-218.
- 川野浩志ほか(2020)『犬と猫の治療ガイド2020 小動物編』インターズー.
- 小動物臨床栄養学研究会. (2019). 犬の腎臓病における水分補給と手作り食の実践ガイド. ペット栄養学ジャーナル, 15(2), 45-52.
- 一般社団法人 日本ペット栄養学会(2020)『犬と猫の栄養ガイドブック 第2版』.
- AAFCO (2021). Dog and Cat Food Nutrient Profiles. Association of American Feed Control Officials.
- AAHA (2021). AAHA Nutritional Assessment Guidelines for Dogs and Cats.
https://www.aaha.org/aaha-guidelines/nutritional-assessment/- International Renal Interest Society (IRIS). “IRIS Staging of CKD.” IRIS Kidney, 2024.
https://www.iris-kidney.com/guidelines/staging.html- Merck Veterinary Manual. “Chronic Kidney Disease in Dogs.” Merck Veterinary Manual, 2024.
https://www.merckvetmanual.com/urinary-system/chronic-kidney-disease/chronic-kidney-disease-in-dogs- National Research Council (NRC) (2006). Nutrient Requirements of Dogs and Cats. National Academies Press.
- Polzin, D. J. (2011). Chronic Kidney Disease in Dogs and Cats. Veterinary Clinics of North America.
※本記事は上記の獣医腎臓病ガイドラインおよび栄養学資料を基に、一般飼い主向けに要点を再構成しています。 愛犬の病状や食事管理については個体差があるため、具体的な治療方針や食事内容の決定にあたっては、必ずかかりつけの獣医師にご相談ください。