
あなたの愛犬が最近、水をあまり飲まなくなったり、食欲が落ちてきていませんか?
もしかすると、それは腎臓病の初期サインかもしれません。
「でも、療法食だけでは水分が足りないし、食いつきも悪い…」
そんな悩みを抱える飼い主さんに注目されているのが、“腎臓に優しい野菜スープ”です。
一見ただのスープに見えるかもしれませんが、作り方や素材を工夫するだけで、愛犬の体調を支え、食欲を刺激し、腎臓の負担を軽くする効果が期待できるのです。
本記事では、市販品と手作りの違い、ステージ別の与え方、注意すべきポインについてまとめました。。
愛犬の食事に野菜スープを取り入れたいと考えているあなたに、是非読んでいただきたいです。
目次
腎臓病の犬に野菜スープが
注目される理由

腎臓病の愛犬と暮らしている飼い主さんの多くが、「食べてくれない」「水を飲まない」「療法食だけではかわいそう」と悩んでい流のではないでしょうか。
愛犬が腎臓病と診断された場合、基本は獣医師推奨の腎臓ケア用治療食を与えることが重要です。
しかし、治療食をどうしても食べない場合や食欲が落ちている場合は、野菜スープを補助食として活用することができます。
「野菜スープなら安心」と思って自己流で作ると、かえって腎臓に負担をかけてしまうこともあります。
本章では、犬の腎臓病の基本から、野菜スープが選ばれる理由、そして“ただのスープでは危険な理由”について解説します。
犬の腎臓病とは:
症状・進行・食事療法の基本
犬の腎臓病とは、腎臓の機能が徐々に低下し、老廃物をうまく排出できなくなる病気です。
特に高齢犬では発症率が高く、慢性腎臓病として長期的なケアが必要になるケースがほとんどです。
腎臓病の主な症状
- 水をよく飲む、尿の量が増える
- 食欲の低下、体重の減少
- 嘔吐、元気がない
- 口臭(アンモニア臭)
- 毛艶が悪くなる、皮膚が乾燥する
初期のうちは目立った症状がないため、気づいたときには進行していることも少なくありません。
腎臓病ケアで大切なこと
腎臓は一度ダメージを受けると再生しにくい臓器です。
そのため、「これ以上悪くしない食事管理」が最も重要になります。
腎臓病の犬に適した食事の基本は、
- たんぱく質とリンの制限
- ナトリウム(塩分)を控える
- 十分な水分を摂る
この3つです。
水分をしっかり摂ることが、腎臓の負担を軽減し、老廃物の排出を助けます。
しかし、腎臓病になると嗜好性が落ちて水を飲まなくなる犬も多く、「どうすれば水分を取ってくれるか?」という悩みを持つ飼い主さんも少なくないでしょう。
野菜スープが選ばれる理由
腎臓病の犬に野菜スープが注目される理由には、以下のような背景があります。
食欲が落ちた犬でも口にしやすい
腎臓病が進むと、固形物を嫌がったり匂いに敏感になったりして、食べなくなることがよくあります。
温かいスープは香りが立ち、胃腸への負担も少ないため、食べてくれることも多いようです。
水分と栄養を同時に摂れる
腎臓病では水分摂取が最優先です
ただの水では飲みたがらなくても、旨味を含んだスープなら自ら飲んでくれることもあります。
胃腸に負担をかけずに栄養補給ができる
野菜に含まれるビタミン・抗酸化成分・食物繊維は、腎臓病のサポート食として役立つ成分も多くあります。
ただし、後述するように「どの野菜でも良いわけではない」点が重要です。
低たんぱく・低リンで腎臓にやさしい
野菜はもともとたんぱく質が少なく、リンやナトリウムも控えめです。
肉や魚のように腎臓に負担をかけにくいため、腎臓病の犬の食事に取り入れやすい食材です。
手作りスープの心理的メリット
愛犬の腎臓病は、飼い主さんにとって精神的にも大きな負担になります。
「少しでもおいしく食べてほしい」という飼い主さんの思いを叶えてくれます。
手作りすることで、愛犬の好みに合わせた調整ができ、食事時間がストレスから“癒しの時間”へと変わります。

腎臓を守るためには、「おいしさ」「水分量」「栄養バランス」を考えてね。
“ただの野菜スープ”ではダメな理由
腎臓病の犬に良いとされる野菜スープですが、ここに意外な落とし穴があります。
野菜の中には、腎臓に負担をかける成分を多く含むものもあります。
特に注意すべきなのが「リン」「カリウム」「ナトリウム」です。
野菜によってはリンが多く、腎臓に負担をかける
リンは骨の健康に欠かせませんが、腎臓病の犬では排出機能が低下しており、体内に蓄積しやすくなります。
過剰になると腎臓への負担が増え、症状を悪化させる原因に。
ほうれん草・小松菜・ブロッコリー・豆類など、リンを多く含む野菜は控えめにしましょう。
カリウム:心臓・神経にも影響
腎臓病が進行すると、カリウムの排出もうまくできなくなります。
過剰なカリウムは不整脈や筋肉の異常を引き起こすこともあります。
にんじんやかぼちゃなども茹でこぼしてから使うと、安全性が高まります。
⚠️高カリウム血症の指摘がある愛犬は、煮汁を薄める・与える量を減らすなどの工夫はできますが、まずは獣医師に相談しましょう。
ナトリウム:絶対に追加しない!
人間のスープ感覚で塩やだしを加えるのは厳禁です。
野菜に含まれる“天然ナトリウム”が煮汁に溶け出すため、ナトリウム制限中の犬は量に注意が必要です。
腎臓病の犬にとってナトリウムの過剰摂取は、腎臓へのさらなる負担を引き起こします。
“濃いスープ”は逆に腎臓の負担に
野菜の旨味がたっぷり出たスープは、犬が喜んで飲むこともありますが、濃度が高すぎると老廃物の負担になったり、ミネラル過多につながることがあります。
腎臓病の犬には薄いスープが基本です。
手作りでは栄養バランスが偏りやすい
腎臓病は「ただ水分を摂らせる」だけでは不十分で、必要な栄養も確保する必要があります。
また、腎臓病では“タンパク質ゼロ”ではなく、“質と量の調整”が必要です。
スープだけでは栄養が不足しがちなため、療法食や獣医師の指示と併用することが大前提です。
愛犬のステージによって“適したスープ”が違う
犬の腎臓病は進行性の病気で、症状や検査結果に応じてステージⅠ~Ⅳに分けられます。
ステージによって必要な食事や水分量が変わるため、愛犬に合ったスープ作りが大切です。
必ず獣医師の診断や指示を確認しましょう。
ステージⅠ〜Ⅱの犬と、Ⅲ〜Ⅳの犬では必要な水分量・エネルギー量・禁止食材が異なります。
たとえば:
・初期(ステージⅠ〜Ⅱ)
→薄いスープで水分補給を促し、野菜の抗酸化成分を補う
・中期〜後期(ステージⅢ〜Ⅳ)
→スープはより薄めにし、カロリーは別の形で補わないと体重が減る
このように、腎臓病の進行度によって「良いスープの条件」が変わるため、獣医師と相談しながら進めることが重要です。
そして何より大切なのは、飼い主さんが悩みながらも「愛犬のために選んだ」という気持ちが、食事ケアの継続につながるということです。
無理のない範囲で、愛犬に合ったスープ選びをしていきましょう。

間違った分量や食材選びで逆効果になることもあります。
獣医師またはペット栄養士のアドバイスを受けながら調整することが最善策です。
腎臓病の愛犬と暮らす
飼い主さんの悩みと解決策

愛犬が腎臓病と診断されると、「ごはんを食べてくれない」「水分が足りない」「何をあげれば腎臓に優しいの?」など、次から次へと不安が出てきます。
特に、療法食を食べない・水分が不足するという悩みは、多くの飼い主さんが抱える大きな問題です。
そんな中で注目されているのが、腎臓に負担をかけずに水分・栄養を補える“野菜スープ”です。
野菜の旨みと自然な香りで食欲を刺激し、無理なく水分補給ができることから、腎臓病の愛犬におすすめです。
療法食だけでは
水分が足りない・食いつきが悪い
腎臓病の犬は、体の老廃物を排出するために多くの水分が必要です。
しかし、療法食はドライタイプが多く、「水をあまり飲まない」「食いつきが悪い」と悩む声が非常に多いです。
腎臓病の犬にとって、「水分をしっかりとること」はとても重要です。
そこで役立つのが野菜スープです。
スープの香りが食欲を引き出し、療法食に適度な水分を加えることで消化もしやすくなります。
とくに、嗅覚で食べる犬にとって香りは強い“食欲スイッチ”になることが期待できます。
野菜スープで“自然な水分補給”
野菜スープは水分補給と食欲アップの両立ができる救世主になります。
温かいスープに野菜の甘みや香りをプラスすることで、嗅覚の鈍くなった犬でも食欲を刺激できます。
実際、療法食にスープを少量かけるだけで食いつきが改善することもあります。
“食べる喜び”を取り戻すことが大切
腎臓病の犬にとって大切なのは、「食べられる状態を保つこと」です。
無理に完璧な食事管理をするよりも、“食べることを続ける工夫”の方が長期的に健康を支えます。
野菜スープは、その第一歩として最適です。
何をどう調整すれば
腎臓に優しい食材になるの?
腎臓病では、リン・ナトリウム・タンパク質の量、そして調理方法がとても大切です。
野菜スープを作るときは、以下のポイントを押さえることで腎臓に優しい内容になります。
⭕️ 適した野菜
- にんじん(甘みがあり食いつき◎)
- キャベツ(食物繊維が豊富で消化しやすい)
- 大根(利尿作用があり、老廃物排出をサポート)
- かぼちゃ(βカロテンが豊富で免疫力UP)
- 白菜
- ズッキーニ
これらは比較的リンが低く、水分補給に向いています。
⚠️ 避けたい食材
- ほうれん草(シュウ酸・リンが高い)
- ブロッコリー(リンが高め)
- じゃがいも(カリウムが高い)
- 玉ねぎ・ネギ類(有害)
🥄 腎臓病向けの調理のコツ
- 野菜は細かく切ると旨みが出やすく、吸収がよくなる
- 煮汁も一緒に与えることで水分補給効果アップ
- 味付けは絶対にしない(塩分厳禁)
- 野菜の“煮すぎ”はミネラルが溶け出しやすいので程よく
🍲 スープ作りの基本ルール
- 味付けは一切不要(塩・だし・油NG)
- 野菜は細かく切り、茹でこぼしてカリウムを減らす
- スープは透明~薄い色程度を目安に

下処理を行うことで、腎臓にやさしい「低リン・低カリウムスープ」になるよ
手作りしてみたいけど、失敗が不安
愛犬の好みや体調に合わせて野菜の種類・硬さ・濃さを自由に変えられることも手作りご飯の強みです。
ですが、「腎臓病の子に手作りするのはハードルが高い」と感じるかもしれません。
実は“野菜スープだけ”なら、とてもシンプルで安全です。
必要なのは、腎臓に負担をかけない食材選びと、味付けをしないことです。
最初は少量から試し、愛犬の状態を見ながら調整時ていきましょう。
ここでは、失敗しないための3つのポイントをご紹介します。
まずは“スープだけ”から始める
初めての方は、食材を増やしすぎないことが大切です。
1〜2種類の野菜をやわらかく煮て、スープを与えてみましょう。
食いつきや便の状態を見ながら、少しずつ種類を増やすのが安全です。
濃すぎない”ことが鉄則
「濃いほど栄養がある」と思われがちですが、腎臓病の犬にとっては逆効果です。
薄めのスープこそが理想的です。
濃縮された出汁にはリン・カリウムが多く含まれるため、煮詰めずにサッと煮るのがポイントです。
定期的に獣医師へ報告する
「手作りスープを始めた」ときは、血液検査の結果を見ながら獣医師に伝えましょう。
愛犬のステージに合わせて、食材や量を調整する必要があります。
市販品(スープ等)を使っていいの?
「忙しくて手作りは難しい」「失敗が怖い」という飼い主さんも多いでしょう。
そんなときは、腎臓ケアに特化した市販スープを上手に活用するのもおすすめです。
市販スープのメリット
- 栄養バランスが調整されていて安心
- カリウムやリンが適切にコントロールされている
- 開封してすぐ使えるため衛生的・時短
- トッピングとして療法食と併用しやすい
特に「獣医師監修」や「腎臓サポート」などと明記されている製品は信頼性が高いです。
注意点
- “一般犬用スープ”は避ける(塩分・調味料が多い)
- 長期的に与える場合は、獣医師と相談する
- “スープだけで栄養を満たす”のは危険

野菜スープは“食欲サポート”や“水分補給”のための補助食品だよ。
主食の療法食を中心に、スープを「つなぎ役」として活用してね。
市販の犬用スープを活用する場合は、腎臓病向けの愛犬に適しているかをチェックしましょう。
市販品は手軽ですが、腎臓病の子向けとは限らないため、成分表示は必ず確認しましょう。
もし不安なら、「野菜だけの無添加スープ」を選ぶのがおすすめです。
そして、市販品と手作りを併用するのもひとつの方法です。
忙しい日は市販スープ、時間がある日は手作りにすることで、飼い主さんの負担も減り、続けやすくなります。
腎臓病の愛犬は、食欲や体調が日によって変わりやすいものです。
そんな時、無理なく水分と栄養をとれる野菜スープは、飼い主さんと愛犬の心強い味方になります。
まずはできる範囲から、優しいスープ習慣を始めてみてください。
腎臓病の犬に適した
「野菜スープ」の基礎知識

腎臓病の愛犬にとって、「食べること」は治療の一部です。
中でも野菜スープは、腎臓への負担を減らしながら水分を補給できる優れたサポート食。
しかし、作り方や使う食材を誤ると、逆に腎臓へ負担をかけてしまうリスクもあります。
本章では、「腎臓病の犬に本当に優しい野菜スープ」を作るための基礎知識をわかりやすく解説します。
腎臓病の愛犬への
スープの役割
臓病の犬に与えるスープで最も大切なのは、「腎臓を休ませる」ことです。
そのために意識すべきポイントは以下の4つです。
低リン
リンは老廃物として腎臓で処理されるため、摂りすぎると腎臓の負担になります。
野菜スープを作る際は、骨や内臓の出汁を避けることが基本です。鶏ガラやかつお出汁ではなく、「野菜のみ」で優しい旨味を引き出しましょう。
低ナトリウム
塩分(ナトリウム)が多いと、体内の水分バランスが崩れ腎臓が過労状態になります。
調味料は一切使用せず、素材の自然な甘みや香りで食欲を刺激するのが理想です。
適切な水分量
腎臓病の犬は脱水しやすいため、水分をしっかり補うことが重要です。
ただし一気に与えると吐き戻しの原因になるため、1日数回に分けて少量ずつ与えましょう。
食欲スイッチを入れる
腎臓病期は食欲低下が起きやすいですが、野菜の甘い香りや温かい湯気が食欲刺激につながることがあります。
特にキャベツ・大根・かぼちゃは犬が好む香りが出やすく、食欲のない時期に役立ちます。
腎臓に優しい野菜の選び方
腎臓病では リン・ナトリウム・カリウムの量の含有量によって注意が必要です。
以下に代表的な野菜の分類をまとめました。
⭕️ 積極的に使いたい食材

- にんじん:甘みがあり、スープの旨味ベースに最適
- キャベツ:ビタミンCや食物繊維が豊富。茹でて水にさらすとカリウムを減らせる
- 大根:消化がよく、カロリーも控えめ
- かぼちゃ(少量):食欲が落ちた犬の嗜好性アップに
⚠️ 注意が必要な食材(調整が必要)

- サツマイモ・ジャガイモ:カリウムが多いので、茹でこぼしを2〜3回行うことで減らす
- トマト:酸味やカリウム量が高いため、少量トッピング程度に
- ブロッコリー:栄養価は高いがリンも多いため、与えすぎ注意
❌ 使用を避けたい食材

- ほうれん草・小松菜:シュウ酸が多く、腎臓に負担をかける
- たまねぎ・ねぎ・にら:犬にとって有害(貧血を引き起こす可能性)
- きのこ類(特に生):消化に負担がかかるため避けましょう
腎臓に負担をかけない工夫
スープの風味づけには昆布・かつお節・鶏ガラなどを使いたくなりますが、腎臓病の犬には避けるべきです。
これらはリンやナトリウムが多く、せっかくの手作りスープが逆効果になることも。
おすすめは以下の方法です。
野菜そのもので旨味を引き出す
- にんじん・キャベツ・かぼちゃなどをじっくり煮込むと、自然な甘みと香りが出ます。
- どうしても香りを足したい場合は、ほんの少量のオリーブオイルを最後に垂らすだけでも食いつきが改善します。
加工食材や調味料はNG
- 「だしパック」「コンソメ」「味噌」「塩」などはすべて不要です。
- 水は軟水(ミネラル分が少ない)を使用すると腎臓に優しいです。
水分多めスープの効果と与え方
腎臓病の犬にとって、水分摂取は治療の一部です。
野菜スープを上手に取り入れることで、以下のような効果が期待できます。
野菜スープのメリット
- 脱水を防ぎ、老廃物の排出をサポートする
- 食欲が落ちた時の「食べやすい栄養補給源」になる
- 薬や療法食への“味のアクセント”として使える
与える量の目安
| 体重 | 1日の目安スープ量 |
|---|---|
| 3kg未満 | 100〜150ml程度 |
| 5〜10kg | 200〜300ml程度 |
| 10kg以上 | 300〜500ml程度 |
※上記は目安です。持病や食事内容により調整が必要なため、必ず獣医師に確認してください。
与え方のコツ
- 冷たいスープは避け、人肌程度(35〜40℃)に温めて与える
- 1回で飲ませず、3〜4回に分けて少しずつ与える
- 残りは冷蔵で保存し、翌日までに使い切る
犬の腎臓病のステージに
合わせたスープづくり

腎臓病と診断された犬にとって、「何を食べるか」はもちろん、「どの段階でどう食べるか」が極めて重要です。
犬の腎臓病は進行性の病気で、国際獣医腎臓学会(IRIS:International Renal Interest Society)の基準に基づき、症状や検査結果に応じてⅠ~Ⅳに分類されます。
ステージによって必要な食事や水分量が変わるため、愛犬に合ったスープ作りが大切です。
スープの内容を決める前には、必ず獣医師の診断や指示を確認しましょう。
本章では、腎臓病のステージ別・野菜スープ作りのポイントを紹介します。
“愛犬の今の状態に合ったスープづくりの参考にしてください。
ステージⅠ・Ⅱ:
進行を遅らせるためのスープ
腎臓病の初期(ステージⅠ〜Ⅱ)は、まだ体に大きな変化が見られず、進行を防ぐ食事が目的となります。
この段階で重要なのは、腎臓の負担を減らしながらも、栄養バランスと食欲維持を両立することです。
ポイント
- 低リン・低ナトリウムのベース
骨や魚の出汁は使わず、にんじん・キャベツ・大根などの淡色野菜で自然な甘みを引き出します。
香りづけにごく少量のオリーブオイルを使用すると嗜好性がアップします。 - 抗酸化野菜の活用
腎臓の酸化ストレスを軽減するため、ブロッコリースプラウトやキャベツなど、抗酸化作用のある“腎臓に負担の少ない野菜”を活用します。
ブロッコリーはリンを含むため、使用する場合は「茹でこぼし」を忘れないようにしましょう。 - 水分量をしっかり確保
腎臓病初期では、老廃物の排出を助けるための水分補給が特に有効です。
1日体重1kgあたり約50〜70mlの水分を目安に、野菜スープを少しずつ複数回に分けて与えましょう。

この時期は“治療食”よりも“腎臓を守る栄養設計”を意識しましょう。
食事制限ばかりでなく、愛犬が『食べることを楽しめる工夫』を続けることが大切です。
ステージⅢ・Ⅳの場合:
食欲低下・水分摂取困難な犬向けスープ
腎臓機能が大きく低下してくるステージⅢ〜Ⅳでは、「食べられない・飲めない」という新たな壁が生じます。
この段階では、栄養よりもまず「食欲と水分摂取を維持すること」が最優先です。
ポイント
- 香りを立たせる
嗅覚の刺激で食欲を促すため、ほんの少量のかぼちゃ・鶏胸肉のゆで汁(1:5希釈)を加えると嗜好性が向上します。
※塩・だし・調味料は一切使用しません。 - 温度は“体温よりやや高め”
35〜40℃程度のスープは香りが立ちやすく、飲み込みやすい温度。
冷たいスープは胃腸の動きを鈍らせるため避けましょう。 - 粘度を調整する
飲み込みが難しい愛犬には、スープに寒天やとろみ粉を少量加え、飲み込みやすくします。
反対に、飲み込みがしやすい愛犬にはサラサラタイプのままでもOK。 - 少量頻回が鉄則
1回に多く飲ませるのではなく、1日3〜5回、数口ずつを分けて与えます。
胃腸への負担を避けつつ、脱水を防ぎます。
併発症がある場合の
野菜スープ調整ポイント
腎臓病の犬は、心臓病・膵炎・高脂血症などを併発するケースが少なくありません。
その場合、通常の「腎臓ケア用スープ」では成分バランスが合わないことがあります。
心臓病併発時
- 塩分・ナトリウムはさらに制限(完全無塩)されます。
- 水分は多すぎると心臓に負担をかけるため、獣医師の指示量を厳守しましょう。
- 使用野菜はカリウム低め(キャベツ・大根中心)がおすすめです。
膵臓病併発時
- 油脂を使わず、完全ノンオイルスープにすましょう。
- 消化にやさしいにんじん・ズッキーニ・白菜を短時間煮込みで柔らかく仕上げましょう。
- 甘味の強いサツマイモは避けましょう。
高脂血症を伴う場合
- オイル類(オリーブオイル・MCTオイル)も避ける。
- 代わりに、水溶性食物繊維(ごく少量のキャベツやおから)で満足感をプラスしてみましょう。
“老犬・シニア犬”に特化した
野菜スープ
高齢犬では、腎臓病だけでなく関節炎や胃腸の弱りも同時に進行していることが多いです。
そこでおすすめなのが、「腎臓+シニア総合ケア」を意識したスープです。
消化・吸収を助ける工夫
- 細かく刻んだ野菜を長時間コトコト煮込むことで、繊維が分解され消化しやすくなる。
- ブレンダーでペースト状にしても◎。歯が弱い老犬にも優しいです。
関節ケアを意識した食材
- かぼちゃ・白菜・にんじんをベースに、少量の白ごまペーストを加えることで、関節に必要な脂質を少し補給できます。
- ただし、リン値を考慮して1食あたりティースプーン1/4程度が目安です。
水分補給のタイミング
- 散歩後や薬の前後に、温かいスープを少量与えると自然に水分が摂れます。
- 食後にスープを与えるよりも、「食前・間食時」に与える方が効果的です。
愛犬の腎臓に優しい
野菜スープ作り方

野菜スープは、あくまで療法食を補うサポートとしての位置付けで、無理に食べさせる必要はありません。
本章では、愛犬が「療法食を食べない」「食欲がない」そんなときに、少しでも水分を補給したり、食事に変化をつけてあげられるようなレシピをご紹介します。
野菜スープを与える際は、必ず獣医師に相談し、愛犬の病状や栄養管理に合った方法で調整してください。
準備するものと下処理野
まず野菜スープを安全に始めるためには、野菜の中にあるカリウム・リンを少しでも減らす下処理がカギになります。
腎臓病の犬ではこれらミネラルの排出が難しくなっているため、手作りスープでもこの工程を省かないことが重要です。
準備するもの

- にんじん、キャベツ、大根などを中心に用意(使いやすい野菜)
- 包丁・まな板・ナイロン袋またはボウル(水に浸すため)
- 鍋、ざる、キッチンペーパー
- 軟水または浄水(ミネラル少なめの水が望ましい)
- キッチンタイマー(茹で時間管理用)
下処理手順
- 野菜を適切な大きさ(例:にんじんは1〜2cm輪切り、キャベツは粗みじん)に切る。
- 切った野菜を 水に20〜30分ほど浸す。(これによりカリウムの一部が水に溶け出す傾向があります。)
- 浸した野菜をざるであげて、新しい軟水を鍋に入れて茹でる。茹で時間は野菜の種類によりますが、にんじんなら5〜7分、キャベツなら3〜5分程度。
- 茹で上がったら 茹で汁は捨て、野菜だけを使う。この茹でこぼし工程でミネラル除去効果があります。
- 茹でた野菜を軟らかくし、スープとして使いやすい形に整える。

浸水+茹でこぼしがポイントだよ!
レシピ1:(初期ケア向き)
低リン野菜スープ
腎臓病の早期(ステージⅠ〜Ⅱ)で、まだ食欲も比較的落ちておらず、療法食をなんとか続けられているという愛犬には、“基本構成”の野菜スープが有効です。
低リン・低ナトリウム・水分多めのレシピを紹介します。
材料(小型犬・体重約5kgを想定)
- にんじん:50g(茹でこぼし後)
- キャベツ:30g(茹でこぼし後)
- 大根:40g(茹でこぼし後)
- 軟水:300ml
- オリーブオイル:小さじ1/2(香りづけ、嗜好性サポート)
※塩・だし・調味料は一切使用しません。
作り方
- 前述の下処理(浸水・茹でこぼし)を済ませた野菜を鍋に入れて、軟水を加える。
- 中火〜弱火で5〜10分ほど煮込み、野菜が十分に柔らかくなったら火を止める。
- オリーブオイルを加えて軽く混ぜ、温度を人肌程度(35〜40℃)に冷ます。
- スープだけを器に入れ、療法食ドライフードにかけて与える(量は愛犬の体重・水分状況を見ながら調整)。
レシピ2:(後期・老犬向け)
落ち・水分補給重視タイプ
腎臓病が進行し、ステージⅢ〜Ⅳに入ると「食べたくない」「水を飲まない」「体重が減ってきた」といった悩みが増えます。
そんな場合は、“嗜好性・水分量・飲み込みやすさ”を重視した野菜スープに工夫が必要です。
材料(中型犬・体重約10kgを想定)
- にんじん:60g(茹でこぼし後)
- かぼちゃ:40g(茹でこぼし後・甘みと香り)
- キャベツ:30g(茹でこぼし後)
- 軟水:500ml
- チキンブロス代替として、鶏胸肉ゆで汁を5倍希釈(無塩):50ml
(※使用可否・量は必ず主治医に相談し、数値が不安定な場合は省く判断も必要です) - オリーブオイル:小さじ1
- 寒天またはペット用とろみ粉:少量(飲み込み補助用)
作り方
- 野菜を浸水・茹でこぼし処理。かぼちゃ含むためより丁寧に。
- 鶏胸肉を塩なしでゆで、そのゆで汁を5倍希釈して香りを足す。
- 鍋に軟水+野菜+希釈ゆで汁を入れて、弱火で5〜10分煮込む。
- 野菜が軟らかくなったら、寒天またはとろみ粉で少しとろみをつける(飲み込みにくい犬向け)。
- オリーブオイルを加え、35〜40℃程度に冷ましてから与える。
- 1回の量は少なめ(例:100ml程度)を、1日3〜5回に分けて与える。
レシピ3:(療法食+スープ活用)
トッピング&アレンジ編
毎日同じスープでは飽きてしまうことがあります。
そんな時のために、療法食と併用できるトッピング&アレンジスープを紹介します。
アレンジアイデア
- 温野菜+スープ掛け:
基本スープに刻んだ低リン野菜(例:ゆでカリフラワー少量)を混ぜ、食材の“楽しさ”を加える。 - 冷製スープチョイス:
暑い季節や食欲が落ちている時は、人肌程度ではなく少し冷やしたスープ(25〜30℃)にし、氷型トレーで「凍らせて舐めさせる」方法も。 - トッピングスープ:
療法食ドライフードにこのスープをかけ、その上に“香り効果”を狙った少量のパセリまたはパセリオイル(極少量)を垂らす。
(※パセリはカリウムを含むため、常用せず・体調や検査値を見ながら使用してください。) - 風味ローテーション:
週に1回、にんじん主体 → かぼちゃ主体 → キャベツ主体 という風に“味の変化”をつけることで、継続性を高める。
注意点
- どんなに少量でも、塩・コンソメ・味噌などの調味料は使用しない。
- アレンジとして肉・魚を加えたい場合は、タンパク質量とリン量を必ず獣医師に相談しましょう。
- アレンジの数を増やすことで管理が大変になるため、週1~2回アレンジ+他は定番スープというバランスがベストです。
保存・再加熱・与える際の注意点
手作り野菜スープを安心して使い続けるには、保存と再加熱のルールを守ることが不可欠です。
腎臓病の犬に特化した注意点も含めた実践方法をご紹介します。
保存方法
- スープを完全に冷ましてから、1回分ずつ小分けにする。
- 冷蔵保存なら24時間以内に使用。冷凍保存する場合は、1ヶ月以内(長くても3ヶ月以内)を目安にし、風味や品質の変化があれば使用を控えましょう。
- 解凍後は、再凍結せず、24時間以内に使い切る。
再加熱・温度管理
- 再加熱は、電子レンジではなく湯せんまたは鍋でゆっくり温め、35〜40℃程度(人肌〜少し温かめ)で与える。
- 高温(50℃以上)は犬の口・胃に負担をかける恐れがあります。
- 冷蔵庫から出した直後(5〜10℃)のまま与えるのも避けるべきです(胃腸の動きが鈍るため)。
与える量の目安
- 体重5kg未満:1回あたり50〜100mlを1日2〜3回
- 体重5〜10kg:1回あたり100〜200mlを1日2〜3回
- 体重10kg以上:1回あたり200〜300mlを1日2〜4回
※ここで示している量はあくまで「目安」です。
体重・腎臓病のステージ・併発症・その日の体調によって適量は変わるため、必ず少量から与え、主治医の指示や愛犬の様子を確認しながら調整してください。

主食(療法食)と併用し、スープは“補助的な水分・嗜好性アップ”として位置づけましょう。
実践後のチェックポイント

スープを与え始めてから
“見てほしいサイン”
野菜スープを取り入れた後、まず確認してほしいのは“目に見える体調の変化”です。
水分を多く含むスープは一見体に優しそうですが、腎臓病のステージや体質によっては注意が必要な場合もあります。
排尿量の変化
排尿量が増えすぎていないか?減っていないか? を観察しましょう。
スープを与えると水分摂取量が増えるため、排尿量も一時的に増えるのは自然な反応です。
数日たっても極端に増減する場合(例:以前の1.5倍以上の尿量・極端な減少)は腎臓機能のバランスが崩れている可能性があります。
飲水量の変化
スープを始めたら、水皿から飲む水の量が減ることがあります。
これはスープで水分を摂取できている証拠なので、問題ありません。
ただし、スープをやめたあとも水を飲まなくなった場合は、味覚変化や口内トラブルの可能性があります。
体重の変化
腎臓病では、体重の減少が最も見逃されやすいサインです。
スープで満足してご飯を食べる量が減ると、栄養不足で体重が落ちることがあります。
週に1回は体重を測り、100g単位の変動にも注目してください。
→ 目安:体重の5%以上減少したら要注意。
お腹に負担が出ていないか
スープは脂肪・たんぱく質を控えたレシピであれば消化にやさしいですが、体質によっては軟便・下痢が出ることがあります。
初めは少量からスタートし、排便の状態をチェックしましょう。
食欲に変化があるか
少量でもスープから香りや温かさを感じることで、食欲が戻る場合がます。
療法食に少量かけたとき、食べ始めがスムーズになることもあります。
元気に過ごせているか
腎臓病の犬は慢性的にだるさを感じています。
スープで少し水分やエネルギーが補われることで、散歩の歩きが軽くなる、表情が明るくなるなどの変化が見られることがあります。
血液検査の数値
獣医師の定期検査では、数値が改善しているか、維持できているかを確認します。
- BUN(尿素窒素)・Cre(クレアチニン)が上昇していないか
- リン(P)・カリウム(K)が急上昇していないか
スープの中身が適切であれば、数値が安定することが多いですが、自己判断でレシピを変えると悪化のリスクもあるため注意が必要です。
スープを中止・
獣医師へ相談が必要な状況
腎臓病の犬にとって、野菜スープは“補助ケア”の一部です。
体調に異変が出た場合は、早めに「スープを一時中止し、獣医師に相談する」ことが大切です。
食欲がさらに低下した・全く飲まない
香りや味でも反応がない場合、体調悪化の可能性があります。
無理に食べさせる必要はありません。
匂いを嗅ぐだけで嫌がる場合は嗜好性の問題ではなく、体調そのものが悪いサインであることが多いため、無理強いは禁物です。
嘔吐・下痢・腹部の張りが出た
腎臓病では胃腸の調子が乱れやすい状態です。
症状が一度でも見られたら、スープは中止しましょう。
明らかな脱水が続く
飲水量が増えない・目が落ちくぼむ・皮膚をつまんでも戻りにくいなどの症状は要注意です。
尿量の急な変化(極端に少ない/多すぎる)
腎機能の悪化や尿路トラブルの可能性があります。
すぐに受診してください。
これらの症状が出たとき、「スープが悪い」と決めつけるのではなく、原因を正確に把握することが重要です。

獣医師さんには、次の内容を伝えましょう。
- 与えたスープの内容(材料・量・回数)
- 発症したタイミング
- 他の食事やおやつとの併用状況
獣医師との連携
腎臓病ケアは、食事・水分・薬の“3本柱”で成り立ちます。
野菜スープはあくまで「食事をサポートする水分補給・嗜好性アップの手段」であり、獣医師・動物栄養士との連携が成功の鍵です。
与える前に必ず相談を
腎臓病にはステージがあり、必要な栄養管理が変わります。
安全な野菜や調理法でも、進行段階によっては避けた方がよい場合もあります。
与える前に必ず主治医へ相談しましょう。
スープの内容・量を共有する
使った食材、塩分・たんぱく質量、与えた量を伝えることで、獣医師はより正確に愛犬の状態を把握できます。
定期検査と併用して活用する
血液検査・尿検査の結果と照らし合わせながらスープの調整ができます。
数値が不安定な時期は、与えるタイミングや内容を変える必要があります。
「スープを飲んでくれたから安心」ではなく、「愛犬に合っているかを一緒に確認していく」と考えると、より安全に活用できます。

腎臓病の犬は病期ごとに適した栄養バランスが異なるため、“レシピの固定”ではなく“調整の継続”が必要です。
よくあるQ&A

本章では、
「それって本当にいいの?」
「他の食材はどうすれば?」
「毎日与えても大丈夫?」
こうした疑問に対して、専門的な視点を加えながら丁寧に答えていきます。
市販スープと手作りスープ、
どちらが良いの?
結論から言うと、腎臓病の犬には基本的に「市販の腎臓ケア用スープや療法食スープ」が安心な選択肢です。
理由は次の通りです。
- 市販製品は、リン・カリウム・ナトリウムなどのミネラル含有量が製造段階で管理されている。
- 獣医師監修で、腎臓病のケアに必要な栄養バランスが調整されているケースが多い。
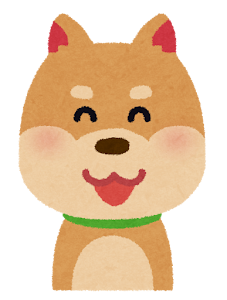
でも、手作りスープにも大きなメリットがあります。
- 犬の嗜好性を引き出しやすい:香りや食感を自分で調整できる
- 素材を透明に把握できる:添加物・塩分・調味料を省ける
- 療法食と併用しながら“愛情表現”として活用できる

ただし、手作りには次のようなリスクもあります。
- 野菜・出汁・調理法によってはリン・カリウム・ナトリウムの管理が難しい。
- 量・頻度・保存・衛生管理を誤ると、かえって腎臓に負担をかけてしまう。
おすすめの使い分けは以下の通りです。
おすすめの使い分け
- 療法食+市販スープ:
まずは安定運用を優先したいとき - 療法食+手作りスープ:
嗜好にムラがある、犬の好みに合わせて調整したいとき
いずれにしても、獣医師や動物栄養士との相談が前提となる点は共通です。
野菜だけで栄養が足りるの?
「野菜スープ」と聞くと「たんぱく質は足りてるの?」という疑問が出るのは当然です。
腎臓病の犬にとっては、たんぱく質の量と質のコントロールが食事管理の大きなカギとなります。
まず理解しておきたいのは、
- 野菜スープは「水分補給+嗜好性+低ミネラル補助」としての位置づけであり、主食(つまりタンパク質・エネルギー源)としては基本的には設計されていません。
- 腎臓病用の療法食は、たんぱく質・リン・カリウム・ナトリウムが計算された量で配合されています。
たんぱく質をどのように確保すればよいか、ポイントを以下にまとめます。
タンパク質確保のポイント
- 療法食のたんぱく質量を確認:腎臓病向けのフードでは「制限たんぱく」または「質の良いたんぱく質を少量」が基本です。
- 手作りスープを併用する場合、主食のたんぱく質量を減らさずに済むように設計するか、獣医師に“スープを使った食事”を相談しましょう。
- 野菜スープだけに頼ると、たんぱく質不足・筋肉量低下・免疫低下につながる可能性があります。
- 食欲が落ちている段階では、「少量でも食いつきが良いスープ+少量の良質たんぱく質(茹でた鶏胸肉/ささみ等、無塩)」という形で併用する方法もありますが、茹で汁や出汁にリン・カリウムが溶け出しているため慎重にしましょう。
つまり、野菜スープを取り入れても「たんぱく質の確保」「主食とのバランス」は必ず意識しましょう。
野菜スープばかり与えていいの?
多くの飼い主さんは、
「スープだけ与えていいの?」
「毎食与えても大丈夫?」
という疑問を持っているのではないでしょうか。
答えは「いいえ、スープばかり・毎食というのは避けるべき」です。
理由は以下の通りでう。
- たんぱく質・脂質・炭水化物・ビタミン・ミネラルなど、栄養バランスを考えると、野菜スープだけでは設計しきれない部分が多い。
- 特に腎臓病の犬では、たんぱく質・リン・カリウム・ナトリウムの管理が厳格になるため、スープばかりという与え方は栄養不足・偏りリスクがあります。
- また、スープの水分量が多すぎると、満腹感・水分過多によるむくみ・胃腸の負担に繋がる可能性もあります。
理想的な活用法としては、
野菜スープの活用法
- 主食=腎臓病用療法食または獣医師監修手作り食 → 1回/日または2回
- 補助食として野菜スープ:1日1〜2回、少量ずつ与える
- 食欲低下時・飲水量が少ないと感じる時にスープの割合を少し増やす(但し獣医師と相談の上)
スープを与えても変化がないとき、
どうすればいいの?
「野菜スープを試したけど、愛犬の食いつきが変わらない」
「尿量・水分量・体重に変化がない」
という声もしばしばあります。
そんなとき、次のステップを検討してください。
スープの内容を見直す
- 食材:
野菜の種類が愛犬の嗜好と合っていない可能性。香り・色・食感を工夫する。 - 温度・テクスチャ:
冷たすぎたり、味が薄すぎたりすると反応が鈍くなります。
35〜40℃くらいの温かさ、少しとろみをつける工夫をしてみましょう。 - 水分量:
スープを与えていても水を飲まない、排尿量に変化がない場合、スープの量・回数の調整が必要です。
療法食・他のケアとのバランスを確認
- 療法食がしっかり食べられていないと、スープだけのサポートでは栄養が伴いません。
- 他の併発症(心臓病・膵臓病など)が影響していないか確認。病状が変わるとスープの効果も変わります。
獣医師に相談するタイミング
- 数週間続けて変化が見られない、または尿量・飲水量・体重・血液検査数値に異変がある。
- 食欲が明らかに落ちている、嘔吐・下痢・血尿が出た。
このような場合は、スープの設計そのものを見直す必要があります。
獣医師・栄養士に「スープを試したけれど反応が出ない」というデータ(使用量・回数・食材)を整理して伝えると改善に繋がりやすいです。
まとめ:
腎臓病の犬|
野菜スープのポイント

腎臓病の愛犬に野菜スープを取り入れる際は、「補助的な水分・嗜好性アップ」としての位置付けを理解することが大切です。
さいごに、本記事のポイントを分かりやすく整理します。
- 野菜スープは「補助ケア」として活用する
- 主食(療法食・手作り食)の代わりにはならない
- 水分補給や食欲サポートが主な目的
- 無理に与えず、愛犬の様子を最優先にする
- 市販スープと手作りスープを使い分ける
- 市販スープ:リン・カリウム・ナトリウム管理がされており安心
- 手作りスープ:嗜好性や素材調整ができるが、栄養管理には注意が必要
- 野菜選び・調理法に腎臓への配慮を
- 低リン・低カリウム・低ナトリウムの野菜を選ぶ
- 浸水・茹でこぼしでミネラル量を調整する
- 塩・だし・調味料は使用しない
- 与える量と頻度は「主食優先」で考える
- スープだけを大量に与えない
- 食欲低下時・水分不足時に補助的に使う
- 体調や飲水量を見ながら調整する
- 体調変化を観察し、早めに対応する
- 排尿量・飲水量・体重の変化をチェック
- 嘔吐・下痢・血尿・むくみがあれば一時中止
- 異変を感じたら早めに獣医師へ相談
- ステージ別・老犬への配慮を忘れない
- 初期ステージ:進行を遅らせる視点で活用
- 後期ステージ・老犬:嗜好性・水分・消化負担を重視
- 併発症がある場合は個別対応が必要
- 獣医師・専門家との連携を大切にする
- レシピ内容・量・回数・体調変化を記録する
- 定期的な血液検査結果をもとに相談する
- 自己判断せず、専門家の助言を受けながら調整する
野菜スープは、腎臓病の犬にとって「食事の楽しみを増やす」「水分補給を助ける」心強いサポートになります。
正しい知識と無理のない工夫を重ねることで、愛犬の生活の質を守りながら、安心して食事ケアを続けることができます。
愛犬にとっての「美味しい時間」「穏やかな時間」が、少しでも増えますように。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

📚<参考文献>
- Akita, K., & Yamamoto, T. (2020). 犬の慢性腎臓病と食事管理. 日本小動物獣医師会誌, 71(4), 210-218.
- 小動物臨床栄養学研究会(2019)『犬と猫の栄養管理ガイド:慢性腎臓病に対する栄養アプローチ』ペット栄養学会出版.
- 日本小動物獣医師会(2020)「慢性腎臓病の犬における栄養管理と食事戦略」『日本小動物獣医師会誌』73(2).
- Purina Institute. (n.d.). 犬の慢性腎病(CKD):治療のための栄養学 — CKD犬の栄養管理に関するガイドライン.
- ヒルズペット. 犬の腎臓病と食事管理の重要性 — たんぱく質・リン・ナトリウムの制限など、腎臓病の犬の食事療法ポイント。
- 柳都 こもれび動物病院. 愛犬、愛猫が慢性腎臓病になった時に確認しておきたい治療ガイドライン — ステージ別管理と注意点の解説。
- Purina Institute. 犬の慢性腎病(CKD):治療のための栄養学 — CKD犬の栄養管理に関するガイドライン。
- Brown, S. et al. (2015). "Guidelines for the management of chronic kidney disease in dogs." Journal of Veterinary Internal Medicine.
- Freeman, L. M. (2012). "Nutrition strategies for dogs with chronic kidney disease." Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice.
- International Renal Interest Society (IRIS). “IRIS Staging of CKD.” IRIS Kidney, 2024.
- Merck Veterinary Manual. “Chronic Kidney Disease in Dogs.” Merck Veterinary Manual, 2024.
- Polzin, D. J. (2013). "Evidence-based dietary management of chronic kidney disease in dogs." Journal of Small Animal Practice.
※本記事は上記の獣医腎臓病ガイドラインおよび臨床データを基に、一般飼い主向けに要点を再構成しています。調理法や分量は文献の栄養学的原則を踏まえて、日常で実践しやすい形にまとめた内容です。