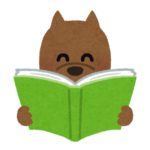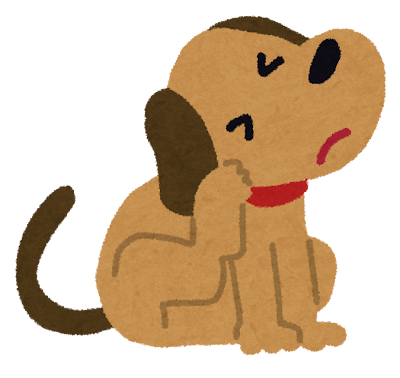
愛犬のかゆみや赤み、フケに悩んでいませんか?
「薬を使ってもなかなか改善しない」「市販フードだけでは満足できない」と感じる飼い主は少なくありません。
実は、犬のアトピー改善には食事の工夫が大きな鍵を握っていることをご存知ですか。
手作り食は「愛犬の体質に合わせて栄養を最適化できる」ため、かゆみや炎症の改善効果が期待できます。
しかし、何も考えずに始めると栄養不足や逆効果のリスクもあります。
本記事は、安全で効果的な手作り食のポイント、すぐに使えるチェックリストやササプリメントの活用法についての情報をまとめました。
愛犬のアトピーに悩む飼い主さんに、ぜひ読んでいただきたい内容です。
目次
犬のアトピーとは?
食事改善でできること

「フードを変えても、手作りにしても、なかなか良くならない」
「薬に頼り続けるしかないの?」
愛犬のアトピーに悩む飼い主さんの多くが、こうした不安を抱えています。
そして、今より少しでも症状を和らげ、愛犬の生活の質を上げたいという切実な思いがあります。
結論から言うと、犬のアトピーは食事だけで完治する病気ではありません。
しかし、食事の見直しによって症状の出方を穏やかにし、悪化の頻度を下げることは十分に可能です。
特に手作り食は、体質や症状に合わせた微調整ができる点で、大きな意味を持ちます。
犬アトピーの症状と原因
犬のアトピー性皮膚炎は、かゆみを伴う慢性的な皮膚の炎症が特徴の病気です。
皮膚のバリア機能が低下するため、二次感染を起こしやすい点も注意が必要です。
よくある症状と主な原因について、以下にまとめました。
よく見られる症状
- 顔・耳・脇・内股・足先をしきりになめる、噛む
- 耳の赤み、外耳炎を繰り返す
- 皮膚の赤み、湿疹、脱毛
- 季節によって症状が強くなる
これらの症状が長期間続く場合、アトピー体質が疑われます。
主な原因
- 環境アレルゲン(ハウスダスト、花粉、カビ、ダニなど)
- 皮膚バリア機能の低下(遺伝的要因が大きい)
- 免疫バランスの乱れ
- 食事内容が間接的に影響するケース
重要なのは、食事そのものがアトピーの直接原因とは限らないという点です。
ただし、体の内側の状態が悪いと、皮膚症状として表面化しやすくなります。
食事がアトピーに影響する理由
「アトピーは皮膚の病気なのに、なぜ食事?」と疑問に思う飼い主さんも多いでしょう。
実は、皮膚の健康は腸内環境・免疫・栄養状態と密接につながっています。
腸と皮膚はつながっている
犬の免疫細胞の多くは腸に存在しています。
消化に合わない食事や、添加物が多い食事が続くと腸内環境が乱れ、免疫の過剰反応が起こりやすくなります。
その結果、アトピー症状が強く出ることがあります。
市販フードでは調整しにくいポイント
- 特定のたんぱく質が体質に合わない
- 脂質バランスが症状に合っていない
- 原材料が多く、原因を特定しづらい
手作り食であれば、使う食材を最小限にし、反応を見ながら調整できるため、アトピー体質の犬にとって大きなメリットがあります。
食事改善の本当の目的
アトピーの食事管理は「かゆみをゼロにする」ことではなく、症状が出にくい体内環境を整えることが目的です。
この視点を持つことで、手作り食との向き合い方が現実的になります。

手作り食では、栄養バランスを整えつつアレルギーの原因を避けることが可能だよ❣️
手作り食で改善できる症状と
できない症状の違い
手作り食は、アレルギー原因の除去や栄養バランス調整が自由にできるため、食事がアレルギー要因になっている場合は、かゆみの軽減、皮膚の赤みや炎症の緩和、被毛のツヤ改善などの効果が期待できます。
ただし、すべての症状が手作り食で改善するわけではありません。
手作り食ので改善が期待できる症状、期待できない症状を以下にまとめました。
手作り食で改善が期待できること
- かゆみの頻度や強さが軽減する
- 皮膚の赤みやベタつきが落ち着く
- 便の状態が安定し、体調全体が良くなる
- 薬の使用量を減らせるケースがある
これは、体の内側の炎症や免疫バランスが整うことで起こります。
手作り食だけでは改善が難しいこと
- 環境アレルゲンが主因の強いアトピー
- すでに慢性化・重症化している皮膚病変
- 細菌や真菌感染を伴う皮膚炎
この場合、食事は治療の補助的な役割になります。
「手作りにしたのに治らない」と感じる多くのケースは、期待値が高すぎたことが原因かもしれません。
手作り食で失敗しやすい落とし穴
- 良かれと思って食材を増やしすぎる
- アトピーに良いと聞いた食材を過剰に使う
- 栄養バランスが崩れ、別の不調を招く

手作り食は「特別な食事」ではなく、体質に合わせて引き算する食事という考え方が重要です。
自己判断で栄養バランスを崩した手作り食は、免疫力低下や皮膚状態の悪化を招くリスクがあるます。
獣医師監修のもとで栄養バランスを整えることが重要です。
手作り食が犬のアトピーに
効果的な理由
アレルゲン除去と
栄養バランスの重要性
犬のアトピー性皮膚炎に悩む飼い主さんは、「どのフードを選んでも愛犬のかゆみが改善しない」「アレルギーの原因がわからない」と不安を抱えているのではないでしょうか。
手作り食は、こうした悩みに直接応える手段のひとつです。
なぜなら、愛犬に合わせてアレルギー原因食材を避けながら、必要な栄養素を調整できるからです。
例えば、牛肉や小麦にアレルギー反応を示す犬には、それらを除いた鶏肉やサーモン、白米やさつまいもを主食に組み合わせることが可能です。
皮膚や被毛の健康に必要なオメガ3脂肪酸やビタミン、ミネラルを加えることで、炎症を抑えつつ免疫バランスを整えることができます。
このように、アレルゲン除去と栄養補給を同時に行える点が、手作り食の最大の強みです。
市販フードとの違い
市販フードは栄養バランスが一定で管理されている反面、添加物や保存料が含まれることが多く、アレルギー症状を悪化させるケースがあります。
ドッグフードは一般的に「一律の栄養設計」であるため、犬個々の体質やアレルギーに細かく対応することは難しいのが現状です。
手作り食は愛犬の体調や好みに合わせて食材や量を調整できるため、アトピーに関連する食材の除去や必要栄養素の補充が柔軟に行えます。
手作り食は犬の消化吸収を考慮して食材を選べるため、腸内環境を整える効果も期待できます。
腸内環境の改善は、免疫バランスを整え皮膚炎の軽減につながることが知られており、これが市販フードとの差別化ポイントです。
科学的根拠から見る手作り食の
メリット・デメリット
オメガ3脂肪酸や抗酸化物質を豊富に含む食材は、炎症性サイトカインの分泌を抑え、皮膚の赤みやかゆみを軽減する効果が期待できることをご存知の飼い主さんも多いでしょう。
一方で、手作り食にはデメリットもあります。
栄養バランスが崩れると、免疫力低下や皮膚状態の悪化を招く可能性があります。
時間や手間がかかるため、忙しい飼い主には続けにくいという課題もあります。
重要なのは、獣医師や栄養士のアドバイスを受けながら、犬の体質や症状に合わせて調整することです。
愛犬のアトピー改善において手作り食は、アレルゲンの除去と栄養バランスを両立できる唯一無二のアプローチです。
飼い主さんが愛犬に合った食事を見つけることで、かゆみや炎症を効果的に軽減し、日々の生活の質を向上させることが可能になります。
犬アトピー向け手作り食の
具体レシピとポイント
アレルギー対策食材の選び方
犬のアトピー改善に向けて手作り食を始める場合、まずはアレルギー対策食材の選び方が重要です。
一般的に犬がアレルギーを起こしやすい食材には、牛肉、豚肉、小麦、乳製品、鶏卵などがあります。これらの食材を避けるだけで、多くの犬でかゆみや皮膚炎の症状が軽減されるケースがあります。
皮膚や被毛の健康に必要な栄養素は十分に補う必要があります。例えば、オメガ3脂肪酸を含むサーモンや白身魚、抗酸化作用のあるブロッコリーやカボチャなどは、アトピーの症状緩和に有効です。
単に「アレルギー食材を避ける」だけでなく、必要な栄養をバランスよく摂取できる組み合わせを意識することが大切です。
おすすめの主食・
副食の組み合わせ
手作り食の基本は、主食と副食のバランスです。
主食には消化が良くアレルギーリスクの低いサツマイモや白米、カボチャなどを選びます。
副食にはたんぱく質源として鶏胸肉やサーモン、野菜や海藻類を加えます。
たとえば、サツマイモを主食にして、鶏胸肉とブロッコリー、少量のオリーブオイルを副食として加えると、皮膚炎を抑えつつ栄養バランスの取れた食事になります。
手作り食は愛犬の体質や症状に合わせて量や食材を微調整できる点が、市販フードにはない大きなメリットです。
簡単に作れる手作り食レシピ3選
- 鶏胸肉とさつまいもプレート
鶏胸肉を茹でてほぐし、サツマイモを蒸して混ぜるだけ。
仕上げに少量のオリーブオイルを加えることで皮膚の炎症を抑える効果があります。 - サーモンとブロッコリーの和風ボウル
サーモンを蒸してほぐし、茹でたブロッコリーとカボチャを混ぜる。
抗酸化作用のある食材を多く含むため、かゆみや赤みの緩和に役立ちます。 - チキンと玄米のバランス食
鶏胸肉と玄米を柔らかく煮込み、細かく刻んだ人参やキャベツを混ぜる。
消化吸収が良く、長期的に続けやすいレシピです。
保存方法・与える量の目安
作った手作り食は、冷蔵で2~3日、冷凍で1か月程度を目安にしましょう。
与える量は犬の体重や活動量によって異なりますが、基本的には体重1kgあたり約40~50gを目安に調整します。
初めて手作り食を取り入れる場合は、少量から始め、体調や皮膚の状態を観察しながら量を調整することが大切です。
手作り食でよくある
失敗と回避法
栄養バランスが偏る
犬のアトピー改善を目的に手作り食を始める飼い主の中には、栄養バランスを十分に考慮せずに食材を選んでしまい、結果的に愛犬の体調を悪化させてしまうことがあります。
たとえば、たんぱく質ばかりに偏った食事や、野菜や炭水化物が極端に少ない食事は、消化不良や免疫低下、皮膚の乾燥などを招く可能性があります。
回避する方法としては、主食・副食・脂質・サプリのバランスを意識することが重要です。
具体的には、消化が良くアレルギーリスクの低い主食(サツマイモ、白米)、皮膚や被毛に必要なたんぱく質(鶏胸肉、サーモン)、オメガ3脂肪酸を含む油脂(オリーブオイル、亜麻仁油)を組み合わせることで、偏りを防ぐことができます。
食材の選び方で失敗するケース
手作り食での失敗で多いのが、アレルギー食材の選択ミスです。犬によってアレルギーの原因は異なるため、「犬に良い」とされる一般的な食材でも、特定の犬にとっては症状を悪化させる場合があります。
例えば、牛肉や乳製品、小麦などは犬アトピーで避けた方が良い食材の代表です。
回避策としては、食材を一度に多く取り入れず、少量から様子を見ながら増やしていくことが大切です。
新しい食材を試す際は必ず1種類ずつ行い、皮膚の赤みやかゆみの変化をチェックしましょう。
必要に応じて、獣医師や犬の栄養専門家に相談することで、安全かつ効果的に手作り食を進められます。
アトピー悪化のサインと
すぐできる対策
手作り食を導入しても、場合によってはアトピー症状が悪化することがあります。
赤みの悪化、かゆみの強まり、フケや脱毛の増加などがサインです。
こうした場合は、原因を特定することが重要です。
すぐにできる対策としては、食事内容を振り返り、最近導入した食材や量の変更を一時的に中止することです。
オメガ3脂肪酸や抗炎症作用のある食材(サーモン、ブロッコリー、カボチャ)を積極的に取り入れ、腸内環境を整える食材を増やすことも有効です。
症状が改善しない場合は、早めに獣医師に相談し、薬やサプリとの併用も検討しましょう。
犬のアトピー改善に手作り食を取り入れる場合、栄養バランスの偏りや食材選びの失敗に注意しつつ、症状のサインを見逃さないことが成功のポイントです。
段階的に導入することで、愛犬の体調に合わせた安全で効果的な手作り食生活を実現できます。
手作り食と
薬の併用のポイント
投薬中でも安全に取り入れる方法
犬のアトピー治療では、抗ヒスタミン薬やステロイド、免疫調整薬などの投薬が行われることがあります。
「手作り食に変えたら薬の効果に影響しないか」と不安になる飼い主も少なくないでしょう。
基本的に、手作り食は市販フードと同じく投薬と併用可能ですが、注意すべき点があります。
薬の吸収に影響する成分が入っていないか確認することです。
例えば、脂質の多い食事はステロイドの吸収を変化させる場合があります。
カルシウムや鉄分を多く含む食材は、一部の薬の吸収に影響することがあります。

獣医師さんと相談しながら、薬を与えるタイミングや食材の組み合わせを調整することが、安全に手作り食を取り入れるポイントだよ。
フード切替のタイミングと注意点
手作り食に切り替える際は、急に全てを置き換えるのではなく、段階的に行うことが重要です。
まず1日1食だけ手作り食に置き換え、残りはこれまでのフードを継続する方法がおすすめです。
この方法により、アトピー症状や消化不良のリスクを最小限に抑えつつ、愛犬の体調を観察できます。
薬を服用している場合は、薬の投与タイミングと食事のタイミングを分けることで、薬の吸収や効果を妨げないようにします。
具体的には、薬の投与前後1~2時間は脂質やサプリの摂取を避けると安心です。
切替期間中は、便の状態、皮膚の赤み、かゆみなどを細かく記録しておくこともおすすめです。
定期検診で確認すべきこと
手作り食と薬の併用を行う場合、定期的な獣医師の診察は欠かせません。
注目すべきポイントは、皮膚の炎症状態、体重変化、血液検査の結果です。
特に栄養バランスが偏ると、血液検査でタンパク質やミネラル不足が現れる場合があります。
薬の量や種類が適切か、手作り食の導入によって症状が安定しているかを確認することも重要です。
飼い主さんが気づかない小さな変化も、定期検診で獣医師に相談することで早期に対処できます。

犬のアトピーの手作りごはんと薬を併用する時は、食材選び・薬の投与タイミング・定期検診の3点を抑えることが成功のだよ!
手作り食のお役立ち情報
手作り食でアトピーが改善した期間の目安
手作り食でアトピー症状が改善する期間には個体差がありますが、一般的には2週間~3か月程度で変化が現れることが多いと言われています。
短期間で改善が見られる犬もいれば、体質や症状の重さによっては半年ほどかかるケースもあります。
ここで大切なのは、改善が見られる前に焦って食材や量を頻繁に変えないことです。
症状が安定するまでは、同じレシピ・食材で継続的に観察することが、正しい評価と効果的な改善につながります。
日々のかゆみの程度、皮膚の赤みや被毛の状態を記録することで、改善の目安を判断しやすくなります。
実際に使えるサプリや
栄養補助食品の選び方
手作り食だけでは不足しやすい栄養素を補うために、サプリや栄養補助食品の活用もおすすめです。
特に犬のアトピー改善に効果的とされる成分には、以下のようなものがあります。
- オメガ3脂肪酸(魚油、亜麻仁油):炎症を抑え、皮膚の赤みやかゆみを軽減
- ビタミンE:抗酸化作用で皮膚の健康維持
- プロバイオティクス(乳酸菌):腸内環境を整え、免疫バランスを改善
- ビタミンB群、ミネラル:皮膚や被毛の再生サポート
サプリ選びのポイントは、添加物や保存料が少なく、犬用に設計されているものを選ぶことです。
投薬中の場合は獣医師に相談し、薬の吸収や効果に影響がないか確認することも忘れないようにしましょう。

「手作り食+サプリを段階的に導入して反応を確認する」ことがポイントだよ。
最初に手作り食だけを取り入れ、症状が安定してからサプリを追加することで、効果の原因を明確に判断でき、愛犬に最適な栄養補給を調整できます。
今日からできる手作り食チェックリスト
犬のアトピー改善に向けて、手作り食を始める際は「今日からできるチェックリスト」を作ることで、すぐに行動に移せます。
ポイントはシンプルで、段階的に進められることです。
今日からできるチェックリスト
- 食材の確認:アレルギーの原因となる牛肉、小麦、乳製品、鶏卵を避ける
- 主食・副食の準備:消化の良い主食(さつまいも、白米)とタンパク質(鶏胸肉、白身魚)を用意する
- 栄養補助の計画:オメガ3脂肪酸、ビタミンE、プロバイオティクスを補う
- 段階的導入:まず1日1食を手作り食に置き換え、残りはこれまでのフードを継続する
- 観察と記録:かゆみ、皮膚の赤み、便の状態を毎日チェックする
このチェックリストに沿って手作り食を導入することで、犬の体調変化に気付きやすく、失敗を防ぎながら改善を目指せます。
食材選びや量の調整も段階的に行えるため、愛犬の個体差に柔軟に対応できます。
獣医師監修の手作り食
手作り食に自信がない、栄養バランスが不安という方には、獣医師監修の手作り食を試す方法もあります。
オンライン相談で愛犬に合った食材とレシピを提案してくれるサービスもあります。
「ココグルメ」のお試しセットを活用
獣医師監修の手作りドッグフード「ココグルメ」では、アレルギー対応の食事プランを提供しています。
アレルゲンを避けた食材を使用した食事が含まれており、愛犬のアトピー改善に役立つ可能性があります。
今なら送料無料で980円のお試しセットが利用可能です。(記事掲載時点)
詳細や申し込みは公式サイトをご確認ください。 (獣医師監修の手作りドッグフード〖公式〗ココグルメ)
「シュクナミ動物病院」の獣医師監修レシピを参考にする
「シュクナミ動物病院」では、皮膚炎や外耳炎などの症状改善を目的とした獣医師監修の手作り食プランを紹介しています。
これらのレシピは、食事からの原因を取り除くことで症状の改善を目指す内容となっています。
具体的なレシピや注意点については、公式サイトをご参照ください。 (shukunami-vet.jp)
DC one dish で愛犬にあったレシピを作成してもらう
「DC one dish」では、愛犬の状態に合わせたレシピ作成を注文できます。音声相談(有料)もできますので、手作り食の第一歩として試してみるのも一つです。
詳細は、公式サイトをご参照ください。(DC one dishu)
書籍を参考にする
愛犬の手作り食の本を参考にするのも安心材料の一つです。
私が手作り食を始めた時に参考にした書籍について、こちらの記事で紹介しています。
手作り食に不安がある飼い主さんも多いでしょう。
私もそうでした。
まずは、獣医師さんに相談することをおすすめします。
かかりつけの獣医師さんが手作り食に詳しい方でなければ、オンラインで相談可能な獣医師さんに相談してみてはいかがでしょうか。
まとめ
犬のアトピー改善に向けた手作り食は、ただ「手作りすれば良い」というわけではなく、愛犬の体質や症状に合わせた工夫が不可欠です。
ここまで解説した内容を踏まえ、重要なポイントを以下にまとめました。
- アレルギー原因食材を避ける:牛肉、小麦、乳製品、鶏卵など、犬によってアレルギー反応を起こす食材は避ける。
- 栄養バランスを意識する:主食(サツマイモ、白米)、タンパク質(鶏胸肉、白身魚)、脂質(オメガ3脂肪酸)を組み合わせ、皮膚や被毛の健康をサポートする。
- 段階的に食事を切り替える:最初は1日1食のみ手作り食に置き換え、徐々に割合を増やすことで、消化不良やアレルギー反応のリスクを軽減する。
- 症状の観察と記録:かゆみ、赤み、フケ、便の状態などを毎日チェックし、改善のスピードや食材の影響を把握する。
- サプリや栄養補助食品の活用:オメガ3脂肪酸、ビタミンE、プロバイオティクスなどで栄養を補い、手作り食だけでは不足しやすい成分を補完する。
- 投薬中でも安全に取り入れる:薬の吸収や効果に影響しないタイミングで与え、獣医師と相談しながら併用することが重要。
- 獣医師監修プランを活用:愛犬に合わせた食事レシピや栄養バランスを確認できるプランを活用すると、安全かつ効率的に改善可能。
- 改善期間は個体差あり:症状の軽い犬では2~3週間、慢性的な症状がある場合は3か月以上かかることもあり、焦らず継続することが大切。
- 段階的な導入と組み合わせが効果的:チェックリストで少量試し、反応を確認してから獣医師監修プランやサプリを追加すると、失敗リスクを抑えつつ改善が可能。
手作り食は、単なる食事ではなく「愛犬の体質に合わせた治療的アプローチ」です。
正しい方法で継続することで、かゆみや炎症を軽減し、皮膚や被毛の健康を守りながら、犬の生活の質を大きく向上させることができます。
本記事が、愛犬と一緒に踏み出す一歩🐾の一助になれれば幸いです。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

📚<主な参考文献>
- 環境省. (2022). アレルギー疾患に関する基礎知識. 環境省公式サイト.
- 日本獣医皮膚科学会. (2023). 犬のアトピー性皮膚炎(Canine Atopic Dermatitis)診療ガイド. 日本獣医皮膚科学会.
- 日本獣医師会. (2021). 犬の皮膚病と食事・栄養管理. 日本獣医師会.
※本記事は、上記の公開情報および獣医学・栄養学に関する一般的な知見をもとに、犬のアトピーと食事管理について一般の飼い主向けに分かりやすく整理・解説したものです。特定の治療法や食事内容の効果を保証するものではありません。愛犬の症状や治療、食事管理については、必ずかかりつけの獣医師にご相談ください。