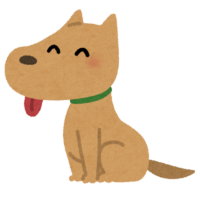
老犬になると、食欲が落ちたり、ドライフードだけでは物足りなさそうにしている姿を見かけることがあります。
そんなとき、多くの飼い主さんが頼るのが「ちゅ〜る」。
でも、ふと気になるのです…
「うちの子にチュールは何本まで大丈夫?」
「毎日与えても安全?」
「病気があっても使える?」
実は、この“ちょっとした疑問”こそ、老犬の健康や生活の質を左右する大切なポイントです。
本記事では、ただの給与目安ではなく、老犬の体調や生活リズムに合わせたチュールの上手な使い方について徹底解説します。
読み終わるころには、「今日からのチュールの与え方」がぐっと安心できるものになり、愛犬の笑顔をもっと増やせるヒントがきっと見つかります。
老犬の食に関する悩み

愛犬が高齢期に入ると、若い頃のように食事を完食してくれない、好きだったおやつに興味を示さないなど、食事の変化に戸惑う飼い主さんは多くいます。
「食べないと体力が落ちてしまうのでは」「このまま痩せ続けないか」と不安になるのは当然のことです。
たいていの愛犬が喜んで食べるチュールは“最後の切り札”のような存在。
同時に「何本まで大丈夫?」「毎日あげても平気?」という心配も出てきます。
本章では、4つの代表的な悩みを整理していきましょう。
老犬の食に関する悩み
老犬が食べなくなる理由は、単なる“好き嫌い”ではありません。
加齢による嗅覚・味覚の低下、歯の衰え、胃腸トラブル、認知機能の変化など、複数の要因が重なっています。
特に嗅覚の低下が大きく影響し、香りが弱いドライフードよりも、香りが強く舌触りの良いチュールだけを欲しがることも珍しくありません。
高齢犬は少し食べないだけでも体重が落ち、体力が戻りにくくなります。
そのため「食べるきっかけ」を作ることが非常に重要で、チュールはまさにその役割を果たします。
ドライフードだけでは
水分・栄養が不足するという不安
「お水をあまり飲まない」「ドライフードばかりで便が固い」、そんな悩みを抱えている飼い主さんも多いでしょう。
シニア期の犬は水分摂取量が減る傾向があり、脱水や腎臓トラブルを起こしやすくなります。
その点、チュールのようなペースト状おやつは約80%が水分で構成されているため、おいしく水分補給ができるのが魅力です。
「食べながら水分が取れるなら」と毎日のように与えている飼い主も少なくありません。
しかし、ここで注意したいのが「主食代わり」にしてしまうリスクです。
チュールは“おやつ・補助食品”に分類されるため、ビタミンやミネラルのバランスが総合栄養食ほど整っていません。
一時的な栄養補助や水分補給としては有効でも、「チュールだけで食事を済ませる」のは長期的には危険です。
つまり、単にカロリー量の問題ではなく、水分と栄養のバランスをどう取るかということは重要です。
おやつ・補助食品としてのチュール、
「何本なら安心か」という疑問
チュール1本あたりのカロリーはおよそ10〜13kcalほど。
体重5kgの成犬なら、1日の必要カロリーが約300〜350kcalなので、チュール1〜2本程度なら大きな負担にはならないと考えられます。
しかし、老犬の場合は基礎代謝が落ちているため、同じ本数でもカロリーオーバーになりやすいのです。
たとえば、活動量が少ないシニア犬の場合、1日の総摂取カロリーを体重5kgで約240kcal程度に抑えるのが理想です。
つまり、チュールを与えるなら1日1本、多くても2本までが目安になります。
ここで大切なのは、“まとめて与えない”ことです。
1本を朝晩に分ける、もしくは食欲がない時に少量トッピングとして使うことで、胃腸への負担を軽減しつつ楽しませることができます。
老犬は内臓機能が弱くなっており、塩分やカロリーを控えたい時期です。
欲しがるだけ与えるのではなく、あくまで“食欲スイッチ”として少量活用するのがポイントです。
さらに、病気や薬の服用がある子には、薬を混ぜる目的でチュールを使うという方法もあります。
「何本まで安心か」を考える際には、愛犬の体重・年齢・運動量・体調といった要素を総合的に判断することが重要です。
腎臓や肝臓に不安がある場合は、獣医師へ相談して与える量を調整しましょう。

わが家でも、投薬の時にチュールを使っています。
健康寿命を延ばしたい老犬への配慮
老犬にとって「食べること」は体力・免疫力を維持する最重要ポイントです。
食べない日が続くと筋肉量が落ち、免疫が下がり、体調が不安定になってしまいます。
シニア犬では以下のような体の変化が起きています。
- 腎臓や肝臓の機能低下:塩分やたんぱく質を摂りすぎると負担がかかる
- 関節や筋力の衰え:肥満や過剰カロリーが関節炎を悪化させる
- 歯や口腔の弱り:噛む力が弱くなり、柔らかいものを好む
こうした状態を踏まえると、チュールを選ぶ際には「低リン」「低ナトリウム」「機能性成分入り」などのシニア犬向け商品を選ぶのがベストです。
与える頻度を減らす代わりに、高栄養タイプを1本だけ使うなど、質を重視した使い方もおすすめです。
チュールを上手に活用し「少しでもおいしく食べられる環境」を整えることは、健康寿命を守る大切なサポートになります。
ただしチュールに依存するのではなく、あくまで補助として使うのが理想です。
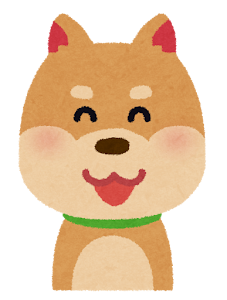
老犬にとって、毎日少しでも「美味しい」「食べたい」と思える瞬間をつくる、それがチュールの最大の価値だわん🐶
知っておきたい
「チュール」の基本情報

老犬にチュールを与えるとき、最初に理解しておきたいのは「チュールがどんな食品なのか」という基本情報です。
チュールは“犬が喜ぶ魔法のおやつ”として知られていますが、老犬に与える際には成分やカロリー、種類の違いをしっかり理解しておくことが大切です。
本章では、愛犬の健康を守りながら上手にチュールを取り入れるための基本情報をまとめます。
ちゅ〜るの成分・
カロリー・形状について
「ちゅ〜る」は株式会社いなばペットフードが販売している人気おやつシリーズで、猫用から火がつき、現在では犬用(いぬ用ちゅ〜る)も豊富に展開されています。
老犬は腎臓・肝臓・心臓などに不調が出やすい年代であるため、与える前に成分・カロリー・形状の特徴について知っておきたいですね。
■ 成分
犬用ちゅ〜るの主原料は、鶏肉やかつお、ささみなどのたんぱく質源。これに加え、植物性油脂・増粘多糖類・ビタミンE・緑茶エキスなどが含まれています。
いなば公式サイト(inaba-petfood.co.jp)によると、犬用の多くは着色料・保存料不使用で、人間の食材と同じ基準で作られているのが特徴です。
■ カロリー
1本(約14g)あたりのカロリーはおよそ10〜13kcal前後。
一見少なく感じますが、体重3〜5kgほどの小型犬にとっては無視できない数字です。
老犬になると基礎代謝が落ちるため、若い頃と同じ感覚で与えるとカロリーオーバーになることもあります。
「食べてくれるからつい何本も…」という与え方はおすすめできません。
■ 形状
柔らかいペースト状で、舐めるように食べられるのが最大の魅力。
歯が弱った老犬でも無理なく食べられ、食欲が落ちたときの補助や薬を飲ませる際の工夫にも使えます。
水分が多いため“おやつ”としての満腹感は得にくく、主食代わりにはなりません。

老犬にとっては「食べやすさ」「水分の多さ」という大きなメリットがあるよ❣️
おやつタイプと総合栄養食タイプの
違いと適用シーン
現在のチュールには大きく分けて2種類あります。
- ① おやつタイプ(一般食)
- ② 総合栄養食タイプ
老犬に与える際は、この違いを理解することが非常に重要です。
おやつタイプ(一般食)
最も流通しているのが「一般食」に分類されるおやつタイプです。
嗜好性を高めるために旨味が強く、カロリーやナトリウム量がやや高めに作られていますが、栄養バランスを満たす完全食ではありません。
食欲がない日や投薬補助、ドライフードへのトッピングとしては優秀ですが、「主食としての使用」は推奨されていません。
老犬の場合、「必要な栄養が不足する → 体調を崩す → 食欲がもっと落ちる」という悪循環が起きやすく、一般食だけで満足する食べ方は避けたいところです。
目的はあくまで“楽しみ”や“ご褒美”として考えましょう。
総合栄養食タイプ
近年登場した「ちゅ〜るごはん」や「ちゅ〜るビッツ総合栄養食タイプ」などは、1本で必要な栄養素を補えるよう設計された製品です。
たとえば、ビタミン・ミネラル・アミノ酸などをバランスよく配合し、主食としても使えるようになっています。

老犬に与える際は、”食事の一部として栄養補助”なのか、“喜ばせたい・ご褒美”のか、目的を明確にして選んでね❣️
公式な給与量目安(一般成犬向け):
「1日4本を目安」
チュール公式サイトや販売元情報(wan-churu.fun)では、一般的な成犬の場合、1日あたりの目安は約4本までとされています。
ただし、これは「健康で活動量のある成犬」を基準とした目安です。
老犬の場合は基礎代謝が20〜30%ほど低下していることが多く、同じ量を与えるとカロリー過多・塩分過剰になるおそれがあります。
老犬の場合の目安
- 体重3kgの老犬 → 1日1本程度
- 体重5kgの老犬 → 多くても1〜2本まで
- 体重7kg以上の中型犬 → 状況を見て2〜3本まで(主食とのバランスを重視)
また、一度に与えるのではなく、朝と夜に分けて少量ずつ与えるのがおすすめです。
老犬の胃腸は若い頃よりもデリケートなため、少量をこまめに与えることで体への負担を減らせます。
ポイント
- 「今日はたくさん動いたから1本増やそう」と、日ごとの体調や運動量に合わせる
- 「食欲がない日は少しトッピングして食べさせる」など、柔軟な使い方をことが大切です。
老犬の場合、体調、体重、既往歴、食欲により「安全に摂れる量」は大きく変わります。
公式の4本基準をそのまま適用するのではなく、「どんな目的で与えるのか」を考えることで、愛犬の健康を支えるパートナー食品に変わります。

わが家のハイシニア犬(2Kg)は、1日1/2本を朝・夕の投薬後に与えています。
目的はご褒美ですが、食欲が落ちてきているので”総合栄養食”を与えることが多いです。
“老犬”だから考えたい
「本数・与え方」の考え方

若いころは4本あげても平気だったけれど、今は体力も落ちて、腎臓や肝臓にも不安がある…。
今の愛犬にとって「どこまでなら大丈夫なのか?」を知ることは、愛犬の健康寿命を守るうえでとても大切です。
本記事では、老犬のエネルギー量の変化・チュールの本数設計の考え方・注意点・具体的な本数目安までを、科学的根拠を踏まえて解説します。
老犬の1日の必要エネルギー量が
成犬とどう違うか?
まず基本となるのが「DER(1日の必要エネルギー量)」です。
成犬(活動量が普通)の場合、計算式は以下の通り。
DER = 体重(kg) × 30 + 70 × 活動係数
活動係数は1.6前後(普通の成犬)とされます。
しかし老犬では筋肉量の減少・基礎代謝の低下により、活動係数は1.2〜1.4程度に下がるのが一般的です。
たとえば、体重5kgの犬で比較すると:
| 成犬(活動係数1.6) | 老犬(活動係数1.3) | |
|---|---|---|
| 1日の必要エネルギー量 | 約310kcal | 約260kcal |
このように、老犬は若い頃より1〜2割ほど少ないエネルギーで十分なのです。
この差を理解せずにチュールを以前と同じ量あげてしまうと、肥満や内臓への負担に繋がる恐れがあります。
チュールの本数を
決める際の考え方
愛犬の体重・活動量・健康状態を把握
まずは現在の体重と生活リズムを見直しましょう。
「以前より散歩時間が短くなった」「寝ている時間が増えた」などの場合、エネルギー消費量が減っているため、おやつのカロリーも見直す必要があります。
また、腎臓・肝臓・心臓に持病がある場合、獣医師と相談のうえで制限をかけることが望ましいです。
おやつとしてのカロリー目安
一般的に、犬のおやつは1日の総エネルギー量の10〜20%以内に抑えるのが理想とされています。
例えば、体重5kg・老犬で1日260kcalが必要な場合、おやつは 26〜52kcal以内 が目安です。
商品の1本あたりカロリー・成分を確認

「いなば ちゅ〜る(犬用)」の基本タイプは、1本あたり約13kcal(14g)。(参考:inaba-petfood.co.jp)
総合栄養食タイプや高齢犬用タイプもありますが、いずれも10〜15kcal前後が目安です。
したがって、先ほどの例では:
26〜52kcal ÷ 13kcal ≒ 1〜4本/日
という計算になります。
ただしこれは“上限”であり、老犬の場合はこれより少なめが理想です。
老犬特有の注意点を加味する
腎臓・肝臓・関節の負担がある場合の配慮
老犬では、腎臓や肝臓の働きが弱まる傾向があります。
チュールにはうま味成分(アミノ酸・塩分・リンなど)が含まれているため、これらの臓器に負担をかける可能性があります。
とくに慢性腎臓病や肝疾患がある子には毎日与えないのが原則です。
塩分・リン・たんぱく質のバランスを見て、
「腎臓サポート用」「シニア犬向け」「減塩タイプ」など、機能性チュールを選ぶのが安心です。
おやつばかりで“主食”がおろそかにならないように
チュールが好きな子ほど、フードを食べなくなることがあります。
この場合、チュールを“ご飯を食べるきっかけ”として使うのがベストです。
ドライフードや手作りご飯にトッピングして香りづけするだけでも、食欲を引き出せます。(参考:きょうのワンごはん)
「チュールだけでお腹を満たす」のではなく、「主食を食べるための補助」にすることが、老犬の健康維持には不可欠です。
具体的な“老犬向け本数目安の例”
体重5kg/活動量低めの場合:
1日1〜2本まで
- 1本13kcal × 2本 = 26kcal(1日の約10%)
→おやつとして適量。 - ご飯をしっかり食べているなら1本で十分。
- 食欲が落ち気味なら、朝晩1本ずつに分けるのがおすすめです。
体重10kg/活動量低めの場合:
日2〜3本まで
- 1本13kcal × 3本 = 39kcal(1日の約15%)
→上限ラインに近いため、他のおやつを減らすよう調整。 - シニア期で肥満傾向があるなら2本以内に抑えるのが安全です。
体重3kg/活動量・食欲が低下している場合:1日0.5〜1本まで
- 食べムラがあるときは、1本を2〜3回に分けて与えると、内臓負担を軽減できます。
- 体力が落ちている子には「水分補給+投薬補助」として使用するのもおすすめです。
高齢犬ならではの視点

飼い主さんの多くは、「食欲が落ちた愛犬に少しでも楽しくご飯を食べてもらいたい」「無理せず健康を保たせたい」、そんな優しさと願いを持っているのではないでしょうか。
本章では、老犬ならではのチュールの活用法・注意点・選び方についてまとめました。
老犬がチュールを喜ぶ理由と
“ご褒美以上の活用法”
シニア犬がチュールを好む理由は、単に「味が濃いから」ではありません。
犬の嗅覚は老化とともに鈍くなり、香りの強いものほど食欲を刺激します。
いなばの公式サイト(inaba-petfood.co.jp)でも、チュールの特徴として「高い嗜好性」が挙げられています。

食欲が低下したときのトッピングや投薬補助としても活躍するよ
食べムラがある老犬にとって、チュールは“ごはんを食べるスイッチ”になります。
ドライフードやウェットフードの上に少量をトッピングするだけで、香りが立ち、食いつきが良くなるケースが多いです。
薬を飲ませるのが苦手な子にも役立ちます。
錠剤を砕いて少量のチュールに混ぜれば、自然に舐め取ってくれることもあります。
いなば公式サイトでも、「投薬補助」としての活用は推奨されており、無理なくストレスを減らせる工夫です。
与え方の工夫
若い頃と違い、老犬は胃腸の働きがゆるやかになっています。
同じ量でも、一度に与えると消化不良や下痢を起こすことがあるため、「与え方」を工夫するだけで体への負担を大きく減らせます。
与え方の工夫
- 朝晩の食事にチュールを“香りづけ”として少量混ぜる
- 水またはぬるま湯で溶かしてスープ状にする(食べやすく・水分補給にもなる)
- 1本を2〜3回に分けて与えることで、血糖値の急上昇を防ぐ

ドライフードをふやかしてチュールを少量混ぜたり、スープ状にするのもオススメだよ。
こうした方法は、「本数を減らしながら満足度を上げる」ための賢いテクニックです。
一度に多く与えるよりも、“ちょこちょこ楽しめる”工夫が、老犬にとっての幸せな時間になります。
“老犬だからこそ”気をつけたい
長期的な影響と対応策
チュールは便利で美味しい反面、長期的な影響にも目を向けることが大切です。
おやつ過多のリスク
老犬は代謝が落ちているため、若い頃と同じ量のおやつを続けると肥満になりやすく、
肥満は関節への負担、糖尿病や心臓病のリスクにもつながります。
液状おやつを頻繁に与えることで歯垢・歯石がつきやすくなり、歯周病や口臭が悪化することもあります。
チュールを与えた後は、軽く歯や口を拭いてあげるなどのケアも取り入れましょう。
食べムラ・体重減少がある場合
「最近、急に体重が減ってきた」「食事の量が極端に減った」などの症状がある場合、単に嗜好の問題ではなく、内臓疾患や痛みが原因のこともあります。
そんな時は、「チュールで食べさせること」に頼りすぎず、必ず獣医師に相談をしましょう。
チュールはあくまで補助的な役割です。
本来の栄養バランスを維持しながら、体調に合わせて上手に使うことが大切です。
老犬の“生活質(QOL)”を
考えた与え方と選び方
「何本まで大丈夫?」という視点から一歩進み、老犬が“どうすれば快適に食べられるか”を考えることが、チュール活用の鍵になります。
歯が弱っている・飲み込みが心配な場合
加齢によって歯がぐらついたり、嚥下(えんげ)機能が落ちると、固形物が食べづらくなります。
その点、チュールのようななめるだけで摂取できる形状は、まさに老犬に向いています。
水分摂取量が減っている場合
水分摂取量が減る子には、チュールをぬるま湯で割って与えると、水分補給+栄養補助の両立ができます。
とくに夏場や乾燥する季節におすすめです。
持病がある場合
近年では、「シニア犬用」「腎臓ケア」「関節サポート」など、機能性ちゅ〜るも登場しています。
例えば、
- 低リン・低ナトリウムタイプ:腎臓・肝臓への負担を軽減
- コンドロイチン・グルコサミン配合:関節サポート
- ビタミンE・オメガ3配合:免疫維持や皮膚被毛の健康に貢献
単に“何本あげるか”ではなく、“どのチュールを選ぶか”によっても老犬の健康維持には重要です。
食欲が不安定になる老犬にとって、チュールは「おいしいご褒美」であると同時に、「生きる喜び」にもなるでしょう。
飼い主さんの工夫次第で、チュールは“嗜好品”から“生活サポート食品”に変わります。
「本数」ではなく「目的」で選ぶこと。
それが、老犬の心と体を幸せにするチュールとの付き合い方と言えるでしょう。
よくある質問FAQ

Q:1日4本は老犬でも大丈夫?
一般的に「1日4本」は成犬向けの公式目安で、老犬にそのまま当てはめると過剰になるケースが多いです。
老犬は基礎代謝が低下し、筋肉量も落ちやすく、若い頃と同じカロリーを必要としません。
また、腎臓・肝臓・心臓などの主要臓器の代謝能力も年齢とともに低下します。
判断の目安としては、以下の3点をチェックしてください。
判断の目安
- 体重の増減:
増えている → 本数が多い可能性 - 便の状態:
ゆるい・軟便 → チュールが多い合図 - 食事量:
総合栄養食を残す → チュールに偏っている
老犬の場合、「1〜2本」で様子を見るのがおすすめです。

療養中や持病がある場合は、獣医師さんに相談しましょう。
Q:夜だけ本数を増やしても良い?
老犬の場合、「夜に食欲が出る」「朝は食べたがらない」ということもよくあります。
このようなリズムの変化は加齢によるもので、無理に朝に食べさせようとせず、食べられる時間帯を大切にするのが基本です。
ただし、夜にまとめてチュールを多く与えるのは避けましょう。
理由は以下の通りです。
理想は、夜の食事前に1本を分けて少量ずつ与えることです。
「夜だけチュール増量」は、老犬には負担が大きく、慢性的な偏食や栄養バランスの崩れにつながります。

“一気に”ではなく“分けて少しずつ”がコツだよ❣️
Q:他のおやつもあげてるけど
どう調整すればいいの?
老犬に複数のおやつを与える場合は、まず「1日のカロリー上限」を決めることが最優先です。
目安として、老犬は体重あたり約70〜80kcal/kg 程度が必要ですが、持病や活動量によって個体差が大きくなります。
調整の手順は次の通りです。
おやつ量の調整手順
- その日に与える他のおやつの合計カロリーを確認する
- チュールのカロリー(1本約7〜14kcal)を加える
- おやつ合計が1日の摂取カロリーの10%以内に収まるよう調整する
たとえば体重5kgの老犬なら、おやつは1日約35〜40kcal以内が望ましいので、チュールは2本程度が上限になります。
Q:持病の老犬には何本が安全?
持病がある場合は、“何本”よりも成分と頻度の管理が重要です。
腎臓病の老犬
低リン・低ナトリウム設計の「ちゅ〜る腎臓配慮タイプ」を選び、週に1〜2回、1本までが理想です。
通常のチュールは塩分やリンがやや多く、腎臓に負担がかかるため控えめにしましょう。
心臓病の老犬
塩分制限が必要なため、通常タイプは避けるのが基本です。
「心臓病ケアフードに香りづけでごく少量混ぜる」程度に留めるのが安心です。
認知症(認知機能低下)の老犬
嗅覚や味覚が鈍くなりやすいため、「香りの強いチュールをトッピングに使う」のは効果的です。
ただし食べすぎによる肥満が脳機能を悪化させることもあるため、1日1本を上限にコントロールしましょう。
いずれの場合も、“毎日与える習慣”ではなく“必要な時に補助として使う”意識が重要です。
継続的に与える場合は獣医師に本数の相談をすることが最も安全です。
Q:ドライフードを残すとき、
チュールの本数を増やしてもいい?
「食べてほしいからチュールを増やす」というのは、多くの飼い主さんが通る悩みですが、結論としてはチュールを増やす前に原因を確認することが重要です。
老犬がドライフードを残す主な理由は以下の通りです。
ドライフードを残す原因
- 歯・口内トラブルで噛みにく
- においが弱く、嗅覚の衰えで興味がわかない
- 胃腸が弱っていて量を食べられない
- 単純に味の好みが変わった
チュールの本数を増やすのではなく、次のような工夫が効果的です。
食欲をわかせる工夫
- ドライフードに「小さじ1〜2杯のチュール」を混ぜる
- ぬるま湯でふやかして匂いを立たせる
- 柔らかい総合栄養食やシニア向けウェットに切り替える
つまり、チュールは「食べさせるきっかけ」であり、「主食の代わり」ではありません。
“チュールを足す”より、“ごはんを工夫する”方が、老犬の健康を長く守れます。

本数を増やすより、フードの見直しや健康チェックを最優先しましょう。
毎日の体調・食欲・うんちの様子を見ながら、
「今日は半分」「今日は1本お楽しみ」といったゆるやかな調整を習慣にすることで、愛犬との時間をより穏やかに、長く楽しむことができるでしょう。
実践のポイント

老犬にチュールを与えるときに一番大切なのは、「本数」だけでなく、愛犬の体調・生活リズム・既往症などを踏まえて総合的に判断することです。
特に老犬は若いころと比べて代謝が落ち、食欲や体調の波が大きいため、同じ本数でも負担の度合いがまったく違ってきます。
本章では、今日からすぐに使える“実践的な見直しポイント”を整理して解説します。
与えた結果を観察しよう
老犬にチュールを与えるときに欠かせないのが、「与えた後の変化を見ること」です。
老犬は体調の変化が表情や行動に出やすく、食べ物によってもすぐに影響が現れます。
日々のチェックポイント
- ウンチの状態
柔らかすぎる・下痢気味なら脂肪や添加物に反応している可能性があります。
正常なウンチはほどよく形があり、つやが少しある程度です。 - 食欲の変化
チュールをきっかけに主食への意欲が戻るなら良い兆候です。
「チュールしか食べない」状態が続くと、嗜好性依存のサインです。 - 体重の増減
1〜2週間単位で体重を記録し、増えすぎ・減りすぎを防ぎましょう。 - 毛づや・皮膚の状態
栄養バランスが崩れると被毛がパサついたり、フケやかゆみが増えることがあります。 - 活力・散歩の様子
チュール後に元気が増すなら良い兆候です。
眠りがち・動かなくなった場合は糖分過多の可能性があります。
特に高齢になるほど胃腸機能は弱くなり、少量のチュールでもお腹に響くことがあります。
1日の中で気になる変化が1つでもあれば、本数を見直すタイミングです。
“本数”を見直すタイミング
老犬期は代謝や臓器機能が変化するため、チュールの適量は季節や体調によっても変わります。
体重測定や血液検査の結果により調整しましょう。
見直しが必要なサイン
- 体重が急増している
→ おやつ過多、チュールを減らすサイン - 体重が減少している
→ 食欲不振、チュールで食事サポートを検討 - 腎臓・肝臓の数値が上昇している
→ ナトリウムやリンを控えたチュールに変更 - 貧血・脱水傾向がある
→ スープタイプや水分補給目的のチュールでサポート
とくに「食事量を減らしていないのに体重が減る」「尿の色が濃い」場合は、すぐに獣医師に相談をしましょう。
獣医師に相談すべきサイン
老犬にチュールを与える本数が適切かどうか、自宅で判断できない場合もあります。
特に以下のようなサインが出ている場合、チュールの本数だけでなく食事設計そのものの見直しが必要です。
早めに受診したいサイン
- 急激な体重減少・増加
- 数日続く下痢・嘔吐
- 明らかな水分摂取量の増加(腎臓病の可能性)
- 夜鳴き・徘徊(認知機能の低下が原因の場合あり)
- チュールを見せても反応が鈍い
特に腎臓や心臓に不安があるシニア犬は、塩分・リン・水分量を総合して調整する必要があり、「何本」が良いかは愛犬によって大きく異なります。
獣医師に現在の食生活を具体的に伝えることで、より正確なアドバイスを受けられます。
チュールだけに頼らない老犬ケア
チュールはあくまで“補助”の位置づけ。
本来の目的である「健康を支えながら、楽しく食べる時間をつくる」ためには、次のバランスが欠かせません。
主食の見直し
- 主食(総合栄養食)で必要な栄養をしっかり補う。
- ふやかして消化を助ける。
- トッピングとして少量のチュールを混ぜることで、嗜好性がアップさせる。
- 食事の温度を40℃前後に調整して香りを引き出す。
- 1日の食事回数を3〜4回に分ける。
水分補給
- シニア犬は喉の渇きを感じにくいため、チュールをスープ状にして与える。
- スープやウェットフードを活用する。
運動・環境
- 適度な運動:食後の軽い散歩で代謝と腸の動きを促進する。
- 認知症予防のための散歩、脳刺激おもちゃを活用する。
- 快適な環境:寝床の温度や湿度も食欲に直結します。冷え・暑さ対策を忘れずに。

チュールに頼りすぎると栄養バランスが偏ったり、食欲の波をコントロールしづらくなったりすることがあるから気をつけよう!
老犬期は「食事=栄養補給」だけではなく、「食べる喜び」「生活の質(QOL)」を支える時間でもあります。
チュールはその一部を助ける素晴らしいツールですが、あくまで補助として使い、本数の増やしすぎには気をつけてあげたいところです。
まとめ

老犬にチュールを与えるときに大切なのは、「何本あげるか」だけでなく、その子の体調・年齢・病歴に合わせて“どう使うか”を考えることです。
チュールは便利でおいしいご褒美ですが、老犬にとっては栄養サポートやコミュニケーションの一部として活用するのが理想です。
以下に、この記事の要点をわかりやすく整理しました。
老犬とチュールの基本的な考え方
- 「チュール=おやつ」ではなく、「老犬ケアの補助食」として捉える。
- 基本目安は1日1〜2本程度(体重・体調によって調整)。
- 成犬用の“1日4本”は老犬には多い場合がある。
- 腎臓・心臓疾患がある子は、ナトリウム・リンの低いタイプを選ぶ。
与えるときの工夫と観察ポイント
- ドライフードに混ぜて食欲を刺激する
- スープ状にして水分補給にも役立つ。
- ウンチの状態・体重・毛づや・活力を毎日チェックする。
- 「チュールしか食べなくなった」場合は、嗜好性依存のサインかも。
- 食後に下痢・嘔吐・むくみがある場合は、すぐに与える量を見直す。
定期的な健康チェックと本数見直し
- 体重測定:月1回、血液検査:半年に1回を目安にする。
- 体重が増える → チュールのカロリー過多を疑う。
- 体重が減る → 食欲不振時のサポートとしてチュールを活用する。
- 腎臓・肝臓の数値が高い場合は、塩分控えめタイプに変更する。
- 獣医師と連携し、チュールの与え方を調整する。
- チュール+生活全体で“老犬ケア”を最適化しましょう。
- 主食(総合栄養食)を軸に、チュールはトッピングとして使う。
- 水分不足になりやすい老犬には、チュールをスープ状にして水分補給する。
- 快適な環境(温度・湿度・寝床)を整えることも食欲維持に効果的。
- 適度な運動・スキンシップも、健康と幸福度の維持につながる。
- 「チュールをあげる=愛情」ではなく、“体に優しい形で愛を届ける”意識で与える。
さいごに
老犬のチュールは、“楽しみの時間”であると同時に、健康を見守るためのバロメーターでもあります。
今日の食欲・表情・体の動き、それらを見ながら、チュールの本数と与え方を日々アップデートしていくことが大切です。
本記事が、“あなたの愛犬とチュールの最適なバランス“を見つける手助けになれれば幸いです。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

📚<出典・参考情報>
- いなばペットフード株式会社. (公式サイト). 「CIAOちゅ〜る」製品情報. https://www.inaba-petfood.co.jp
- 大谷智子・山崎良太(監修). (2021). 『犬の高齢期ケアガイド』 誠文堂新光社.
- 日本小動物獣医師会. (2019). 『シニア犬の食事管理と栄養指針』 小動物臨床栄養学委員会資料.
- AAFCO (Association of American Feed Control Officials). Official Publications and Dog Nutrient Profiles.
- Case, L.P., Daristotle, L., Hayek, M.G., & Raasch, M.F. (2011). Canine and Feline Nutrition (3rd ed.). Mosby.
- FEDIAF (The European Pet Food Industry Federation). Nutritional Guidelines for Complete and Complementary Pet Food for Cats and Dogs.
- Hand, M.S., Thatcher, C.D., Remillard, R.L., & Roudebush, P. (2010). Small Animal Clinical Nutrition (5th ed.). Mark Morris Institute.
※本記事の「チュールは老犬に何本まで与えて良いか」という基準は、公表されている一般的な栄養情報をもとに分析し、老犬の健康維持に配慮してまとめています。特定の商品・企業・医療機関の見解ではありません。
※老犬の体調・持病・食欲には大きな個体差があります。初めて与える場合や食欲低下が続く場合は、かかりつけの獣医師へご相談ください。