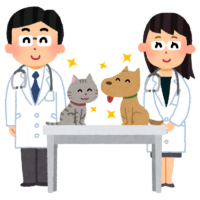
あなたの愛犬に「手作りごはんを食べさせたい」と思ったことはありませんか?
市販フードの原材料や添加物に不安を感じ、「自分の手で安全なごはんを作ってあげたい」と考える飼い主さんは年々増えています。
しかし一方で、「獣医さんは手作りごはんを危険だと言う」「栄養バランスが崩れると病気になるらしい」といった声も多く、ネット上では真逆の意見が飛び交っています。
実は、私自身も同じように悩んだ一人です。愛犬が尿石症を発症し、療法食が必要になったことをきっかけに、手作りごはんという選択肢を考えるようになりました。
しかし、かかりつけの獣医師さんからは「反対ではないけれど、積極的に勧めるものでもない」という慎重な反応でした。
「やめた方がいいのかな…」という不安と、食事の選択肢が限られることへの葛藤、そして諦めきれない気持ちの間で揺れていました。
そこで自己流で進めるのではなく、通信講座で基礎を学び、犬の栄養や手作りごはんに関する書籍を読みながら、少しずつ知識を整理していきました。
本当に手作りごはんは危険なのでしょうか?
それとも、正しい知識と向き合い方があれば、安全に続けられる選択肢なのでしょうか?
本記事では、獣医師の見解や現場で語られている視点をもとに、「手作りごはんを選ぶべき場合・避けるべき場合」を整理し、あなたの愛犬にとって無理のない判断ができるよう解説します。
読み進める中で、「うちの子には何が合っているのか」を、落ち着いて考えるヒントを持ち帰っていただければ幸いです。
目次
手作りごはんの危険性を
気にする本当の理由

愛犬の手作りごはんに興味がある、またはすでに与えている飼い主さんの中には、
「本当にこれで合っているのか」
「獣医師さんから“危険”と言われて戸惑った経験がある」
といった葛藤を抱える方も多いのではないでしょうか。
犬の手作りごはんについて調べていくと、肯定的な意見もあれば、強い否定の言葉に触れ、不安になることもあるかもしれません。
本記事では、なぜ手作りごはんが不安視されることがあるのか、そして獣医師が「危険性」という言葉を使う背景について、現場で語られている視点をもとに整理していきます。
「市販フードが不安」
愛犬に“もっと良いものを”と思う気持ち
手作りごはんに関心を持つきっかけとして、最も多いのが市販フードへの不安です。
- 原材料がよく分からない
- 添加物や保存料が気になる
- 食いつきが悪い、体調に変化があった
こうした経験をすると、「自分で作った方が安心なのでは」と考えるのは自然な流れです。
実際、手作りごはんには、
- 食材を自分で選べる
- 香りや温度で食欲が上がる
- 体調や好みに合わせて調整できる
といった確かなメリットがあります。
しかし一方で、獣医師が懸念するのは「想いの強さ」と「知識の不足」がセットになったときです。
愛情があるからこそ、間違いに気づきにくい。ここに、手作りごはんの落とし穴があります。
手作りごはんが、
なぜ一部の獣医に危険と言われるのか
獣医師が「手作りごはんは危険」と言うとき、すべての手作り食を否定しているわけではありません。
問題視されているのは、主に次のようなケースです。
栄養バランスが崩れやすい
家庭で作るごはんは、どうしても、
- カルシウム・リン
- 微量ミネラル
- ビタミン類
が不足、または過剰になりやすい傾向があります。
特に怖いのは、すぐに症状が出ないことです。
数か月〜数年かけて、骨・内臓・皮膚トラブルとして現れるため、「原因が手作りごはんだと気づきにくい」のです。
「良かれと思って」が裏目に出る
ネットやSNSには、
- この食材が良い
- これは毒だから絶対ダメ
といった情報が溢れています。
しかし、犬の体格・年齢・持病によって適量は大きく異なります。
一部だけ切り取った情報を信じてしまうと、慢性的な負担を与えてしまうことがあります。
獣医師は「結果」を見ている
家庭では元気に見えていても、動物病院には、
- 血液検査で異常が出た犬
- 成長期に骨格異常が起きた犬
- 腎臓・肝臓に負担がかかった犬
が実際に来院します。
獣医師は「うまくいっている手作りごはん」よりも、トラブルが起きたケースを数多く見ている。
だからこそ、強めの言葉で注意喚起をすることがあるのです。

手作りが悪いのではなく、“知識のない手作り”が危険なのです。
獣医師が現場で見ている
「手作りごはんトラブル」のリアル
多くの獣医師が感じているのは、「手作りごはん=悪」ではなく、「自己流・我流の継続が怖い」という点です。
よくある現場トラブル例
- 鶏肉と野菜だけの食事が続き、カルシウム不足
- 「ヘルシー」を意識しすぎて脂質が極端に少ない
- 病気があるのに健康犬と同じ手作り食を与えている
これらはすべて、飼い主さんの善意から生まれています。
獣医師が本当に伝えたいこと
多くの獣医師は、
「手作りごはんをやめてほしい」のではなく、
「正しい設計なしで続けるのをやめてほしい」と考えています。
- 栄養設計を学ぶ
- 獣医師や専門家に相談する
- 市販フードと併用する
こうした現実的な選択肢を知ってほしい、という思いが背景にあります。
不安になるのは、それだけ真剣に愛犬の健康を考えている証拠です。
大切なのは、極端な情報に振り回されず、「なぜ危険と言われるのか」を理解したうえで選択することです。
手作りごはんは、正しく向き合えば「危険」ではなく、管理が必要な選択肢のひとつに変わります。
“迷い”を解く3つのポイント
手作りごはんを「安全に、無理なく」続けるためには、次の3つの視点を押さえることが重要です。
① 安全な作り方の基本
調理中の加熱・冷却・保存管理を正しく行い、食材の変質や細菌繁殖を防ぐ。
特に鶏肉や魚介類は加熱の徹底が必須です。
② 危険な食材の見極め方
SNSで「犬にいい」と紹介されている食材でも、与え方や量を間違うと危険なものがあります。
代表的なNG食材(玉ねぎ、ネギ類、チョコ、ぶどう、ナッツ、生卵など)を把握しておくことが前提です。
③ 獣医が勧める“バランス食”の考え方
完全な手作りにこだわらず、「市販フード+手作りトッピング」など、栄養バランスを崩さずに愛情を伝える方法を知ること。
実際、多くの臨床獣医師もこの“併用スタイル”を推奨しています。

わが家でも、併用スタイルを長年実践してきました❣️
手作りごはんの
代表的な5つの危険性!
愛犬や愛猫のために「安心で安全なごはんを自分で作りたい」と思う飼い主さんは年々増えています。
しかし、「手作りごはんが原因で体調を崩してしまった」という現実も少なくありません。
なぜ、“良かれと思って作ったごはん”が危険になるのでしょうか?
本章では、特に多くの飼い主さんが陥りやすい5つの危険性について詳しく解説します。
栄養バランスの崩れ ―
必須栄養素の過少・過剰
⚠️「見た目」や「好み」だけでは栄養が偏る
手作りごはんの一番の落とし穴は、見た目が美味しそうでも栄養バランスが整っていないことです。
人間の食事では「肉・野菜・ごはんがあればOK」と思われがちですが、犬には人と異なる必須栄養素の比率があります。
例えば、犬の体は人間よりも多くのタンパク質を必要とし、またカルシウムとリンのバランスが非常に重要です。
肉中心のメニューにすると「リン」が過剰になりやすく、骨や歯を作る「カルシウム」が不足します。
この状態が続くと、骨の脆弱化・関節の変形・成長不良を引き起こすことがあります。
⚠️よくある誤解:栄養剤を少し入れれば安心?
中には「サプリメントで補えばいい」と考える方もいますが、これは誤解です。
栄養は“バランス”が命”であり、1種類だけを補っても、他の栄養素との比率が崩れると逆効果になることもあります。
特に脂溶性ビタミン(A・D・E・K)は体内に蓄積されやすく、過剰摂取による中毒症状(関節痛・肝障害・骨異常など)を招く危険もあります。
実際の獣医師の現場では
動物病院では、「毛づやが悪い」「体重が減った」「骨格が発達しない」などの症状で来院し、検査すると原因が栄養バランスの崩れによるものだったというケースが多くあるようです。
特に成長期の子犬や老犬では影響が出やすく、食事内容を見直すことで改善する場合も少なくありません。
安全に手作りするための対策
手作りごはんを安全に続けるためには、必ず栄養設計をベースにすることが大切です。
「なんとなく」ではなく、以下のような手順を取り入れましょう。
栄養設計の手順
- 愛犬・愛猫の体重・年齢・運動量に合ったカロリーと栄養素を算出する
- 動物栄養学に基づいたレシピ本や獣医監修のメニューを参考にする
- 一度でもよいので、獣医師または栄養士に食事設計を相談する
感覚ではなく“数値で考える”ことで、健康被害の多くを防ぐことができます。
- Oliveira M. C. C. 他. “Analysis of recipes of home‑prepared diets for dogs and cats.” British Journal of Nutrition, 2017. (PMC)
- University of California, Davis. “Homemade dog food recipes can be risky business, study finds.” 2013.
(ucdavis.edu)- Royal Canin Academy. “Homemade diets – good or bad?” 2022.
(academy.royalcanin.com)
犬に“有害な食材”の
誤使用リスク
⚠️「人間に良い=犬猫にも良い」は大きな誤解
手作りごはんで次に多いトラブルが、有害食材の誤使用です。
飼い主さんの中には「人間が健康に良い食材だから大丈夫」と思い込んでしまう方もいますが、犬や猫の体の代謝機能は人間と大きく異なり、私たちに無害な食品でも、彼らにとっては毒になることがあります。
⚠️代表的な危険食材
動物病院(例:さくま動物病院【sakuma-anihos.com】)でも実際に注意喚起されている代表的な食材には以下があります。
- 玉ねぎ・ねぎ・にんにく類:赤血球を壊し、貧血を引き起こす。加熱しても毒性は残る。
- ぶどう・レーズン:腎不全を起こす可能性。少量でも危険。
- チョコレート・ココア:テオブロミン中毒。心臓・神経に影響。
- キシリトール:血糖値を急激に下げ、肝障害の原因にも。
- ナッツ類・アボカド・アルコールなども中毒リスクがある。
これらの食品は「少量なら平気」と誤解されがちですが、体重や体質によってわずかな量でも重篤な中毒症状を起こす場合があります。
⚠️SNS発の“誤情報レシピ”に注意
近年では、SNSや動画サイトで「簡単・健康・愛犬が喜ぶ手作りごはん」として紹介されているレシピの中に、上記のような危険食材が使われているケースも見受けられます。
特に、人間向けの健康食ブーム(低糖質・発酵食品・スーパーフードなど)を取り入れた内容は要注意です。
「SNSで見た」「フォロワーが多い人が紹介していた」という理由だけで真似するのは危険です。
その情報が獣医師監修かどうかを必ず確認しましょう。
⚠️知らないうちに与えてしまう“隠れリスク”
意外と見落とされがちなポイントが、調味料や加工食品に含まれる成分です。
例として、ハムやツナ缶、味付きの野菜スープなどには塩分・香辛料・添加物が多く含まれています。
「少しだけ」「汁を薄めているから大丈夫」と思っても、犬猫の腎臓や肝臓には大きな負担となります。
⚠️安全のためにできるチェックリスト
- 人間用のレシピをそのまま流用しない
- 加熱・下処理を必ず行う(特に肉・魚・卵)
- SNSや動画の情報は必ず獣医監修か確認
- 不安な食材は、動物病院で「これは与えていいか?」を相談する
犬や猫の手作りごはんは、正しい知識と準備があれば健康に良い選択肢にもなります。
しかし、ちょっとした思い込みや「人間基準」での判断が、彼らにとっては深刻な健康被害につながることを忘れてはいけません。
「愛情」を「安全」に変えるためには、情報源の質と専門的なサポートが欠かせません。
- Cortinovis, C. & Caloni, F. “Household Food Items Toxic to Dogs and Cats.” Frontiers in Veterinary Science, 2016. (Frontiers)
- “Raw diets for dogs and cats: a review, with particular reference to microbial hazards.” Davies, R.H. Journal of Small Animal Practice, 2019. (onlinelibrary.wiley.com)
- U.S. Food & Drug Administration (FDA). “Get the Facts! Raw Pet Food Diets can be Dangerous to You and Your Pet.” 2018. (U.S. Food and Drug Administration)
- “(Raw) food for thought: antimicrobial resistance and BARF pet diets.” NCCEH (Canadian Centre for Policy Alternatives). 2022. (ncceh.ca)
調理・保存管理の
不備による衛生リスク
手作りごはんは「愛情を込めて作る安心食」と思われがちですが、実は家庭調理ならではの衛生リスクが潜んでいます。
特に問題になるのが、「加熱不足」「冷却・保存管理の不備」「再加熱の方法」です。
これらのミスは、人間の食事では大丈夫でも、犬の体には大きな負担となることがあります。
生肉・半生調理による細菌リスク
犬や猫は肉食動物のイメージが強いため、「生肉も平気」と考える飼い主さんも多いですが、サルモネラ菌・カンピロバクター・リステリア菌などの感染リスクは非常に高いです。
実際に、獣医師の間でも「下痢や嘔吐で来院した犬の一部が、手作り生肉食を食べていた」というケースが報告されています。
これらの菌は、加熱(75℃以上)でほぼ死滅しますが、加熱が不十分だと菌が残り、愛犬の腸内だけでなく、調理者(飼い主)にも感染する恐れがあります。
保存方法のミスによる変質・毒素発生
作り置きの際、冷蔵庫や冷凍庫で保存しても、保存温度や期間を誤ると食材が変質します。特に注意したいのが、
- 常温に長時間放置
- 一度解凍した食材を再冷凍
- ぬるい温度での再加熱(菌が死なず増殖)といったケースです。
これらは、食中毒や肝臓障害、腸内環境の悪化を招く可能性があります。
「見た目やニオイは問題なさそうでも、実は菌が繁殖していた」というのが、最も怖い点です。
安全のためのポイント
- 肉や魚は必ず中心までしっかり加熱(75℃・1分以上)
- 冷蔵は2日以内、冷凍は2週間以内を目安に使い切る
- 解凍は電子レンジまたは冷蔵庫で、常温放置は避ける
- 作り置きは1食分ずつ小分けして冷凍する
家庭調理で安全を確保するには、“清潔さ”と“温度管理”がカギです。
愛情のこもった食事を「安全に届ける工夫」が欠かせません。
ライフステージ・健康状態に
合わない食事の選択
「手作りなら健康に良い」と思っていても、ライフステージや健康状態に合っていないと、逆に体を壊してしまうことがあります。
犬や猫の栄養バランスは、人間以上にデリケート。成長段階・体質・病歴によって必要な栄養素やカロリーがまったく違うため、一律のレシピでは対応できません。
子犬に多い栄養過不足
子犬や子猫は急速に成長するため、カルシウム・リン・タンパク質などのバランスが非常に重要です。
手作りごはんでカルシウムが不足すると、骨の変形や成長障害につながる恐れがあります。
また、成長期に脂質を控えすぎると、免疫力の低下や皮膚トラブルが起きることも。
特に「鶏むね肉と野菜だけ」など、ヘルシー志向すぎるメニューは要注意です。
老犬・老猫に多い
エネルギー・たんぱく制限の誤り
老犬・老猫になると代謝が落ち、腎臓や肝臓への負担が懸念されます。
しかし「たんぱく質を減らした方がいい」と思い込み、極端に減らすと、筋肉量の低下や体力喪失を招きます。
シニア期こそ、高品質なたんぱく質を適量摂ることが重要。獣医師が推奨する「腎臓に優しいレシピ」や「消化吸収の良いメニュー」を選ぶべきです。
持病がある子には要注意
糖尿病、心臓病、アレルギー、腎疾患などがあるペットに自己流の手作り食を与えると、症状の悪化につながる危険があります。
例えば、糖尿病の犬に炭水化物の多いレシピを与えたり、腎疾患の猫に高リン食材を使ったりするのは厳禁です。
このようなケースでは、必ず獣医師の栄養指導を受けることが基本です。
“監修なし”“簡単レシピ”
に潜む落とし穴
SNSやブログ、YouTubeなどでは「簡単・安全な手作りごはんレシピ」が数多く発信されています。
しかし、実際には専門知識に基づかない“自己流レシピ”や“獣医監修なしの情報”も多く、これが最も危険な落とし穴です。
“簡単レシピ”の裏にある落とし穴
「鶏むね肉と野菜だけ」「ごはんにツナを混ぜるだけ」といった“簡単レシピ”は、一見ヘルシーに見えますが、
- カルシウムやミネラル不足
- タンパク質・脂質の過不足
- ビタミンA・E・B群の欠乏
など、長期的な栄養失調を引き起こすことがあります。
特にSNSでは「うちの子も元気です!」という体験談が拡散されがちで、科学的根拠に乏しい“感覚ベース”の情報が広まっています。
監修のない情報は“危険を見逃す”
ペットの栄養学は人間の栄養学とは全く異なります。
たとえば犬猫にとって有害な食材(玉ねぎ・ブドウ・チョコレートなど)は、少量でも中毒症状を起こします。
獣医師が監修していない情報は、こうした危険食材の知識や摂取量の基準が曖昧な場合が多く、
「知らずに与えていた」「ネットの情報を信じて中毒を起こした」という事例も報告されています。
信頼できる情報源を選ぶコツ
- 獣医師または動物栄養学専門家が監修していること
- **栄養バランス(たんぱく質・脂質・カルシウム比率)**が明示されていること
- 科学的根拠や研究データに基づいていること
- 商業目的の広告ではないこと

当サイトでご紹介しているレシピは、獣医師監修ではありませんが、栄養学的根拠に基づいた一般向けのレシピです🐶
これら3つのリスクは、いずれも「手作り=悪」ではなく、知識と管理の不足が“危険”を生むという共通点があります。
大切なのは、SNSの情報全てで落とし穴があるということではありません。大切なのはうのみにせず、獣医師や栄養専門家の監修のもとで“安全に続ける方法”を選ぶことです。
獣医の視点と実践チェック
獣医が“手作りごはんを勧めない/限定で使う”理由とは
獣医学・動物栄養学の専門家が、なぜ飼い主に手作り食を全面的には推奨せず、むしろ限定的な併用を勧めるのか、その理由を見ていきましょう。
まず、米国の University of California, Davis が実施した研究によると、市販の手作りレシピ200件を解析したところ、95 %ものレシピが必須栄養素を少なくとも1つ以上満たしていなかったという結果が出ています。 (ucdavis.edu)
このことから、「材料をそろえて作れば安心」という単純な考えでは、犬の健康を守れないことが明らかです。
さらに、別の専門サイトでは「手作り・家庭調理・生食などは、栄養バランスだけでなく、細菌汚染・寄生虫・保存管理のリスクも高い」と指摘されています。 (Auburn University)
つまり、「獣医師が手作りをすすめない」「限定的にしか使わない」のは、以下のような理由によるものです:
- 完全な栄養設計がなされていないことが多い
- 調理・保存・衛生面の管理コストとミスの可能性が高い
- ライフステージ(子犬・老犬)や疾患があるペットでは、少しのミスが重大な健康影響につながる
そのため、「手作りごはん=絶対安全」という構図は獣医師から見るとリスクのある誤解です。
実際、多くの獣医師が「市販の総合栄養食を軸に、手作りをトッピングや時々使いにするハイブリッド方式」を提案しています。
手作りごはんが特に危険な
3つの状況
手作りごはんが比較的安全に機能するケースもありますが、次の状況ではリスクが特に高まるため、獣医師が慎重になるようです。
成長期の子犬・子猫
成長期にはカルシウム・リンの比率、タンパク質・脂質・ビタミンDなどの必須栄養素が非常に厳密に求められます。
市販フードでも「子犬用」「子猫用」として設計されていることが多く、栄養が整っています。
ところが手作りだと「成長期だから肉をたくさん入れておけばOK」という認識だけでは、カルシウム不足やリン過多、骨格の発育異常に繋がる恐れがあります。 (PMC)
老犬・老猫(シニア期)
シニアになると代謝や消化吸収機能が低下し、腎臓・肝臓・心臓などへの負担も考慮すべきです。
ここで「ヘルシーに肉少なめ・野菜多め」にしすぎると、逆にタンパク質不足による筋肉量低下・体力喪失を招くこともあります。
手作りで“あえて控える”のであれば、その分何をどう補うかを設計できていないと危険です。
慢性疾患・アレルギー・特別な体質を持つペット
例えば腎臓病・心疾患・消化器疾患・多発アレルギーなどのペットには、通常以上に精密な栄養管理が必要です。
獣医が監修する療法食や処方食がある状況で、自己判断で手作りに切り替えたり併用したりすることは、症状悪化の危険があります。
“手作り+市販”というハイブリッド戦略も有効ですが、ここでは特に獣医師のチェックが必須です。
これら3つの状況では、手作りごはんを「やらない」「やるなら厳格に管理」のいずれかを選ばなければなりません。
もしあなたの愛犬が「子犬・老犬・病気がある」の場合は、この点を最優先で押さえてください。
自家製ごはんを安全にするための
チェックリスト
獣医師さんの視点を交えて、実際に家庭で手作りごはんを始める飼い主さんがチェックすべき項目を「飼い主目線で分かりやすく」整理しました。
- 食材リスト:
- 使用する肉・魚・野菜・穀物は**ヒューマングレード(人用基準)**を選ぶ。
- 与えてはいけない食材リストを常備する(例:玉ねぎ・ネギ・ぶどう・レーズン・チョコレート・キシリトール)。 (petmd.com)
- 调理工程:
- 肉・魚は中心部まで十分に加熱する(例:75℃以上を意識)。
- 加熱、冷却、再加熱について適切に管理。
- 保存条件:
- 作り置きは冷蔵2日以内、冷凍2週間以内など目安を設定。
- 解凍・再冷凍・常温長時間放置を避ける。
- 定期的な健康チェック:
- 体重・体格(ボディコンディションスコア)・便の状態・被毛のツヤを月1回チェック。
- 半年〜1年に1回は血液検査・栄養数値(カルシウム・リン・アルブミン・肝腎機能)を獣医師と相談。
- レシピの見直し:
- 1年以上同じ配合で与え続けるのではなく、成長期・老齢・運動量の変化・体調によって見直す。
- レシピの出典・監修があるかを確認。無監修のレシピは“補足付きで使う”方が安心。
このチェックリストをノートやスマホに記録しておくと、「あれ?何か変だな」という初期サインを見逃さず、早めに対処できます。
“手作りごはん+総合栄養食”という
ハイブリッド戦略の提案
最後に、獣医師が現場で実際に推奨している「完全手作り」ではなく「手作りを市販の総合栄養食と併用する」ハイブリッド戦略を具体的にご紹介します。
これにより、手作りの“愛情”と、市販食の“栄養設計済み安心”を両立できます。
- American Animal Hospital Association(AAHA). “Homemade Pet Food Guidance: Teaching Clients to Avoid Common Pitfalls and Maintain Quality Control.” (2021) (AAHA)
- University of California, Davis “Evaluating Fresh Diets in Practice.” (2019) (Today's Veterinary Practice)
併用のモデルケース
- 基本は市販の総合栄養食(動物病院推奨やAAFCO基準のもの)を中心に。
- 週に2~3回、手作りごはんを“トッピング”として活用。例えば、肉・野菜を加えるだけ、または1食分を手作りに置き換える。
- 成長期や体調を崩した直後などのタイミングでは、市販食を継続しつつ、獣医師監修の手作りレシピを1週間分だけ導入してみる。
- 定期的に“手作り食を与えていない日”と“与えた日”で便・食いつき・体重・動きの違いを記録し、効果と違和感をチェックする。
この戦略であれば、「すべて手作りにしなければ」とプレッシャーを感じず、かつ安全性を確保しながら手作りの楽しみも味わえます。
特に飼い主さんが初めて手作りに挑戦する場合は、まずこのハイブリッド方式から始めるのが安心です。
今すぐできる
「安全な手作りごはんの準備」
手作りごはんを愛犬・愛猫に与えたいと考えたとき、まず気になるのが「安全にできるかどうか」「間違えて体調を崩さないか」という不安ではないでしょうか。
本章では“すぐ始められて、かつ安心できるステップ”について整理しました。
我が子の栄養ニーズを把握する ―
年齢・体重・健康状態別のポイント
まず最初に必要なのは、あなたのペット「この子」がどんな状況にあるかを知ることです。
年齢・体重・健康状態によって、必要な栄養量や制限が変わります。
例えば、成長途中の子犬・子猫は骨格形成や臓器発育のためにカルシウム・リン・タンパク質・脂質・ビタミンDなどの要求が高く、少しの偏りが発育障害につながることがあります。 (PMC)
一方、シニア犬・猫は消化機能や腎臓・肝臓の負担を考えて「高すぎるたんぱく質」「過剰な脂肪」「塩分」などを避ける必要があります。
さらに、持病(腎臓病・心臓病・消化器疾患・アレルギーなど)があるペットでは、標準の栄養設計では危険な場合もあり、専門家(獣医師または動物栄養士)への相談が推奨されています。 (Auburn University)
今日からできるステップ:
- 現在の体重/理想体重を測定(獣医師と相談)
- 年齢・活動量・健康状態を把握
- まず「この子にはどんな栄養が必要か(または制限があるか)」を紙やスマホに書き出す
与えて良い&絶対に避けるべき
食材リスト
次に重要なのは「何を入れるか」だけでなく「何を入れてはいけないか」です。誤った食材を与えると、手作りごはんが逆にペットにとって危険になってしまうからです。
獣医師・動物栄養学の文献でも、手作り食の危険要因として「栄養不均衡」「食材中の有害物質」「細菌・寄生虫汚染」などが挙げられています。 (ResearchGate)
⭕️ 与えて良い主な食材
- ヒューマングレードの鶏肉・赤身肉・魚(骨除去・加熱済み)
- 野菜(かぼちゃ・にんじん・ブロッコリー等。消化しやすいよう下処理)
- ごはん・玄米・麦などの炭水化物(活動量に応じて)
- 無塩・無添加の食材・控えめな油脂(オメガ3系を意識)
❌ 絶対に避けるべき主な食材
- 玉ねぎ・ネギ・にんにく類(赤血球破壊のリスク)
- ぶどう・レーズン・チョコレート・キシリトール(猫・犬ともに中毒リスク)
- 生の鶏肉・生卵(サルモネラ菌・寄生虫リスク)
- 過剰なレバー(ビタミンA過剰症)
- 塩分・調味料・香辛料の強いもの(腎臓・心臓負担)

このリストを見える化して、冷蔵庫横など分かりやすい場所に貼るとミス防止に役立つよ。
1回の食事で意識すべき
栄養バランス基準
手作りごはんを“ただ作る”だけでなく、“適切なバランスで提供する”ことが、獣医師が警戒する大きなポイントです。
文献では「多くのホームメイドレシピが栄養要件を満たしていない」ことが報告されています。 (PMC)
例えば、成犬の場合のひとつの目安が以下のように提示されることがあります(あくまで目安です):
- タンパク質:体重1 kgあたり約2.0〜2.5g
- 脂質:総エネルギーの20〜30%程度
- 炭水化物:活動量・体重維持に応じて調整(全体の30〜50%目安)
そして、カルシウム:リン比は1.2〜1.4:1を意識することが骨・歯の健康維持に重要です。
飼い主さんにおすすめの具体的な方法としては、まず「市販フードの栄養表示」と「手作り食の栄養想定値」を比較し、バランスが大きく崩れていないか確認することです。
「この子の場合、体重4kgなのでタンパク質は8〜10gを目安に」といった具合に、具体値を持つことで手作りを始めるハードルが下がります。
調理・保存の基本ルール
栄養バランスが整っていても、調理や保存が適切でなければ“危険性”は高まります。
獣医学の観点からも「手作り・生食・家庭調理は細菌・寄生虫・保存不良のリスクが高い」と指摘されています。 (Auburn University)
以下、家庭で実践すべき基本ルールです。
- 肉・魚は必ず中心部まで十分に加熱(例:75℃以上1分以上)
- 下処理後、室温に長時間置かない(2時間以内を目安)
- 作り置きは冷蔵で2日以内、冷凍保存なら1〜2週間以内を目安に使用
- 一度解凍した食材は再冷凍しない
- 調理器具(まな板・包丁・ボウル)は人用とペット用を分け、使用後は熱湯・洗剤で洗浄
- 食べ残しが少ないときは無理に与えず廃棄し、次の食事で調理量を見直す
こうした衛生管理を習慣にすることで、手作りを“安心して続けられる”土台ができます。
定期的チェック&“変化に気づく”
ためのサイン
手作りごはんを与えている場合、定期的に“健康のサイン”をチェックすることが獣医師の推奨です。
栄養バランス・調理・保存を守っていても、個体差や体調変化で異変が出る可能性があります。
文献でも、「ホームメイド食を与えたペットは、定期的な血液検査・体格チェックが望ましい」と記載されています。 (ResearchGate)
チェックすべき主なサイン
- 便の状態:形・色・回数・臭いの変化がないか
- 体重・ボディコンディションスコア(肥満・痩せすぎになっていないか)
- 被毛・皮膚の状態:ツヤ・抜け毛・かゆみ・湿疹の有無
- 食欲・水分摂取量の変化:急に食いつきが悪くなったり水を多く飲むようになった場合は要注意
- 活動量・姿勢・歩き方の変化:元気がなくなった・歩き方がぎこちない場合は栄養・骨格・関節に問題が出ている可能性
また、可能であれば「半年~1年ごとに血液検査(アルブミン・カルシウム・リン・肝腎機能)+獣医師による栄養相談」をして、「この手作りごはんで大丈夫か」をプロに確認することが安心につながります。
こうした“変化に気づく習慣”が、単なる“良さそうなごはんをあげる”から、“安心してあげ続けられるごはん”へと変わるポイントです。
手作りごはんを
選ぶべきor見送るべき
ケース別判断表
「愛犬に安心・安全な食事をあげたい。
でも言葉どおり手作りごはんにしても大丈夫?」と迷う飼い主さんにとって、最も知りたいのは「自分の子には手作りでいいのか/控えた方がいいのか」という判断基準ではないでしょうか。
そこで本章では、獣医師目線・栄養学的研究をもとに、手作りごはんを“積極的に検討すべき”状況と、“慎重に/避けた方がいい”状況を明確化し、さらに「判断に迷ったときに獣医師相談までのチェックリスト」も作成しました。
手作りごはんを「積極的に検討すべき」
4つの状況
以下のような状況にある愛犬は、「市販フードでは対応が難しいケース」もしくは「手作りに切り替えるメリットが明確にあるケース」と言えます。
こうした状況では、手作りごはんを選択肢として真剣に検討されると良いでしょう。
ただし、適切な栄養設計・獣医師あるいは栄養専門家への相談が前提です。
- 明らかな食物アレルギーがある場合
市販フードに含まれる複数の原材料や添加物に対してアレルギー反応を示すペットでは、原材料を自分で選べる手作りが有効な場合があります。
ただし、栄養バランスが崩れやすいため、獣医師・栄養士監修のレシピが望まれます。研究でも「ホームメイド食を処方された犬のうち、飼い主が改変を行うことで栄養が不均衡になった」ケースが報告されています。 (PMC) - 市販フードを食べてくれない/拒否反応・食いつき低下がある場合
「市販フードを与えても食べない」「吐く・下痢を繰り返す」というペットでは、手作りごはんを少量取り入れて食欲を促す方法が参考になります。ただし、単に食いつきだけを優先すると、「栄養バランスより好み優先」に陥るリスクがあります。 - 健康目的・特殊目的(減量・皮膚疾患・腸疾患など)がある場合
例えば腸疾患・皮膚アレルギー・多発食物制限などで、適切な市販フードが見つからないケースでは、手作りごはんを取り入れた“療法的な食事”が有効になることがあります。研究によれば、適正に設計された手作り食は「腸・皮膚系疾患の改善」に寄与したという報告もあります。 (PMC) - 飼い主自身が栄養・調理・保存管理に十分な準備ができている/関与できる場合
手作りごはんは、“手軽に見えて実はハードルが高い”というのが獣医師の見解です。米国の研究では、200件のレシピのうち95%以上が必須栄養素の1つ以上を満たしておらず、栄養不均衡になるリスクが極めて高いと報告されています。 (ucdavis.edu)
すなわち、飼い主自身が「年齢・体重・健康状態・栄養素・調理・保存・検査」について一定の知識・時間・意欲を持っていることが、手作りを検討する重要な条件です。
手作りごはんを
「慎重に/避けるべき」状況
逆に、手作りを選ぶことでリスクが高まる状況も明確にあります。
以下のようなケースでは、まず市販の総合栄養食を軸に、手作りを控えめに検討することをおすすめします。
- 成長期(子犬・子猫)
成長期には、骨格・臓器・免疫系の発達に向けて極めて厳密な栄養バランスが必要です。市販フードでも「子犬用・子猫用」として設計されており、手作りでは少しのズレでも成長障害を招く恐れがあります。研究でも「カルシウム・リンの比率が崩れた手作り食で骨格異常が発生した」という報告があります。 (PMC) - 老齢(シニア期)の犬・猫
代謝や消化機能が落ちていたり、腎臓・肝臓・心臓などに疾患を抱えていたりする場合、栄養管理がより繊細になります。手作りで極端に制限し過ぎる、あるいは過剰にしてしまうと、筋肉量の低下・免疫力の低下・体調不良を引き起こす可能性があります。 - 慢性疾患・治療食が必要なペット
腎臓病・心臓病・消化器疾患・アレルギーなど、既に特別な療法食または処方食を与えている場合、自己判断で手作りに切り替えるのは危険です。獣医師の監督・定期検査がないまま手作りを始めると、症状を悪化させるリスクがあります。
以上より、こうしたケースでは「まずは獣医師の監督下で市販フードを継続し、手作りは限定的に利用する」という考え方が適切です。 - 飼い主が栄養管理・調理・保存・検査に時間・知識・体制を確保できていない場合
手作りごはんは「ただ作る」だけでは済みません。材料選定・栄養計算・調理・衛生・保存・記録・体調チェック…と多くの要素が関わります。前述の研究では、飼い主がレシピを改変したり、サプリメント・調理法を誤ったりして栄養不均衡を招いたケースも多々報告されています。 (PMC)
このような場合、リスク回避の観点から「手作りをごく一部(トッピング程度)に留め、市販食を中心にする」戦略を推奨します。
判断に迷ったら“獣医師相談”までの
チェックリスト
「うちの子はどちらに当てはまる?迷う…」という飼い主さん向けに、判断を整理できるチェックリストを作成しました。
該当項目が多いほど、手作りを慎重に検討すべきです。
| チェック項目 | はい/いいえ |
|---|---|
| 年齢:子犬・子猫/シニア(7歳以上) | |
| 持病・治療中(腎臓・心臓・消化器・アレルギーなど)あり | |
| 市販フードで満足な食いつきがない・拒否反応がある | |
| 飼い主自身が調理・保存・栄養管理に十分な準備ができている/時間と体制がある | |
| 栄養バランスを確認できるレシピ(獣医師・栄養士監修)を使用する予定・使用している | |
| 定期的な健康チェック(体重・便・被毛・血液検査)を実施している・する予定がある |
判断アドバイス
- 「はい」の数が多い:手作りを検討して良いケース。ただし、必ずプロの相談を挟むこと。
- 「いいえ」が多い:まずは市販の総合栄養食を継続。手作りはトッピング・週1回程度など限定的に始める。
- 判断に迷う場合は、獣医師または動物栄養の専門家(ボード認定獣医栄養医)に相談することが最善です。
米国の研究では「無監修レシピを飼い主が改変した結果、栄養不均衡や疾病が発症した」ことが明らかになっています。 (PMC)
この記事を読み終えた今、「愛犬には手作りごはんが向いているか/控えた方がいいか」を判断できるのではないでしょうか。
何よりも大切なのは、“愛情+正しい知識+プロの関与”です。
手作りごはんは魔法ではありませんが、飼い主さんの意識次第で「安心して与えられる選択肢」になります。
まとめ
安全な手作りごはん判断のポイント
愛犬の「健康のために手作りごはんを与えたい」と思う気持ちは、多くの飼い主さんに共通しています。
しかし、実際には「手作りごはん=安全」ではなく、栄養の偏りや誤った調理による健康被害のリスクが存在します。
本記事で紹介した重要なポイントを整理しておきましょう。
● 手作りごはんを「積極的に検討すべき」4つの状況
- ① アレルギーが明確な場合:特定の食材や添加物への反応があるときは、原材料を管理できる手作りが有効。
- ② 市販フードを食べない・体調を崩す場合:食欲不振・下痢などの改善目的で、少量の手作り併用が有効。
- ③ 特定の健康目的がある場合:皮膚疾患・腸疾患・減量など、獣医師と相談しながら療法的に活用できる。
- ④ 飼い主が十分な知識と時間を持ち、専門レシピに基づいて実施できる場合:自己流ではなく、監修レシピを使用することが前提。
● 手作りごはんを「慎重に/避けるべき」状況
- ① 成長期(子犬・子猫):栄養バランスが少しでも崩れると、骨格や発育に悪影響を及ぼすリスクあり。
- ② 老齢期(シニア):代謝低下や慢性疾患が多く、過剰・不足どちらも健康悪化の原因に。
- ③ 慢性疾患・療法食が必要な場合:腎臓・心臓・消化器系などの病気がある場合、独自判断での手作りは危険。
- ④ 飼い主が栄養管理・保存衛生に自信がない場合:誤った加熱や保存で、細菌増殖や中毒を起こす恐れ。
● 手作りごはんを始める前にチェックすべきこと
- 年齢・体重・健康状態を正確に把握しているか
- 使用予定のレシピが獣医師・動物栄養士の監修によるものか
- 調理・保存・衛生管理を守れる環境が整っているか
- 便・体重・被毛など、健康変化を定期的に観察できているか
- 定期的に血液検査・健康診断を受ける習慣があるか
これらを満たしていれば、手作りごはんを“安全に”取り入れる準備が整っていると言えます。
● 獣医が推奨する最も現実的な方法

「手作りか、市販か」ではなく、「手作り+総合栄養食のハイブリッド方式」がベスト。
たとえば、
- 普段は総合栄養食のフードを与え、週に数回だけ手作りメニューを追加する。
- 手作りをトッピングとして使い、嗜好性や食欲アップを狙う。
こうした「併用スタイル」なら、栄養バランスを確保しつつ、飼い主の愛情と安心感も両立できます。
手作りごはんは、愛情を形にする素晴らしい方法である一方、知識・準備・継続管理が不可欠です。
判断に迷うときは、必ず獣医師や動物栄養士に相談し、自己判断で進めないことが大切です。
愛犬への愛情と知識が融合すれば、きっと「うちの子に合った最善の食事」見つかります。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

📚<主な参考文献>
- 環境省(2010). 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(ペットフード安全法)解説資料. 環境省.
- 福田, 靖(編著)(2018). 小動物栄養学 第2版. 文永堂出版.
- 日本獣医師会(編)(2019). 獣医療における栄養管理の考え方. 日本獣医師会.
本記事は、上記の獣医栄養学・獣医療に関する公開資料および専門書を参考に、一般の飼い主向けに内容を整理・解説したものです。
手作りごはんの安全性や適否は、犬の年齢、体格、健康状態、既往歴などによって大きく異なります。本記事は特定の食事法を推奨または否定するものではなく、実際の食事管理や治療方針については、必ずかかりつけの獣医師にご相談ください。