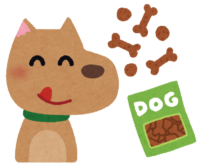
「ちょっと味見してみたら、意外とおいしいかも」
愛犬にあげるおやつを手に、そんな経験をしたことはありませんか?
「犬のおやつを人間が食べても大丈夫?」「どんなおやつなら安心?」「どうすれば特別な時間になるの?」
本記事では、そんな疑問に答えながら、“おやつ時間”をもっと豊かにするための新しい発想と実践アイデアを紹介します。
目次
犬のおやつを
人が食べる前に知ること

ペットショップの棚にずらりと並ぶ「犬用おやつ」。
愛犬にあげるとき、ふと「これ、私が食べても大丈夫なのかな?」と思ったことはありませんか?
本章記事では、飼い主の立場からそんな疑問にお答えしています。
”愛犬と同じおやつを食べてみたい”
飼い主の心理
愛犬の目をじっと見ながらおやつを取り出した瞬間、「ああ、自分も一口だけ…」と思ったことがある方は多いですよね。
この“飼い主心理”にはいくつかの深い動機が潜んでいます。
ひとつは「共体験欲求」、つまり愛犬と“同じもの”を共有したいという気持ち。
世の中のペット市場では「飼い主とペットの共食」がキーワードになってきています。
実際、あるペット用品店の取材では「新商品が出たときには、店長が自ら人間が味見することもある」と紹介されています。
もうひとつは「安心確認欲求」。
「人間が口にして安全なら、愛犬も安心して与えられる」という逆発想です。
そして三つ目は「好奇心・楽しみ欲」。見た目も香りも“おやつ”というカテゴリーならば、愛犬用でも「味ってどうなんだろう?」という興味が湧くのは自然なことです。
飼い主の3つの動機
次のような3つの動機もあるでしょう。
- 「味見してみたい」動機
→「可愛い愛犬が喜んでるもの、ちょっと自分も味わってみたい」という“飼い主の好奇心”。 - 「安全か知りたい」動機
→愛犬と暮らすために「このおやつ、人も犬も大丈夫?」という不安を抱える飼い主さんも少ないくないでしょう。
実際、専門サイトでも「犬用お菓子は人間が食べても全く問題ない」という記述がありますが、同時に「味はかなり控えめ」という注意点もあります。 (わんちゃんホンポ) - 「共食・シェアできるおやつを探している」動機
→飼い主さんとして「一緒におやつタイムを楽しみたい」という思いもあるでしょう。
最近では「人も一緒に食べられるおやつ」など、共食スタイルがトレンドです。 (ワンコnowa)

あなたはどれに当てはまりますか?
犬用と人間用の
おやつの違い

ペットショップで手に取る「犬用おやつ」。
見た目やパッケージだけでは、人間用のおやつと大きな差を感じないかもしれません。
しかし、実際には「犬用」「人用」で目的・基準・原材料が明確に異なっており、人が食べる時にも押さえておきたいポイントがあるのです。
本章では、原材料・安全基準・味や香りという3つの視点から、 「なぜ犬用と人間用は同じに考えてはいけないのか」について解説します。
原材料から見る
犬用と人間用おやつの違い
犬用おやつと人間用おやつの違いで、まず押さえておきたいのが原材料の考え方です。
犬用おやつは、「犬が健康に食べられるか」「犬の嗜好性が高いか」を最優先に作られています。 一方で、人間が食べることは前提にされていないため、人にとっては好ましくない原材料が含まれる場合もあります。
- 動物性副産物:内臓や骨、皮など、人用食品では避けられがちな部位が使われることがある
- 高ミネラル設計:犬の栄養補給目的で、人には過剰になりやすい
- 犬向け嗜好素材:匂いを強くする目的で、人によっては独特に感じられる成分が使われることがある
「無添加」「自然素材」と書かれていても、それは犬にとっての話です。
人が食べる前提とは少し考え方が異なる点として、知っておくと安心できるポイントです。
安全基準と目的から見る
犬用と人間用おやつの違い
人間用おやつと犬用おやつでは「何のために作られているか」「どのような安全基準で作られているか」という点に注目してみましょう。
■ 目的の違い
人間用おやつ
- 味・香り・食感・見た目などが消費者の嗜好に強く応じて設計されている。
- 市場競争も激しく、「おいしさ」「見た目」「満足感」が重視されている。
犬用おやつ
- 主に「犬が喜んで食べる」「栄養バランス・与えやすさ・歯のケア」など犬の視点・飼い主の利便性に重きが置かれている。
- 人間の味覚・嗜好には配慮されていない。

犬用おやつは「人が美味しく、安全に食べ続ける」ことを想定していないよ
■ 安全基準・表示義務の違い
人間用おやつ
- 人間用食品は「食品衛生法」「食品表示法」などによって厳しい表示義務・基準があります。
犬用おやつ
- 日本では「ペットフード安全法」が適用されていますが、人間用食品と目的が異なるため、基準や表示方法にも違いがあるとされています。
- 表示形式も「粗たんぱく質25%以上」「粗脂肪10%以上」など“以上/以下”での保証表示であり、人用食品のように「100gあたり炭水化物30g」などの形とは異なる。
このような違いから、犬用おやつが「人が食べても一応安全」というケースは多くても、「人間用と同じ満足感・同じ味・同じ表示精度」を期待するのは難しい、というのが実態です。
つまり、飼い主として「味見してもいいけど、期待を上げすぎないほうがいい」というスタンスが賢明です。
味や香りから見る犬用おやつの特徴
「犬のおやつ 人間が食べる」と検索する人の中には、 すでに食べてしまった、もしくは味が気になっているという方も多くいます。
実際に食べた人の感想で多いのは、次のような声です。
- 味がとても薄い
- 甘みや塩味がほとんどない
- 香りが独特で、人によって好みが分かれる
これは、犬用おやつが味覚よりも嗅覚を重視して設計されているためです。
犬は人間ほど味を感じないため、香りや食感で「美味しさ」を判断します。
人間が食べると「思ったより美味しくない」「違和感がある」と感じやすいのは、 人向けに調整されていないからであり、失敗や異常ではありません。
味や香りだけで「食べられるから安全」「美味しいから問題ない」と判断するのは危険です。
犬用と人間用のおやつは、似ているようで目的も基準もまったく違うことを理解したうえで、冷静に判断することが大切です。
犬のおやつを人が食べても
安全かを徹底解説
「飼い主としてたまには愛犬と“おやつタイムを共有”してみたい。でもこれって安全なの?」
本章では、法律・表示・製造工程などの観点から「人が犬用おやつを食べても大丈夫か?」について、SNSで話題の商品レビュー、実際に食べた人の声、そして知らないと危険な成分リストもご紹介します。
法律・表示・製造工程から見る
「人が食べられる」ライン
まず、安全性を論じるには、法的・表示的な側面を理解しておくことが重要です。
法律・規制の枠組み
日本では、犬用・猫用を含む愛玩動物用の飼料(ペットフード)は、ペットフード安全法の対象となっています。
犬用おやつもこの法の範囲に入る製品が多く、製造・販売事業者は表示義務などを遵守しなければなりません。 (maff.go.jp)
ただし注意点として、「ペットフード=人用食品と同じ基準」というわけではありません。
表示義務も、人用食品に比べて緩めであるという指摘があります。 (犬の健康おやつ専門店こらすぃおん)
表示内容・確認ポイント
ペットフード安全法では、例えば以下の項目が義務となっています:名称、原材料名、原産国名、事業者の氏名住所、賞味期限。 (maff.go.jp)
製造工程についても「有害な物質を含まない原材料」「微生物を除去する加熱・乾燥処理」などの基準があります。 (maff.go.jp)
「人間も食べられます」といった明記は、ペットフード安全法上の表示義務には含まれておらず、もしそのような表示がある場合は食品としての基準/保健所等の確認が必要です。 (maff.go.jp)
“人が食べられる”とはどういう意味?
ここで重要なのは、「人が食べても即座に命の危険があるような成分は入っていない可能性が高い」ということと、逆に「人間にとって味・栄養バランス・添加物量が人用食品と同じ基準ではない」という点です。
少量の“味見”レベルなら大きな問題にならないケースが多いという分析もあります。 (PET CUTIE INFO)

「人用おやつ代わりに常用しても良い」といわけではないよ⚠️
SNSで話題の
“人も食べられる犬用おやつ”の真相
「人も食べられます」と謳う犬用おやつがSNSで多く話題になっています。
実際にはどうなのか、レビューや現状を見てみましょう。
■ 話題の背景
例えば、あるペット用品店の取材記事では、「わんちゃんのおやつは、人間が食べても大丈夫なものを犬用にアレンジして作られています」という店長のコメントも紹介されています。 (sapporohassamu.aeonmallhokkaido.com)
■ 実際の評価は?
その記事では、ヒト試食後の感想として「味の薄いジャーキーって感じで、美味しい!!味の薄さが健康的」というコメントがありました。 (sapporohassamu.aeonmallhokkaido.com)
レビュー記事では「人間が食べても大丈夫な人用食材レベルを謳っているものでも、『味があまりしない』『食べ応えが薄い』といった評価が多い」という記録があります。 (おすすめドッグフードのABC)
「味が薄い」「ちょっと香ばしい」
実際に食べた人のリアルな声
安全性や表示がOKでも、「味・香り・食感」も気になりますよね。
実際に人が食べたときの声を見てみましょう。
味・香り・食感の傾向
レビューからは次のような共通評価があります:
- 味がかなり控えめ(薄味) →「人用おやつを想像すると物足りない」 (ロケットニュース24)
- 香りが強めの肉系ジャーキーなどは「酒のつまみになりそう」とも。 (おすすめドッグフードのABC)
- 食感が硬め/噛み応え重視 →人間用のおやつとしては「噛み疲れそう」という声あり。 (いまトピ)
注意したい点
- 「人より犬の味覚・嗜好に設計されている」ため、人が食べると“ちょっと物足りない”“味が想像と違った”と感じることが多い。
- 食べ続けると「栄養バランス」「カロリー」「塩分」などで人用食品に比べて見劣りする可能性があります。レビューでは「少量なら問題ないが常用は避けるべき」とする意見も。 (ペットフードマガジン)
知らないと危険!
犬には平気でも人が避けるべき
成分リスト
犬にはOKでも“人が食べる上で注意したい成分”を整理します。
注意すべき成分と理由
- 保存料・酸化防止剤(例:ソルビン酸K、亜硝酸Na) → 人用食品では規制や使用量が明確ですが、ペット用だと表示が任意・基準もゆるめという分析あり。 (ペットフードマガジン)
- 添加香料・着色料 → 犬用のおやつでは「嗜好性」を高めるために香り・風味が強めだったり、素材そのものの味を抑えたものがあるため、人が食べると「物足りなさ」や「違和感」を感じることも。
- 高タンパク/高脂肪設計 → 犬用設計のため、動物性タンパク質・脂質が多めの製品もあり、人が日常的に食べると栄養過多・消化負担につながる可能性あり。 (PET CUTIE INFO)
- 味付け控えめ/調味料少なめ → 動物の味覚・摂取基準に合わせてあるため、人用おやつとして期待する“塩気・甘み・香り”が不足し、「味が薄い」と感じる原因になります。
- 微量の食品用以外素材・処理工程 → 輸入素材やペット用規格基準の差があり、製造時の加工・保存体制が人用食品とは異なるケースも。 (ファンタジーワールド [FANTASY WORLD])
安全に味見・共用するためのチェックリスト
- 原材料名・表示ラベルを確認:犬用おやつでも「人も食べられる素材とかヒューマングレード」と明記されているか。
- 表示義務項目(名称・原材料・賞味期限・製造者)を確認。犬用おやつであっても「犬用/猫用」が明記されている必要あり。 (env.go.jp)
- 味見レベルにとどめる:量・頻度を控え目に。常用するものではないという前提を持つ。
- 愛犬と“共用”を楽しむなら、味・食感の違いを前提に「人向け軽めのおやつ+犬用おやつ」という形にする。
- アレルギー・消化器に敏感な人は慎重に:犬用おやつは人用の基準で設計されていないため、体質によっては合わない可能性あり。
“愛犬とおやつをシェア“
知っておきたい
チェックリスト
「愛犬が食べているおやつ、美味しそう…」「ちょっと味見してみたい」「せっかくなら一緒に食べたい」
そんな気持ち、実は多くの飼い主さんが抱いています。
しかし、気軽に“シェア”する前に知っておくべきポイントがあります。犬と人では体のつくりも、味覚も、必要な栄養も違うため、無条件で「大丈夫!」とは言えません。
本章では、愛犬とおやつを一緒に楽しみたい人のために、安全で楽しくシェアするための実践的なチェックリストをお届けします。
まず見るべきは原材料と成分表—
安心の見極め方
原材料の順番に注目
パッケージの裏に書かれた「原材料名」は、含有量が多い順に記載されています。
最初に記載されている原料ほど、そのおやつの主成分です。
人も食べるなら、まず「主原料が食肉・魚・野菜・穀物など、人用でも一般的に安全な素材か」を確認しましょう。
たとえば「鶏ささみ」「かぼちゃ」「さつまいも」「米粉」などであれば、人間が食べても安全性が高い素材です。一方で「動物性副産物」「ミール」「レンダリング製品」などの表記は、どんな部位が使われているか明確でないため、人が食べるには不向きといえます。
添加物・保存料・香料をチェック
犬用おやつには、嗜好性を高めるために香料や酸化防止剤が使用されている場合があります。
特に注意したいのは以下のような成分です。
- ソルビン酸K(保存料)
- BHA・BHT(酸化防止剤)
- 人工香料・着色料
これらは犬にとって許容範囲でも、人間の食品基準では使用量や扱いが異なります。
「ヒューマングレード」や「人も食べられる素材使用」と明記されている商品を選ぶと安心です。
■ 成分表で脂質・塩分を確認
人が食べる場合、特に塩分と脂質量はチェックポイント。
犬用おやつは人間の基準よりかなり塩分控えめですが、製品によっては動物性脂質が高く、「噛みごたえ重視」でカロリーが高めのものもあります。
「100gあたりのエネルギー」「脂質量」を確認し、少量を味見する程度にとどめましょう。
“人も犬も”で安全に食べるための
量とタイミング
量の目安は「ひと口サイズまで」
人も犬も食べられる素材のおやつであっても、人が一袋食べるのはやめましょう。
ペット用おやつはあくまで犬の体に合わせて栄養バランスが設計されています。人にとっては栄養過多になったり、消化に負担がかかる可能性もあります。
人が味見するなら、1〜2口程度が適量。
犬に与える場合も、「1日のカロリーの10%以内」が理想とされます。
たとえば5kgの成犬なら、1日に必要なカロリーはおよそ350kcal前後。
そのうちおやつは35kcal以内が目安です。
タイミングも大事
犬におやつを与えるタイミングは、「食事と食事の間」または「トレーニングのご褒美」としてが基本です。
人が同じタイミングで食べることで、“一緒におやつタイム”というコミュニケーションの演出ができます。
ただし、散歩直後や運動後など、犬の体温が上がっているときは避けましょう。消化に負担がかかることがあります。
人がコーヒーや甘いお菓子を一緒に食べる場合、犬にはそれを与えず、犬専用おやつだけを一緒に楽しむスタイルが安全です。
アレルギーに注意
犬にも人にも共通する注意点が「アレルギー」。
鶏肉・乳製品・小麦などは、犬にも人にもアレルゲンになりやすい食材です。初めてのおやつをシェアする場合は、少量から試すのが鉄則。
犬が舐めるだけ、人は小さくかじるだけ、という“試し食べ”からスタートしましょう。
ちょっとアレンジでさらに楽しく!
共用おやつの食べ方アイデア
せっかくなら、「愛犬と一緒に楽しめるおやつ時間」をもっとおしゃれに、楽しく演出してみましょう。
ここでは、無理なくできる“人犬共用おやつ”のアイデアを紹介します。
1. 冷凍フルーツヨーグルトバー
プレーンヨーグルトに、刻んだりんごやブルーベリーを加えて冷凍。
人はそのままデザートに、犬には小さく割って与えれば、夏にもぴったりのシェアおやつになります。
※甘味料入りヨーグルトやキシリトール入りは絶対に避けてください。
2. さつまいもクッキー
犬用さつまいもジャーキーを細かく刻み、小麦粉・卵・オリーブオイルを加えて焼くだけ。
人が食べるとほのかに甘く、犬には食物繊維たっぷり。シンプルで“両方OK”なヘルシースナックです。
3. 手作りチキンスープ
茹でた鶏むね肉と野菜を煮込み、塩分を加えずスープに。
人は味を見てからお好みで塩をプラス、犬には無塩のままで。
同じ鍋から取り分けて楽しめる“共食”スタイルは、愛犬家の間でも人気です。
4. 犬用ビスケットを“ディップ”で楽しむ
犬用ビスケットをクラッカー代わりにして、人はチーズや蜂蜜ディップを添えると、おしゃれなおやつプレートに。
犬にはそのまま与えればOK。香りを共有できるだけでも、犬はとても喜びます。

大切なのは「味を共有すること」ではなく、「時間を共有すること」だよ❣️
原材料を確認し、量やタイミングを守って、無理のない範囲でおやつタイムを楽しみましょう。
そして、「おいしいね」と笑い合える時間こそが、何よりのご褒美です。
人も犬も笑顔になる!
一緒に食べられるおやつ
おすすめと作り方
愛犬とひとときをともに過ごしていると、「このおやつ、私も味見してみたい」「せっかくだから一緒に楽しめたらいいな」という気持ちがふと湧いてきませんか?
しかし、ただ「人も食べられる」と謳われているからといって、何も考えずに“共用”してしまうと、安全性や満足度の点でギャップを感じてしまうこともあります。
本章では、飼い主さんの「味見してみたい」「安心して一緒に食べたい」という悩みに応えつつ、「ブランド紹介」「手作りレシピ」「メリット・デメリット」「栄養・カロリー設計」についてご紹介します。
実は増えている!人も食べられる
犬用おやつブランド5選
“人も食べられる”を謳うおやつブランドが、国内外で着実に増えています。飼い主としても「せっかくだから、愛犬と同じおやつを楽しみたい」という願いに応えてくれる存在です。ここでは、ブランドごとに特徴を紹介します。
- ヒューマングレード犬おやつ 黒毛和牛50 g:国産黒毛和牛を使用し、無添加設計。人にも安心して手に取れる素材を前面に打ち出しています。
- K9 ナチュラル フリーズドライ グリーン・マッスル50 g:ヒューマングレード食材を使ったフリーズドライおやつ。人が試食可能な品質という声も。
- PEGS トリムネ 無添加鶏むねジャーキー50 g:国産鶏むね肉を使用し、無添加・低脂質設計。飼い主も安心して少量味見可能なタイプ。
- ヒューマングレード鹿肉おやつ30 g:鹿肉・国産・無添加という条件を満たす希少なブランド。素材そのものの風味を人も犬も感じやすい。
- ダックレバー ケリー&コーズ:レバー系のおやつで高タンパク。人向けの珍しい素材感も「試してみたい」という興味を引きます。
加えて、国内ブランドでも「人も食べられる」ことを明言しているものがあります。例えば、
- iico:人も食べられる安心な設計で、「食品衛生法・ペットフード安全法を満たした品質」と説明されています。(goooods)
- コミフ:人が口にするものと同等の「食品」カテゴリで製造されており、「飼い主さんも一緒に食べられるおやつ」というコンセプトを打ち出しています。(コミフ)
家で簡単に作れる!
犬にも人にも優しい手作りレシピ
既製品だけでなく、「手作りして愛犬と一緒に食べるおやつ」という選択肢も魅力的です。
特別な材料を買わずにできるレシピを紹介します。
レシピ1:さつまいも&おからクッキー
材料:
- さつまいも(中) 1本(蒸して皮をむいて潰す)
- おからパウダー 50g
- 無添加プレーンヨーグルト 大さじ1
- オリーブオイル 小さじ1
作り方:
- さつまいもを蒸して潰し、おからパウダー・ヨーグルト・オリーブオイルを加えて生地を作る。
- オーブンを170℃に予熱し、生地を5mm厚に伸ばして型抜きまたは切り分け。
- 約20分焼き、冷めたら愛犬用に小さくカット、人用にはそのままどうぞ。
◎ポイント:砂糖・塩を使わないため、犬にも人にも優しいレシピ。人用なら蜂蜜やバニラを少量添えても。
◎ブログ収益化視点:完成写真・工程動画・簡単なアレンジ(例:チーズトッピング)を載せると読者の滞在率が上がります。
レシピ2:鶏ささみ&かぼちゃスティック
材料:
- 鶏ささみ 100g(茹でて細切り)
- かぼちゃ 50g(蒸して潰す)
- 全粒粉 40g
- 卵 1個(小型犬の場合は半分の量)
作り方:
- ささみ・かぼちゃ・全粒粉・卵を混ぜ、生地を作る。
- スティック状に形成し、160℃で15分焼く。
- 人用にはローズマリー軽く振っても◎。犬用はそのまま。
このように、“素材を共用できる設計”にすることで「一緒に食べられる!」という実感を読み手に与えられます。
共用おやつのメリット・デメリットを
冷静にチェック
「愛犬と同じおやつを食べられる」メリットがありますが、デメリットを整理しましょう。
◎メリット
- 飼い主と愛犬の「おやつタイム」が共有されることで、絆やコミュニケーションが深まる。
- 「人も安心して食べられる素材」という観点で選ぶことで、愛犬の健康意識も高まる。
- SNS映え・ブログネタとしても魅力:共用シーンの写真・レビューが動きやすい。
- 手作りレシピなら、素材コストを抑えて「ブログ収益化+読者満足」に繋がる。
×デメリット
- 味・満足感が人用おやつに比べて控えめであることが多く、「人用代わりにはならない」というギャップ。実際、ある編集部では「味の薄いジャーキーって感じで…」という感想が出ています。(sapporohassamu.aeonmallhokkaido.com)
- 栄養バランス/カロリー設計が犬用に偏っているため、人が“常用”するのは不向き。
- 犬用でも「人も食べられる」と謳っていても、アレルギー/消化面で人には合わない可能性あり。
- “共用”を過度に強調すると、犬用おやつとしての本来の目的(ご褒美、しつけ用)から外れてしまう恐れがある。
カロリー・栄養バランスを整えて
“おいしく安全”に楽しむコツ
せっかく人と犬でおやつを共有するなら、「美味しさ+安心+バランス」が重要です。
次のポイントを押さえておきましょう。
■ 人用として考えるなら
- おやつの1回量を「人の一口分」程度に抑える。例:50kg体重の人なら100〜150kcal程度までが目安。
- 脂質・塩分・糖分は控えめのものを選び、もし自作するならオリーブオイル・蜂蜜少量などで調整。
- 「素材そのまま風味」が強いおやつ(例:フリーズドライ肉系)では、噛む・飲み込むの速度・満足感が人用とは異なるため、ゆっくり味わうことを意識。
■ 犬用から共用する場合の配慮
- 犬用おやつは犬のカロリー・栄養に合わせて設計されているため、人が多く食べると栄養過多・カロリー過多になりやすい。
- 量を調整する(味見1〜2口、共用としては少量)こと。
- 手作りする場合、犬の体重・年齢・運動量を考えた上で一緒に楽しむ「少量バージョン」を作ると安全です。
- 栄養の視点で言えば、「タンパク質源・野菜・穀物」のバランスを考え、極端な成分偏り(例:高脂質・高タンパクのみ)を避けましょう。
- 「ヒューマングレード素材使用」「無添加・無着色」等の表示がある商品でも、表示が飼料扱いのものと「食品扱い」のものでは基準が異なるため、表示をよく読むこと。
よくある疑問Q&A:
犬の栄養と安全性の
観点から検証
「愛犬とおやつを分け合いたい」そんな気持ちは多くの飼い主さんに共通するものです。
しかし「犬のおやつを人間が食べても平気?」「逆に、人の食べ物を少しだけ犬にあげてもいい?」と迷う瞬間も多いでしょう。
本章では、犬の栄養と安全性の観点から、よくある質問をわかりやすく整理しました。
Q1:
犬用ジャーキー、
人間が食べても問題ない?
犬用ジャーキーは基本的に「犬の味覚と体に合わせて作られた食品」です。
そのため、人が食べてもすぐに害はない場合が多いものの、「人の食品基準ではない」という点には注意が必要です。
犬用おやつは、人間用の食品と比べて以下のような違いがあります:
- 衛生基準・保存料の扱いが異なる(人間向けよりも緩いことがある)
- 調味が薄い、またはまったくされていない
- 肉の部位や副産物が使われている場合もある
犬が安全に食べられる=人にも完全に安全とは限りません。
どうしても試したい場合は、成分表を確認し、加工肉や添加物が少ない無塩タイプを選ぶようにしましょう。
あくまで「一口味見」程度にとどめるのが安心です。
Q2:
人間用クッキーを犬に分けてもいい?
見た目も香りも甘くて美味しいクッキー。
つい「少しだけなら」と思ってしまいますが、人間用のクッキーは犬にとってリスクが高い場合があります。
主な注意点は以下の通りです:
- 砂糖・バター・塩分が多い
- **チョコレート・ナッツ・人工甘味料(キシリトール)**など、犬に有害な成分が含まれている可能性
- 消化しづらい小麦粉を多く使用している場合も
一見シンプルなプレーンクッキーでも、バターや砂糖の量が犬の体には負担となることがあります。
どうしても一緒に楽しみたいときは、「人も犬も食べられる素材(米粉・豆乳・はちみつ少量)」で作った共用レシピを利用しましょう。
Q3:
“人も食べられる”表示って
本当に安全?
最近は「人も犬も食べられる」と表示されたおやつを見かけることがあります。
確かに安心感はありますが、その表現には注意が必要です。
この表示は、「人間が口にしても健康被害が出ない程度の品質」という意味であり、
人間用としての味・栄養バランスが保証されているわけではありません。
つまり、次のように考えるのが正確です:
「人が食べても害はない」=「人にとっておいしい・栄養的に優れている」ではない。
「犬が食べても安全」=「毎日与えてもバランスが取れる」ではない。
購入の際は、「原材料・成分表・製造元の安全基準」をチェックしましょう。
特に添加物・保存料・塩分・糖分の含有量が少ないものほど、共用に向いています。
Q4:
共用おやつばかりあげると
犬の栄養が偏る?
「人も犬も食べられるおやつ」だからといって、毎日そればかりを与えるのは避けたほうがよいでしょう。
なぜなら、犬の体に必要なたんぱく質・脂質・ビタミン・ミネラルのバランスが、人間とは大きく異なるためです。
犬の主食であるドッグフードは、栄養バランスを綿密に計算して作られています。
一方、共用おやつは「補助的なお楽しみ」として設計されているものがほとんどです。
与え方の目安は次の通りです:
- 1日の摂取カロリーの10%以内におさえる
- あげる時間は食後2〜3時間空ける
- 手作りする場合は塩・砂糖・油分を極力控える
愛犬と同じおやつを楽しむことは素敵な時間になりますが、その「一緒に食べる幸せ」を特別なイベントとして楽しむのがおすすめです。
💡犬用・人間用を問わず「安全性」「栄養バランス」「与える頻度」を意識すれば、愛犬とのおやつタイムをより安心して共有できます。

大切なのは「お互いに無理なく、美味しく、健康的に楽しむこと」だよ❣️
“おやつ時間”を
もっと特別にするアイデア
愛犬とのおやつ時間。それはただ「食べる」だけの時間ではありません。
最近は、「犬のおやつを人間が食べる」ことをきっかけに、一緒に楽しむ“共食文化”が少しずつ広がっています。
本章では、おやつを通じて絆を深め、SNSでも話題になるような新しい楽しみ方、そして環境にも配慮した“未来型おやつ”の選び方を紹介します。
おやつが絆を深める
愛犬とのシェア体験がくれる心理効果
「一緒に食べる」という行為には、言葉を超えたつながりがあります。
心理学的にも、共食は信頼関係を強め、安心感を生む行為として知られています。
愛犬におやつをあげるだけでなく、自分も同じおやつを一緒に口にすることで、
「同じものを共有している」という一体感が生まれます。
実際、犬は人間の表情や動作にとても敏感。
飼い主が楽しそうに食べる様子を見るだけで、犬のオキシトシン(幸せホルモン)分泌が高まるという研究もあります。
おやつをシェアする時間は、単なる“ご褒美タイム”ではなく、お互いの幸福感を共有するセラピーのような時間なのです。
SNSで話題!
犬と一緒に楽しむ
フォトジェニックおやつ
「#犬のおやつ」「#一緒におやつ」「#dogtreattime」などのハッシュタグには、
愛犬とおそろいのおやつを楽しむ投稿があふれています。
“人も犬も食べられる”おやつは見た目にも可愛らしく、SNS映えする写真を撮るにはぴったりのテーマです。
フォトジェニックに撮るコツは3つ:
- 自然光で撮る – 朝や夕方の柔らかい光が、毛並みやおやつの質感を美しく見せます。
- 同じ構図で「おそろい感」を出す – お皿を並べて、「人用」「犬用」を同じ形で撮ると統一感が生まれます。
- リアクションを撮る – 犬が食べる瞬間の表情や舌を出す姿は、自然で愛らしく、見る人の心を惹きつけます。
見た目の美しさだけでなく、「一緒に食べる喜び」が伝わる写真は、多くの飼い主たちの共感を呼びますよ。
地球にもやさしい選択
サステナブル素材のおやつを選ぶ理由
最近注目されているのが、「サステナブル素材を使った犬のおやつ」。
たとえば、おから・米粉・昆虫タンパク・規格外野菜など、廃棄を減らす素材を活用した商品が増えています。
これらの素材は、環境への負担を減らすだけでなく、栄養価が高く消化にもやさしいのが特長。
人も犬も安心して食べられるものが多く、
「食を通して地球にも配慮できる」という点で、意識の高い飼い主に支持されています。
たとえば、昆虫タンパクを使ったクッキーや、おからとサツマイモの焼き菓子などは、
犬にも人にもやさしく、“美味しさ”と“エシカル”を両立できる新時代のおやつといえるでしょう。
これからのトレンドは
“ヒューマングレード”
「ヒューマングレード」とは、人間が食べても問題ない品質基準で製造されたペットフードのこと。
今、世界中で注目を集めているトレンドです。
この流れの背景には、次のような価値観の変化があります。
- “家族同然”の存在にふさわしい食の安心を求める人が増えた
- 自分の健康志向(オーガニック・グルテンフリーなど)を愛犬にも反映させたい
- 一緒に食卓を囲む時間を大切にしたいというライフスタイルの変化
ヒューマングレードのおやつは、品質・安全・共感をキーワードに進化を続けています。
将来的には、「犬用」「人用」という境界があいまいになり、
“共に食べること”そのものが、ペットライフの中心になっていくでしょう。
まとめ:
犬のおやつを
“人も一緒に楽しむ”
犬用おやつの中には人も安全に食べられるものがあり、共に味わう時間が愛犬との絆を深めるきっかけにもなります。
しかし一方で、“人が食べても安全”と“人の食品として作られている”ことはまったく別の話です。
人と犬が一緒のおやつを楽しむための重要なポイントをまとめました。
- 犬のおやつを食べてみたい理由は主に3つ
「味見して安全性を確かめたい」「愛犬と同じものを共有したい」「興味や話題性」。どれも自然な心理ですが、まずは安全確認が最優先です。 - 犬用おやつと人間用おやつは“基準”が違う
犬に安全な成分でも、人が多量に摂取すると消化不良やアレルギーを起こす場合があります。食品衛生法の対象外である点も理解しておきましょう。 - 「人も食べられる」と表示されていても注意
これは“食べても害がない”という意味であり、“人間の食品基準を満たしている”わけではありません。過信せず、製造元や原材料を確認するのが鉄則です。 - 安心のチェックポイントは3つ
①原材料の明記があるか
②保存料・着色料が少ないか
③製造元がヒューマングレードに対応しているか - 共用おやつの取り入れ方
・量は犬の体重に合わせて控えめに
・人と分ける際は、味付けをしないプレーンタイプを選ぶ
・一緒に食べる時は「特別な時間」として与えるのがおすすめです。 - おすすめはヒューマングレードや手作り
人間が食べても安全な基準で作られた「ヒューマングレード」のおやつや、少ない材料で作れる手作りおやつは、共用に最も適しています。 - 専門家の意見も参考に
栄養士やペットフードアドバイザーの監修情報をチェックし、愛犬の健康状態に合わせたおやつ選びを心がけましょう。 - おやつは“楽しみ”であり“絆づくりの時間”
共に食べることで、信頼関係や幸福感が高まるという心理的メリットも。写真やSNSでシェアする楽しみ方も広がっています。
人と犬が“同じおやつを分け合う”時代は、単なるトレンドではなく「より深く寄り添う関係」の象徴です。
安全性を守りながら、あなたと愛犬だけの“特別なおやつ時間”を楽しんでください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

📚<主な参考情報>
- 消費者庁. (n.d.). ペットフードの安全確保について. 消費者庁.
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/other/pet_food/- 日本獣医師会. (n.d.). ペットフードの与え方と注意点. 公益社団法人日本獣医師会.
https://jvma-vet.jp/pet_owner/petfood/- 農林水産省. (n.d.). ペットフード安全法について. 農林水産省.
https://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/petfood/- イオンモール札幌発寒. (n.d.). ペット用品店スタッフが語る「人も味見する犬用おやつ」の実情. イオンモール札幌発寒公式サイト.
https://sapporohassamu.aeonmallhokkaido.com/lp/aruco/detail/aruco_392507.html- ワンコnowa. (n.d.). 人も一緒に食べられる犬用おやつが人気の理由. ワンコnowa.
https://wankonowa.com/column/1873/- わんちゃんホンポ. (n.d.). 犬用お菓子は人間が食べても大丈夫?注意点と味の特徴. わんちゃんホンポ.
https://wanchan.jp/food/detail/13008本記事は、犬用おやつと人間の食の安全性に関する一般的な情報提供を目的とし、上記の公開情報・専門メディアを参考にまとめたものです。
人が犬用おやつを口にすることの可否や安全性については、製品ごとの原材料表示や注意書きを必ず確認し、体調や状況に応じてご自身の判断で行ってください。