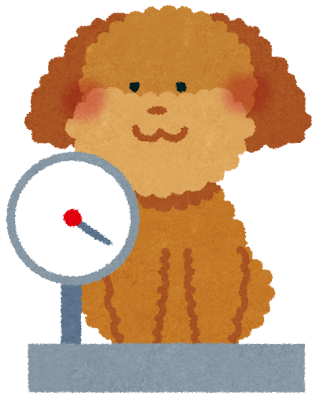
「手作りご飯に変えたのに、愛犬の体重が減ってしまった…」そんな経験はありませんか?
安全で栄養満点のはずの手作りご飯が、逆に痩せやすさの原因になることもあるのです。
本記事では、愛犬が健康的に体重を維持できる秘訣を詳しく解説します。
読み進めていただければ、今日から実践できる具体策がすぐにわかります!
目次
犬が手作りご飯で
痩せる理由

愛犬に手作りご飯を与えているのに、なぜか体重が減ってしまう…。
そんな悩みを抱える飼い主さんは少なくありません。
手作りご飯は安全で栄養価の高い食事として人気ですが、実はちょっとした工夫や知識がないと、痩せやすくなってしまうことがあります。
本章では、犬が手作りご飯で痩せる主な原因と、その背景について詳しく解説します。
栄養バランスの偏りが原因
手作りご飯で痩せてしまう最も多い原因は、栄養バランスの偏りです。
特にたんぱく質・脂質・炭水化物のいずれかが不足すると、体重減少につながります。
- たんぱく質不足:筋肉量や内臓の健康を維持するために必須。肉や魚を十分に与えないと、筋肉量が減り痩せやすくなります。
- 脂質不足:エネルギー源となる脂質が不足すると、体が脂肪を燃やして補おうとし、体重減少の原因になります。
- 炭水化物不足:犬は炭水化物をエネルギーとして完全に必要とするわけではありませんが、消化吸収しやすい炭水化物を少量加えることで、体重維持に役立ちます。
犬は人間よりもたんぱく質と脂質が重要なエネルギー源になります。
ヘルシー志向で胸肉や大量の野菜中心にすると、カロリー密度が低くなり体重が落ちる場合があります。
また手作りは水分が多く、見た目の量と栄養量が一致しない点も盲点です。

野菜中心や低脂肪志向の手作りご飯は、栄養バランスの偏りによって痩せやすくなるから注意が必要だよ。
カロリー計算の誤り
犬の必要カロリーは体重、年齢、犬種、運動量によって大きく変わります。
小型犬と大型犬では同じ体重でも必要カロリーは異なり、間違った計算は痩せる原因になります。
たとえば、小型犬は消化能力が小さいため、少量でもエネルギー不足になりやすく、大型犬は筋肉量に応じた十分なカロリーが必要です。
手作りご飯では、食材ごとのカロリーを把握し、1日の総カロリーを計算して調整することが体重維持の基本です。

1食あたりのカロリーを計算しないと、必要カロリーに届かないことがあるよ・
よくある間違い!
- 胸肉中心で低脂肪・低カロリーになっている
- 野菜の割合が多く、実質カロリーが不足している
- 脂質を避けすぎている(脂質は犬の重要なエネルギー)
- 炭水化物がほとんど無いメニューになっている
特に脂質は1gあたり9kcalと高エネルギーです。
痩せている犬には適量の良質な脂(魚油、鶏皮、オリーブオイル少量など)を加えることで改善するケースが多く見られます。

3分でできる簡単チェック!
- 1週間分の食事メニューを書き出し、肉・脂質・炭水化物・野菜の割合を確認する
- 1日の総量をドライフード換算で比較(ドライのカロリー基準で必要量と比べる)
犬種・年齢・体質の影響
犬種や年齢、体質によっても痩せやすさは異なります。
消化吸収能力や基礎代謝量に差があるため、同じ食事でも痩せやすい犬とそうでない犬が存在します。
犬種の影響
柴犬やトイプードルなど、筋肉量が少ない犬は痩せやすい傾向があります。
また、チワワやポメラニアンなどの小型犬は、数十グラムの変化でも見た目や健康に影響します。

微妙なカロリー不足が、短期間で体重低下につながることがあるから注意しよう!
年齢の影響
若くて運動量が多い犬や作業犬種は消費カロリーが大きく、同じ手作りメニューでも不足しやすくなります。
逆に老犬は消化吸収が低下し、手作りご飯でも栄養が足りず痩せやすい特徴があります。
体質の影響
軟便が多い、食べるのが遅い、嘔吐しやすい等の症状がある犬は吸収効率が落ち、必要な栄養が身体に行き渡らないことがあります。
隠れた病気の可能性
手作りご飯に切り替えたばかりなのに急に痩せた場合、病気の可能性も考慮する必要があります。
ご飯の影響だと思い込むと、本当の病気の兆候を見逃すことがあります。
特に「短期間で急激に痩せた」場合は、まず健康チェックを最優先にしてください。

愛犬の様子を毎日記録しておくと、いざという時に役立つよ❣️
以下の症状が同時にある場合は速やかに獣医師に相談してください。
獣医師に相談すべき症状
- 飲水量の増加(腎疾患や糖尿病の可能性)
- よく食べるのに体重が減る(甲状腺機能亢進症など)
- 慢性的な下痢・軟便(吸収障害や膵炎など)
- 元気消失、著しい疲れやすさ
手作りご飯で愛犬が痩せる原因は、栄養バランスの偏り、カロリー計算の誤り、犬種・年齢・体質、そして隠れた病気など複数あります。
これらの要因を理解して食事内容や量を調整しましょう。
急激な体重減少や複数の異常が見られる場合は、自己判断せず早めに獣医師に相談することが重要です。
愛犬が手作りご飯で
痩せないための基本ルール

愛犬が手作りご飯を食べているのに痩せてしまう…そんな悩みは、多くの飼い主さんが抱える問題です。
手作りご飯は健康的で安心ですが、栄養バランスやカロリー管理を誤ると、体重減少につながります。
本章では、犬が手作りご飯で痩せないための基本ルールを紹介します。
必要カロリーの計算方法
手作りご飯で痩せてしまう最大の原因は、必要カロリーに届いていないことです。
実は手作りご飯は水分量が多く、見た目の量とカロリーが一致していないことが多いのです。
「前と同じ量を食べている」
「お腹いっぱいそうに見える」
と、感覚で判断しないようにしましょう。
基本となる考え方
- 犬の必要カロリーは「体重・年齢・活動量」で決まる
- 手作りご飯はドライフードよりカロリー密度が低い
- 野菜が多いほど、満腹でもカロリー不足になりやすい
基本の計算式としては、以下の方法があります。
・基礎代謝量(RER):70 × (体重(kg))^0.75
・1日のカロリー(MER):基礎代謝量 × 活動係数(小型犬1.6~2.0、中型犬1.4~1.8、大型犬1.2~1.6)
この計算により、必要カロリーを把握し、食事量を調整することで痩せるのを防げます。
特に小型犬は少量でもカロリー不足になりやすいため注意が必要です。
体重が落ちる前に、「この食事で必要カロリーを満たしているか?」を定期的に確認することが重要です。
理想の栄養バランス
栄養素の基本構成
犬の手作りご飯で意識したい基本構成は以下の通りです。
手作りごはんの基本構成
- 主役はたんぱく質(肉・魚・卵など)
- 脂質は控えるものではなく、調整するもの
- 炭水化物はエネルギー源として適量必要
- 野菜は「かさ増し」ではなく「補助」と考える
特に痩せてしまった犬の場合、脂質を避けすぎていることが多く見られます。
脂質は犬にとって重要なエネルギー源であり、極端に減らすと体重維持が難しくなります。
栄養素のバランス
手作りご飯で痩せないためには、たんぱく質・脂質・炭水化物・ビタミン・ミネラルのバランスを整えることが重要です。
栄養バランス
- たんぱく質:
40〜50%。筋肉や臓器の健康維持に不可欠。 - 脂質:
30〜40%。エネルギー源として体重維持に重要。 - 炭水化物:
10〜20%。消化吸収が良く、体力維持に役立つ。 - ビタミン・ミネラル:
野菜やサプリで補う。
※あくまで一般的な目安であり、愛犬の体質や状態によって調整が必要です。

偏った配分では痩せやすくなるよ。
毎日の食事で栄養バランスを意識してね❣️
食材選びのポイント
犬の手作りごはんでは、どんな食材を選ぶかによって栄養バランスや体調への影響が大きく変わります。
本項では、よく使われる食材と選ぶ際のポイントを整理します。
よく使われる食材と選び方の目安
| 食材の種類 | ポイント | 注意点 |
|---|---|---|
| 鶏肉・白身魚 | 高たんぱくで消化しやすい | 脂身や皮は控えめにする |
| 牛肉 | エネルギー補給に向く | 脂肪分が多い部位は避ける |
| かぼちゃ・さつまいも | 炭水化物源として使いやすい | 与えすぎるとカロリー過多になりやすい |
| 緑黄色野菜 | ビタミン・食物繊維を補える | 加熱して細かく刻む |
ただし、愛犬の体質やアレルギー、持病によって適さない食材もあるため、初めて与える際は少量から試し、体調の変化をよく観察してください。
手作りご飯で避けたい食材
手作りご飯では、安全性の面だけでなく、体重維持の観点から避けたい食材もあります。
一般的に知られている危険食材に加え、使い方次第でカロリー不足を招きやすい点にも注意が必要です。
| 食材 | 理由 |
|---|---|
| 玉ねぎ・にんにく | 中毒の危険があり、少量でも健康被害の可能性 |
| ぶどう・レーズン | 腎障害の報告があり、安全量が不明 |
| チョコレート | テオブロミン中毒のリスク |
これらは、犬にとって有害とされている食材です。
少量でも健康に影響を及ぼす可能性があるため、手作りごはんでは使用しないようにしましょう。
また注意したいのが、低脂肪・低カロリー食材ばかりを選んでしまうケースです。
ささみや野菜は、手作りごはんに取り入れやすく栄養価の高い食材です。
ただし、低脂肪・低カロリーな食材だけで食事を構成してしまうと、必要なエネルギーが不足し、体重が落ちてしまうことがあるので注意しましょう。
「手作りごはんで必要なカロリーを満たせているか」という視点を忘れないことが、手作りご飯で痩せないための重要なポイントです。

愛犬の好みや消化のしやすさも考慮して、毎日の食事にバリエーションを持たせることも大切だよ❣️
痩せにくい食事構成のポイント
手作りご飯では、使う食材によって“太りやすさ・痩せやすさ”は大きく変わります。
痩せにくい食事を目指すなら、以下のポイントを意識してください。
痩せにく食事のポイント
- 鶏胸肉だけでなく、もも肉や赤身+脂身を組み合わせる
- 白身魚だけでなく、サーモンなど脂のある魚も取り入れる
- 野菜は低カロリー食材ばかりに偏らない
- 炭水化物を極端に抜かない
体重が落ちている愛犬には、ダイエット向け食材ばかりを使っていないか、一度立ち止まって見直してみましょう。
手作りご飯と
ドライフードの併用のメリット
手作りご飯だけではカロリーや栄養素の管理が難しい場合、ドライフードとの併用がおすすめです。
ドライフード併用のおすすめポイント
- カロリー調整:
ドライフードを少量混ぜることで、必要なカロリーを安定して摂取できます。 - 栄養補助:
ビタミンやミネラルが強化されたフードを併用することで、偏りを防げます。 - 食いつき改善:
手作りご飯にドライフードを加えることで香りや食感が増し、食欲を刺激できます。
この併用方法は、手作りご飯の魅力を損なわずに体重管理を行うための家庭でできる実践的な工夫です。
手作りご飯で愛犬が痩せないためには、必要カロリーの把握、理想の栄養バランス、食材選びの工夫、そしてドライフード併用によるカロリー・栄養補助が重要です。
併用は妥協ではなく、愛犬の体調を優先した現実的な選択です。
「痩せないこと」を最優先に考えるなら、ぜひ選択肢の一つとして検討してみてください。

わが家も、手作りごはんとドライフードの併用です🐶
犬が手作りご飯で
痩せたときの対処法
愛犬に手作りご飯を与えているのに体重が減ってしまった場合は、痩せてしまう原因を見極め、適切な対策を取ることが重要です。
本章では、愛犬の体重減少に気づいたときに実践できる具体的な対処法を解説します。
急激な体重減少の判断基準
愛犬が急激に体重を減らしている場合は、注意が必要です。
目安としては以下のような場合に注意しましょう。
- 1週間で体重の5%以上減少している
- 食欲はあるのに体重だけが減っている
- 元気がない、毛艶や皮膚の状態が悪化している
これらの症状が見られる場合は、単なる食事管理の問題だけでなく、病気の可能性もあるため、早めに原因を特定することが重要です。
食事量の調整と回数
痩せやすい犬の場合、1回の食事で必要なカロリーを摂取するのは難しいことがあります。
そこで少量多回の食事が有効です。
- 1日2回の食事を、3~4回に分ける
- 吸収率が良くなるように、柔らかく調理した食材を与える
- 好物の食材やトッピングを活用し、食欲を刺激する
少量多回にすることで、消化吸収効率が向上し、体重減少を防ぐ効果があります。
サプリメントや栄養強化の活用
手作りご飯だけではどうしても不足しやすい栄養素があります。
そんな時はサプリメントや栄養強化食品の活用が有効です。
- ビタミンやミネラルの補給に、犬用マルチビタミンサプリを追加
- オメガ3脂肪酸で皮膚や毛艶をサポート
- 高カロリー補助食品でエネルギーを補う
サプリを使う場合も、過剰摂取にならないように、推奨量を守ることが大切です。
獣医師に相談すべきタイミング
自己判断で対処しても改善が見られない場合、獣医師への相談は早めに行いましょう。以下の状況では特に注意が必要です。
- 1週間で体重が5%以上減少した場合
- 食欲が落ち、元気もなくなってきた場合
- 便や尿に異常が見られる場合
- 毛艶や皮膚に変化がある場合
獣医師に相談することで、隠れた病気の早期発見や、適切な栄養補助の提案を受けられます。
体重管理だけでなく、愛犬の健康全般を守るために重要なステップです。
手作りご飯で愛犬が痩せてしまった場合、原因の特定と食事調整、サプリの活用、そして必要に応じた獣医師相談が基本の対処法です。
これらを組み合わせることで、健康的に体重を回復し、愛犬の元気を取り戻すことができます。
成功・失敗パターンからの
学びと教訓
愛犬の健康を考え、手作りご飯に切り替えたのに痩せてしまった…。同じ経験をした飼い主は少なくありません。
成功例だけでなく、失敗からも学ぶことで、次の失敗を防ぎ、成功へのヒントを得ましょう。
手作りご飯で痩せてしまったケース
Aさんは、愛犬の健康のために野菜中心の手作りご飯を始めました。
しかし、食欲はあり順調に思えましたが、数週間後には愛犬の体重が減り、体が細くなってきたことに気づきました。
- 原因:栄養バランスの偏り(たんぱく質と脂質不足)
- 症状:体重減少、元気はあるが筋肉が落ちてきた
- 教訓:手作りご飯は安全でも、栄養バランスを無視すると痩せやすい

特に野菜や炭水化物中心の食事は、エネルギー不足に直結します。
「見た目の満足感だけでは体重維持はできない」ということがわかります。
改善して健康を取り戻したケーズ
飼い主Bさんは、愛犬が痩せてきたのを機に、食事量と栄養バランスを見直しました。
たんぱく質を増やし、脂質を適度に補い、少量多回の食事に変更しました。
さらに、獣医師に相談し、必要なビタミンやミネラルをサプリで補給しました。
- 結果:1ヶ月で体重が安定し、毛艶や筋肉も改善
- 工夫:手作りご飯とドライフードを併用し、カロリーと栄養を確保
- 学び:痩せた原因を正確に把握し、対策を組み合わせることが成功の鍵

「痩せたからといって食事量をただ増やすのではなく、栄養バランスを整え、吸収率を考えた食事管理が重要」ということがわかります。
陥りやすい間違い
チェックリスト
愛犬が手作りご飯で痩せる原因には、共通する間違いがあります。
以下のチェックリストで自分の管理方法を振り返りましょう。
チェックリスト
- 栄養バランスを無視して野菜や炭水化物中心の食事になっていないか
- 必要カロリーを計算せず、食事量だけで調整していないか
- 急激に手作りご飯に切り替え、消化不良や吸収不足を起こしていないか
- 獣医師に相談せず、健康状態の変化を見逃していないか
- 食事回数が少なく、一度に多量を与えて吸収が悪くなっていないか
これらのチェックポイントを押さえることで、愛犬が痩せてしまうリスクを減らし、健康を維持することができます。
手作りご飯は愛犬にとって素晴らしい食事ですが、正しい知識と工夫があって初めて「痩せない、健康的な食事」となります。
本章で紹介したケーズやチェックリストを参考にしてみてください。
手作りご飯で
痩せないためのポイント
手作りご飯は愛犬にとって安全で栄養豊富な食事ですが、適切に管理しないと痩せてしまうことがあります。
本章では、愛犬が健康的に体重を維持できる具体策を学びましょう。
愛犬の嗜好性を活かした
栄養補給法
犬は味覚よりも嗅覚で食欲が刺激されます。
食材の香りや食感を工夫することで、自然に栄養を摂取させることが可能です。
- 香りが強い食材を適量使用(鶏肉、魚、チーズなど)
- トッピングで食欲を刺激(煮干し粉や鶏レバーを少量加える)
- 固さや温度を工夫して食べやすくする(柔らかく煮る、少し温める)
これにより、食べむらが少なくなり、必要なカロリーや栄養素を自然に補給できます。
季節や活動量に応じた
カロリー調整法
犬の必要カロリーは季節や運動量によって変化します。
冬は寒さでエネルギー消費が増え、夏は暑さで食欲が落ちることもあります。
また、散歩や運動量が増える時期はカロリーも増やす必要があります。
- 寒い季節:脂質や炭水化物をやや増やして体温維持
- 暑い季節:水分補給と消化に優しい食材を優先
- 運動量増加時:高たんぱく・高エネルギー食材でサポート
このように、日々の活動や季節に応じて微調整することで、手作りご飯で痩せるリスクを減らせます。
家庭で簡単にできる栄養管理の工夫
栄養管理は難しそうに思えますが、家庭でも簡単に実践可能です。スマホアプリや表を使った管理法がおすすめです。
- スマホアプリで食材とカロリーを入力し、1日の総カロリーと栄養バランスを確認
- エクセルやノートで「たんぱく質・脂質・炭水化物・ビタミン・ミネラル」の摂取量を記録
- 週ごとに体重と食事内容を比較し、必要に応じて調整
- 好物や嗜好性のデータも記録し、食欲管理に活用
こうした管理法を取り入れることで、手作りご飯で痩せない食事作りが可能になります。
ポイントは「無理なく継続できる方法」を選ぶことです。
まとめ
手作りご飯で愛犬が痩せないようにするには、栄養バランスやカロリー管理だけでなく、犬の嗜好性や生活リズムも考慮することが重要です。
本記事でご紹介した独自のポイントを押さえて、愛犬の健康維持と体重管理を実現してください。
- 嗜好性を活かした栄養補給:香りや食感、トッピングを工夫し、自然に食欲を引き出す。
- 季節・活動量に応じたカロリー調整:寒い季節や運動量が多い時はカロリーを増やし、暑い季節や運動量が少ない時は消化しやすい食材を優先。
- 家庭で簡単にできる栄養管理:スマホアプリや表で食材・カロリー・栄養素を記録し、体重変化と照らし合わせて調整。
- 少量多回の食事で吸収率向上:一度に大量を与えず、1日3~4回に分けて与えることで消化吸収を助ける。
- 継続できる工夫が大切:無理なく続けられる管理方法を選ぶことで、手作りご飯の効果を最大限に活かせる。
これらのポイントを日々の食事に取り入れることで、愛犬が健康的に体重を維持し、元気で長生きできる生活をサポートできます。
本記事が皆さまの愛犬の健康維持の一助になれば幸いです。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

📚<主な参考文献>
- 一般社団法人 日本ペット栄養学会. (2020). 犬と猫の栄養ガイドブック. インターズー.
- 日本獣医師会. (2015). 小動物臨床栄養学. 文永堂出版.
- 日本獣医生命科学大学比較栄養学研究室. (2019). 犬の栄養学と食事管理. 学窓社.
- Brown, S. et al. "Nutrition for Dogs with Chronic Kidney Disease." Journal of Veterinary Internal Medicine, 2015.
- Polzin, D. "Chronic Kidney Disease in Dogs: Dietary Management." Veterinary Clinics of North America, 2013.
- Roudebush, P. et al. "Evidence-Based Nutritional Approaches for Managing Canine CKD." Veterinary Therapeutics, 2010.