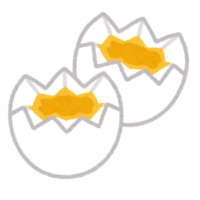
愛犬にも「ゆで卵」をあげてみたいと思ったことはありませんか?
実は、ゆで卵は犬にとって高タンパク・低脂質で、栄養バランスのとれたごちそう。
でも一方で、「白身はダメ」「半熟は危険」「与えすぎ注意」など、真逆の情報もあふれています。
「結局どうすれば安全なの?」「うちの子にもあげて大丈夫?」
そんなモヤモヤを解消するために、安心・安全な犬用ゆで卵レシピ」を徹底解説します。
読み進めていただければ、あなたの愛犬が喜ぶ、安心・安全な一皿が完成するはずです。
目次
犬にゆで卵を与える前に
知っておきたい基本知識

手作りご飯を考える飼い主さんにとって、「犬にゆで卵を与えてもいいの?」という疑問を一度は抱くのではないでしょうか。
見た目にも栄養たっぷりな卵ですが、人間と犬では消化や栄養バランスが異なるため、「与え方」や「量」に注意が必要です。
結論から言うと、完全に火を通したゆで卵は、犬にとって安全で栄養価の高い食材です。
ただし、アレルギーや消化不良のリスクもゼロではないため、「正しい知識」と「個体差への配慮」が大切になります。
本章では、ゆで卵が犬にもたらすメリットと、与える際の注意点を詳しく解説します。
犬にとってゆで卵は
どんな栄養源になるの?
卵は「完全栄養食品」と呼ばれるほど、バランスよく栄養が詰まっています。
特に犬にとって嬉しい栄養素は以下の通りです。
たんぱく質
卵のたんぱく質は、消化吸収率が高く、アミノ酸スコアが100点満点。
犬の筋肉維持、皮膚、被毛、内臓機能の健康維持に欠かせません。
特に、運動量が多い犬や成長期の子犬にとって、たんぱく質は欠かせないエネルギー源です。
ビオチン
ビオチン(ビタミンB群の一種)は、皮膚や被毛の健康維持に重要な栄養素です。
乾燥肌やフケ、毛艶の低下を防ぐ働きがあります。
生卵のままでは「アビジン」という成分がビオチンの吸収を妨げますが、ゆで卵にすることでこの問題は解消されます。
その他の栄養素も豊富
- 鉄分:貧血防止に役立つ
- ビタミンA:免疫力アップ
- セレン:抗酸化作用で老化予防
- 脂質:適度なカロリー補給源
これらの栄養素がバランス良く含まれているため、ゆで卵は「トッピング」や「おやつ」としても優秀です。
”ゆで卵=安心”と言われる理由
犬に卵を与えるとき、もっとも安全なのが「ゆで卵」です。
その理由は以下のとおりです。
ゆで卵が安全な理由
- 加熱することでサルモネラ菌のリスクが低減
- 卵白に含まれるアビジンの影響が弱まる
- 硬さがあり、与える量の調整がしやすい
- 余計な調味料を使わずに済む
特に卵白に含まれるアビジンは、生の状態だと「ビオチン(ビタミンB群)」の吸収を妨げるため注意が必要です。
十分に加熱することで、アビジンは変性してビオチン結合能が失われるため、”十分に加熱(固ゆで)”すればほぼ問題ありません。
半熟はサルモネラやアビジンの不活化が不完全な可能性があるため、愛犬に与える場合は、”完全に火を通した固ゆで卵”を選びましょう。
与える前に知っておきたい
デメリット・注意点
どんなに栄養豊富な食材でも、与え方を間違えると健康に悪影響を及ぼすことがあります。
ゆで卵も例外ではありません。ここでは、与える前に知っておきたいポイントを整理します。
与える量の目安を守る
卵は高カロリーかつ脂質が多いため、与えすぎると肥満の原因になります。
体重別の目安量は次の通りです。
| 体重 | 1日の目安量(ゆで卵) | 補足 |
|---|---|---|
| 2kg | 5〜8g(卵の1/10〜1/8) | カロリー比が大きいため少量で調整 |
| 3kg | 8〜12g(卵の1/8程度) | おやつレベルでの使用が安心 |
| 5kg | 12〜18g(卵の1/6〜1/5) | 1個丸ごとは多すぎるので分割推奨 |
| 8kg | 20〜28g(卵の1/4程度) | 運動量によって調整 |
| 10kg | 25〜35g(卵の1/4〜1/3) | 主食と合わせて総カロリーを確認 |
卵1個のカロリーは60〜100kcalと幅があり、一般的なM〜Lサイズでは約70〜90kcalになります。
上記の給餌量は「卵サイズによるカロリー差」を考慮した目安であり、愛犬の体調や運動量に合わせて微調整するとより安全です。
体重別の推奨量はあくまで目安であり、愛犬の基礎代謝や主食のカロリー、持病や治療食の有無を必ず考慮することが重要です。
特に腎臓病や膵炎などの持病がある犬は、自己判断せず獣医師の指示に従いましょう。

食事の主食ではなく、「補助的な栄養源」として扱うことがポイントだよ❣️
調味料は一切不
人間用に作る時と同じ感覚で塩・マヨネーズ・しょうゆを加えるのは絶対NGです。
犬は塩分耐性が低く、少量でも腎臓や心臓に負担をかける可能性があります。
「茹でるだけ・何も足さない」が鉄則です。
黄身と白身のバランス
アレルギーが出やすいのは白身です。初めて与える際は、黄身の少量からスタートしましょう。
黄身には脂質が多いので、肥満犬には白身だけを少量にするなど調整が必要です。
保存方法にも注意
余ったゆで卵は、衛生面の観点から保存期間に注意が必要です。
一般的な公的機関の情報では、殻付きの固ゆで卵は冷蔵で最長7日、殻を剥いた場合は2〜3日以内が目安とされています。
時間が経つと酸化が進み、風味が落ちるだけでなく消化にも悪影響を与えることがあります。

余ったゆで卵は冷蔵で2日以内に与えるようにしよう。
こんな愛犬は注意!
卵は基本的に安全な食材ですが、全ての犬に向いているわけではありません。
以下のようなケースでは、与える前に必ず注意が必要です。
子犬の場合
消化器官がまだ未発達なため、卵のたんぱく質をうまく分解できないことがあります。
最初は耳かき1杯分程度の黄身からスタートし、体調に問題がないか確認しましょう。
高齢犬の場合
高齢になると代謝が落ち、脂質を処理しづらくなります。
固ゆで卵を細かく刻み、消化の負担を減らす工夫を。
また、週1〜2回程度にとどめるのがおすすめです。
食物アレルギー持ちの犬の場合
卵アレルギーは珍しくないため、初回はごく少量から始めましょう。
皮膚の発疹、嘔吐、下痢、呼吸困難などの異常が見られた場合は速やかに獣医師に相談してください。
アナフィラキシーなど重症化の可能性もあるため、与える際は安全面に十分注意しましょう。
参考:POCHI ポチの幸せ
持病がある犬(膵炎・腎臓病など)
膵炎や腎臓病の愛犬には、脂質やたんぱく質の制限が必要な場合があります。
この場合、自己判断で与えず、必ず獣医師に相談してからにしましょう。
その他
- 肥満気味の犬
卵のカロリーは見逃されがちでう。普段の食事量と必ず調整しましょう。 - 早食いや丸飲み癖のある犬
卵白を細かく刻む、黄身をつぶすなどの工夫しましょう。

年齢・体重・犬種・個体差に応じた調整が必要です。
疑問があれば獣医師に相談しましょう!
愛犬の体質や年齢に合わせて調整しながら、安心・安全なゆで卵レシピを日々の食事に上手に取り入れよう。

「犬用ゆで卵レシピ」
基本編

「犬にゆで卵をあげても大丈夫?」
「実際にどうやって作ればいいの?」
そんな疑問を持つ飼い主さんもいるでしょう。
本章では、犬の健康を第一に考えたゆで卵レシピを、初心者でも失敗なくできるようにわかりやすく紹介します。
どんな愛犬にもやさしい「ゆで卵の与え方」まで丁寧に解説します。
材料・準備するもの(味付けなし、卵だけ)
犬用ゆで卵の材料は、とてもシンプルです。
材料(小型犬2〜3回分)
- 鶏卵:1個
- 水:適量(ゆでる用)

人間用のように塩や調味料を一切使わないようにしよう❣️
「塩を少しだけなら大丈夫?」と迷う飼い主さんもいるかもしれませんが、犬は人間より塩分に敏感で、わずかな量でも腎臓や心臓に負担をかけるおそれがあります。
マヨネーズやオイルを使うと脂質が多くなり、膵炎などのリスクが高まることもあるので控えましょう。

卵だけ・水だけが犬用レシピの基本中の基本だよ❣️
ゆで時間と調理のポイント
ゆで卵と一口に言っても、「半熟」「固ゆで」で栄養や消化のしやすさが少し変わります。
愛犬の体調や目的に合わせて選びましょう。
■ 固ゆで卵:消化が良くて安心
- ゆで時間の目安:10〜12分
- メリット:
加熱殺菌されており、サルモネラ菌の心配がない。
白身もしっかり固まり、消化吸収が安定している。 - 向いている犬:子犬、高齢犬、体調が安定しない犬、初めて卵を食べる犬。
■ 半熟卵:食いつきがアップ
- ゆで時間の目安:6〜7分
- メリット:
香りが良く、食いつきアップする。
加熱時間が短いため、ビタミン・ミネラルも比較的保持されやすい。 - 注意点:
完全に火が通っていないため、衛生管理が重要。
すぐに冷まして冷蔵保存は最長1日程度に留める。

栄養価に大差はないけど、初めて与えるなら固ゆでからスタートがおすすめだよ❣️
ゆで上がったら、流水でしっかり冷やすことで殻もむきやすくなり、食感もやわらかく仕上がります。
消化・安全のための工夫
愛犬にとって“食べやすさ”と“安全性”を両立するためには、仕上げの工程が大切です。
以下のポイントを押さえて、安心して食べられる状態に整えましょう。
■ しっかり冷ます
温かいままだと、内部に熱がこもり、口の中をやけどする危険があります。
特に小型犬は舌が敏感なので、手で触ってぬるい程度まで冷ましましょう。
■ 殻を丁寧にむく
卵の殻の破片が残ると、口内や消化器を傷つける恐れがあります。
流水の下で丁寧に殻を取り除き、薄皮も可能な限り取ってください。
■ 与えやすく刻む
犬のサイズや食べ方に合わせて、1cm角〜みじん切り程度にカット。
小型犬や老犬は細かく、噛む力がある成犬ならやや大きめでもOKです。
黄身と白身を軽くほぐして混ぜると香りが立ち、フードのトッピングにも使いやすくなります。
■ 保存のコツ
- 冷蔵保存:
ラップや密閉容器に入れて1〜2日以内に使い切る - 冷凍保存:
できるだけ避ける(解凍時に水分・風味が落ち、犬の食いつきが悪くなる
初めて与える時のポイント
愛犬に初めて与える時は、多くの飼い主さんが不安ではないでしょう。
「どれくらいなら大丈夫?」
その答えは、「初回はひとかけらサイズ(耳かき1杯分程度の黄身)から」が基本です。
■ ステップ① 少量テスト
まずは黄身をほんの少しだけ与え、24時間体調を観察します。
- 嘔吐や下痢
- 口周りや耳を掻く
- 皮膚の赤み・かゆみ
これらの症状がなければ、翌日以降に少しずつ量を増やしてOK。
「問題なさそう」と思っても、連日与えず、週2〜3回のトッピング程度から始めましょう。
■ ステップ② 与えるタイミング
おすすめは「朝食後のトッピング」または「おやつ時間(空腹時を避ける)」。
空腹のまま卵を食べると、脂質が刺激となり下痢を起こすケースがあります。
■ ステップ③ 与え方のアレンジ
- ドライフードに刻んだゆで卵を少し混ぜる
- 手作りごはんのトッピングにする
- 黄身をスプーンで少しだけ与える(高齢犬向け)
こうした工夫で、「特別感」を出しながらも負担なく与えられます。

犬用ゆで卵レシピのポイントは、「シンプルさ」と「安全性」だよ❣️
人の感覚で“味を足す”必要はなく、むしろ卵そのままの香り・食感が犬には魅力です。
「愛犬にゆで卵を食べさせてみたい」
「でも失敗したくない」
そんな飼い主さんこそ、今日紹介した方法をまずは試してみてください。
応用レシピ
もっと喜ぶゆで卵活用術
「シンプルなゆで卵だけでは物足りない」「せっかくなら、もっと栄養バランスの良いごはんにしてあげたい」、そんな飼い主さんのには、“応用ゆで卵レシピ”をおすすめします。
本章では、犬の健康を守りながら、食欲を刺激し、“食べる喜び”を感じてもらえる工夫を紹介します。
どれも手間は最小限。冷蔵庫にある材料+ゆで卵1個で、すぐ作れる簡単メニューです。
トッピング風:
ドッグフードにゆで卵をプラス
一番手軽で、毎日のごはんに取り入れやすいのが「トッピング風レシピ」です。
ドライフードの香りを引き立て、食欲が落ちた時にも“ひと口目”を誘います。
■ 作り方(小型犬1回分)
- 固ゆで卵(1/4個)を細かく刻む
- いつものドライフードにのせ、全体を軽く混ぜる
ポイントは、「白身と黄身を混ぜる」こと。黄身だけだと脂質が多くなり、白身だけだと香りが弱くなります。
両方を合わせることでたんぱく質・ビタミン・風味のバランスがとれ、犬の食いつきが格段にアップします。
■ 栄養メリット
- たんぱく質で筋肉や被毛の健康をサポート
- 黄身のビオチン・ビタミンB群で皮膚・毛艶を改善
- シニア犬の筋肉維持にも効果的
「フードは変えたくないけど、少しだけ手作り感を出したい」という飼い主さんにもおすすめの方法です。
混ぜごはん風:
野菜・お肉少量で手作り犬ご飯感アップ
ゆで卵に野菜やお肉を少し加えるだけで、簡単に“手作りごはん風”になります。
「完全手作りはハードルが高いけど、健康的に見える食事をあげたい」という方にぴったりです。
■ 材料(小型犬1回分)
- ゆで卵:1/2個
- 鶏むね肉(茹でまたは焼き):20g程度
- にんじん・ブロッコリーなどの野菜:大さじ1
- 白米(または炊いた雑穀ごはん):大さじ1
■ 作り方
- ゆで卵・鶏肉・野菜をすべて1cm角にカット
- 温かいごはんに混ぜるだけ(調味料不要)

熱すぎると香りが飛ぶよ。
食べやすいように、冷めてから与えてね。
■ 栄養バランスのポイント
- 卵と鶏肉で「動物性たんぱく質」がしっかり摂れる
- 野菜のビタミン・食物繊維で腸内環境をサポート
- ごはんで少し糖質を足すことで、エネルギー補給にも◎
また、食材をあらかじめまとめて茹でておけば、翌日のアレンジも簡単。
「1回作って2回分」のストック方式で続けやすいのも魅力です。
おやつ・ご褒美仕様:
スナック風レシピ
トレーニングやお留守番のご褒美に、栄養たっぷりの“ゆで卵スナック”を。
市販の犬用おやつより低脂質で、無添加。冷蔵庫にある材料で5分以内にできます。
■ ゆで卵ボール
材料:
- ゆで卵(黄身):1個分
- 片栗粉:小さじ1
- 水:少々
作り方:
- 黄身をフォークで潰し、片栗粉・水を混ぜて小さな団子状にまとめる
- フライパンで軽く焼く(油なし)
→ 表面はカリッと、中はほろっとした食感に。冷めたら一口サイズにして与えます。
■ こんな時におすすめ
- しつけトレーニングのご褒美
- 食欲がない時の“香りで誘う一口”
- シニア犬や歯が弱い犬の軽食

冷蔵で1日、冷凍で1週間以内に使い切ろう!
食欲が落ちた時・シニア犬向けアレンジ
年齢を重ねると、嗅覚が鈍くなり、固いものが食べにくくなります。
そんな時こそ、ゆで卵の香りと柔らかさが活きます。
■ 刻みゆで卵が最適な理由
- 消化しやすく、たんぱく質の吸収率が高い
- 香りが優しく、食欲を刺激しすぎずに自然に食べられる
- 柔らかく、歯や胃腸への負担が少ない
■ アレンジ例
- 固ゆで卵を細かく刻み、ぬるめのスープ(鶏スープなど)に混ぜる
- ドライフードに少しのゆで卵を加え、香りづけトッピングとして活用
- 食欲がない日は、黄身だけを少量ずつ与える
これだけで「食べるきっかけ」になることが多く、
「この一口が食べられたらまた元気が出る」というケースも珍しくありません。
犬のゆで卵レシピは、“与え方の工夫”ひとつで大きく変わります。
どのレシピも、
- 味付け不要で安全
- たんぱく質&ビタミン補給ができる
- 冷蔵庫の残り食材で手軽に作れる
という3つの共通点があります。
今日からあなたの愛犬のごはんに、ひと手間プラスしてみませんか?
“ただのゆで卵”が、愛犬にとって特別なごちそうに変わります。
安全性・バリエーション・
長期活用のコツ
「どう選ぶ?」「どのくらいの頻度で?」「長く続けても大丈夫?」という疑問を持つ飼い主さんも多いでしょう。
本章では、日常的にゆで卵を取り入れるうえで知っておきたい知識について解説します。
卵の選び方と保存のポイント
犬に与える卵は「新鮮で衛生的なもの」が基本です。
特に、殻にひびが入っていたり、常温で長時間放置された卵はサルモネラ菌のリスクが高まるため避けましょう。
- 選び方:産卵日または賞味期限が新しいものを選びましょう。スーパーで購入する際は、できるだけ冷蔵コーナーで販売されている卵を選ぶのがおすすめです。
- 産地:できれば国産卵を。流通経路が明確で鮮度が保たれやすく、管理体制もしっかりしています。
- 保存方法:冷蔵庫(10℃以下)で保管し、ゆでた後はその日のうちに与えるのが理想です。ゆで卵を作り置きする場合は、必ず冷蔵で保存し、2日以内には使い切りましょう。
また、ゆで卵を切ったあとに出る「黄身の黒ずみ」は酸化によるものなので問題ありませんが、腐敗臭や変色がある場合は与えないでください。
ゆで卵以外の卵調理 vs ゆで卵、
犬に適しているのはどっち?
卵は調理法によって栄養の吸収率や消化のしやすさが変わります。
では、犬にとって最適なのはどの調理法なのでしょうか?
- スクランブルエッグ:柔らかく消化しやすいですが、油を使う調理はNG。もし与える場合は「油なし・塩なし」で、テフロン加工のフライパンなどを使って加熱します。
- 目玉焼き:白身がしっかり固まっていればOK。ただし、焦げや油が酸化した部分は犬の胃に負担がかかるため避けましょう。
- ゆで卵:最も衛生的で保存性も高く、余計な脂質や塩分を含まないため、犬には「ゆで卵」が最もおすすめの調理法です。
簡単で安全性が高く、栄養をそのまま摂取できるのが「ゆで卵」。
毎日のフードに取り入れるなら、まずはここから始めるのがベストです。
毎日与えてもいいの?
結論から言うと、「毎日少量ならOK」。
ただし、全体のカロリーや栄養バランスを崩さない範囲で与えることが前提です。
卵1個(約60g)はおよそ90kcal。小型犬には多すぎるため、目安としては以下を参考にしてください。
- 小型犬(〜5kg):ゆで卵の1/4個(週に2〜3回)
- 中型犬(〜15kg):1/2個程度(週に3〜4回)
- 大型犬(15kg以上):1個まで(週に4〜5回)
与えすぎると脂質やカロリー過多になり、肥満の原因になります。あくまで「フードのトッピング」「たまのご褒美」として考えましょう。
ゆで卵を長期的に
レシピに取り入れる際の注意点
長期的に与える場合、以下の3点に注意してください。
①肥満に注意
卵黄には良質な脂質が含まれますが、摂りすぎるとエネルギー過多になります。
体重が増えやすい犬は、黄身を減らして白身メインにするのがおすすめです。
②アレルギーリスク
卵白は犬にとってアレルゲンになりやすい食材の一つです。
初めて与えるときはごく少量から始め、皮膚のかゆみや下痢などがないか観察しましょう。
③栄養の偏り
卵は完全栄養食品といわれますが、カルシウムや繊維などは不足しています。
あくまで「主食の補助」として扱い、バランスの良いドッグフードや野菜と組み合わせましょう。
ゆで卵を与えてはいけないケース
以下のような場合は、自己判断で与えるのではなく、獣医師に相談しましょう。
- 膵炎や脂質代謝異常がある犬(脂肪分が負担に)
- 腎臓病などでたんぱく質制限をしている犬
- アレルギー体質で、以前に卵を食べて下痢や発疹が出た犬
また、ゆで卵を与えたあとに次のようなサインが見られたら、早めに診察を受けましょう。
- 食欲不振・嘔吐・下痢が続く
- 皮膚をかゆがる、赤みが出る
- 便がいつもよりベタつく、臭いが強い
これらは軽度の食物不耐性から、重度のアレルギー反応まで幅があります。
愛犬の体調を観察しながら、適量・適頻度を守ることが、長く健康にゆで卵を楽しむコツです。
ゆで卵は「ちょっとしたご褒美」にも「栄養補助」にもなる万能食材。
ただし、その「ちょっと」が積み重なって体に負担をかけないよう、上手に取り入れていきましょう。
よくある質問 Q&A
Q:小型犬/大型犬で量はどう変わる?
犬にゆで卵を与える際の「適量」は、体重や年齢、運動量によって変わります。
一般的な目安として、体重5kgの小型犬で1/4個、10kgで1/2個、20kg以上で1個までが目安です。
卵は高たんぱく・高脂質の食品なので、あくまで主食の補助的なトッピングとして与えましょう。
特に去勢・避妊済みや運動量が少ない犬は、カロリーオーバーになりやすいため注意が必要です。
また、ゆで卵を与える頻度としては、週に2〜3回程度が理想です。
毎日与えるよりも、たまの「ご褒美」や「栄養補助」として取り入れることで、健康的に楽しめます。
Q:卵の白身だけ・黄身だけ与えてもいい?
結論から言うと、黄身だけ与えるのはOK、白身だけは注意が必要です。
白身には「アビジン」という成分が含まれ、ビタミンB群の一種である「ビオチン」の吸収を妨げる可能性があります。
一方で黄身は、鉄分・ビタミン・脂質がバランス良く含まれ、犬の毛艶や皮膚の健康をサポートします。
そのため、与えるなら黄身中心、白身は加熱したものを少量にするのが理想的です。
全卵をゆで卵にして与える場合は、完全に加熱されていれば問題ありません。生卵の白身だけ与えることは避けましょう。
Q:ゆで卵の殻は与えてもいい?
卵の殻にはカルシウムが豊富に含まれており、粉末にして少量与える分には問題ありません。
しかし、そのままの殻は絶対にNGです。鋭利な破片が口腔や消化管を傷つけるリスクがあるため危険です。
もし殻をカルシウム源として利用したい場合は、殻を完全に乾燥させてミルサーなどで細かく粉砕し、ごく少量(耳かき1杯程度)をフードに混ぜる方法が安心です。
Q:味付けありのゆで卵でもいい?
人間用に味付けしたゆで卵(塩、マヨネーズ、しょうゆ、サラダなど)は、犬には絶対に与えないでください。
塩分や脂質が過剰で、腎臓・肝臓・胃腸への負担になります。
犬用に作るときは、完全に味付けなしで茹でるのが基本です。
卵の自然な香りや甘みだけでも、犬にとっては十分に魅力的なおやつになります。
もし食いつきが悪い場合は、刻んだ卵を温かいフードに混ぜたり、香りの強い鶏むね肉スープを少量垂らして風味を加えるとよいでしょう。
Q:レバー・魚・お肉を控えている時、ゆで卵だけで代用できる?
ゆで卵は確かに高たんぱくで栄養価が高い食材ですが、完全に肉や魚の代わりにはなりません。
理由は、卵には犬に必要なアミノ酸や脂肪酸の一部が不足しているからです。
たとえば、肉類に多く含まれる「タウリン」や「EPA/DHA」などは卵だけでは補えません。
卵はあくまで「一部を補助する食材」として位置づけ、主食や他のたんぱく源と組み合わせてバランスを取ることが大切です。
もし持病やアレルギーで動物性たんぱくを制限している場合は、獣医師に相談のうえ、卵の量や頻度を調整しましょう。
まとめ
ゆで卵は、犬にとって高たんぱく・低脂質で消化吸収の良い優秀な食材です。
ただし、与え方や量を間違えると消化不良や肥満、アレルギーの原因になるため、正しい知識をもとに与えることが大切です。
犬とゆで卵のポイント
- ゆで卵は「固ゆで」で与えるのが基本
→生卵や半熟はサルモネラ菌のリスクがあるため避けましょう。 - 殻は必ず取り除く
→硬い殻は消化できず、のどや腸に詰まる危険があります。 - 与える量は体重に応じて調整
→小型犬は1/4個、中型犬は1/2個、大型犬は1個までが目安です。 - 与える頻度は週2〜3回程度が理想
→毎日は避け、栄養バランスを崩さないようにしましょう。 - 卵アレルギーに注意
→初めて与えるときは少量から試し、様子を見ましょう。 - 味付けは禁止
→塩・マヨネーズ・油などの調味料は犬の体に負担をかけます。
犬におすすめの
ゆで卵レシピのポイント
- 野菜や鶏むね肉と組み合わせると栄養バランスがUP!
→ビタミン・食物繊維が補え、消化にも優しい。 - 刻んでトッピングに使うとドッグフードの食いつきが改善
→食欲が落ちているシニア犬にもおすすめ。 - 手作りごはんにする場合は全体のカロリー調整を意識
→卵1個=約90kcal。体重に合った摂取量に調整しましょう。
こんなときは注意!
- 下痢や嘔吐などの消化不良の症状が出たらすぐ中止
- アレルギー体質や膵炎経験のある犬は獣医師に相談してから与える
- シニア犬・肥満傾向の犬には卵白中心にするのがおすすめ
この記事の結論
ゆで卵は「手軽で安全な良質タンパク源」として、愛犬の健康維持や食欲アップに大いに役立ちます。
しかし、“安全なゆで卵=与え方次第”です。
正しい調理法・量・頻度を守ることで、あなたの愛犬にとって最高の栄養おやつになります。
ゆで卵をきっかけに、犬の「食事の楽しみ」と「健康づくり」を両立させていきましょう。
本記事が、皆さまの愛犬が喜んでくれる一皿の一助に慣れれば幸いです。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

📚<主な参考文献>
出典・参考文献(APAスタイル)
- Benesse. (2023). 犬に卵を与えるときは加熱してから. いぬのきもちweb.
- Hill’s Pet Nutrition. (2023). 犬に卵を食べさせても大丈夫? Hill’s公式サイト.
- 農林水産省. (2022). 卵の保存と取扱いの注意. https://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/food-safety/egg.html
- 文部科学省. (2022). 日本食品標準成分表2022(八訂). 卵類の成分値.
- World Small Animal Veterinary Association. (2011). Global nutrition guidelines. WSAVA Global Nutrition Committee.
- U.S. Food and Drug Administration & U.S. Department of Agriculture. (2023). Egg safety and storage guidance.